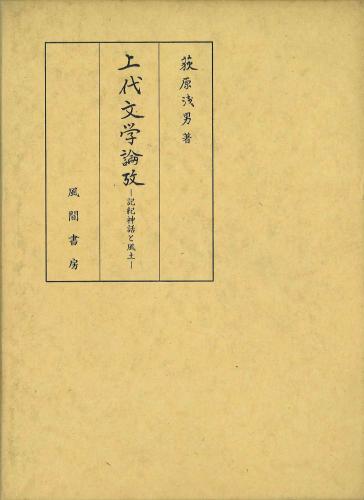
上代文学論攷
記紀神話と風土
定価14,080円(本体 12,800円+税)
過去数十年間に亙る「古事記」の神話とその風土・環境の探訪に裏付けられた私見と上代文学研究の成果を「記紀神話論」「風土論」「古事記研究書解題」等各編に収録。
【著者略歴】
荻原浅男(おぎわら あさお)
明治41年 長野県佐久市に生まれる。
昭和9年 松本高等学校(文甲)を経て
東京帝国大学国文学科卒業。
昭和13年 中華民国国立北京師範大学教授。
昭和15年 京城帝国大学助教授。
昭和25年 千葉大学(文学部)教授。49年に定年退官。千葉大学名誉教授
昭和49年 駒澤短期大学教授。同部長併任。
昭和56年 駒澤短期大学教授を定年退職、
同時に(福岡)純真女子短期大学教授に就任。60年同職を依願退職。
その他に多摩美術大学・都立大学(大学院)・電気通信大学・中央大学(大学院)等の講師を兼務。
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示
はしがき
第Ⅰ編 記紀神話論
第一章 神話原論
1 日本神話研究と国文学
2 上代古典の神話・伝説・説話とその文学性
3 日本神話研究の課題―方法論を中心として―
第二章 神話の構造
4 記紀所収の日月眼生伝の一考察
―特に中国の日月眼生伝との対比を中心に―
5 日神・素神の「うけひ」神話の機構
6 大山津見神と大三島
―イザナキ・イザナミ両神の国生み神話考―
7 「塩こをろこをろに」考
―イザナキ・イザナミ両神の聖婚神話考―
第三章 神人の像
8 大国主と大物主
9 悲劇的英雄倭建命
10 古代史(書紀)に輝く三輪氏の偉業
11 記紀に現われた三輪の巫女
第Ⅱ編 風土論
第一章 風土原論
1 上代文学の環境
―歴史的風土的環境を中心に―
2 記紀神話の風土背景
―国生み神話を対象にして―
第二章 風土の諸相
3 天若日子神話所見の美濃国なる「喪山」考
―その所在と伝承の背景―
4 越(こし)のヌナカワヒメ(沼河比売)探訪記
―古事記神話の風土性―
5 古事記神話の伝承地について
―岐神の鎮座地、(再考)天若日子の美濃の喪山―
6 南九州神話の旅
―天孫ニニギノ命神話の旧跡を訪ねて―
7 「笠紗の御前(みさき)に真来(〇〇)通りて」考
―その訓義と歴史風土的背景―
第Ⅲ編 古事記研究書解題―古事記研究史―
第Ⅳ編 附編
第一章 万葉集論
1 天武朝文学に関する基礎的問題
―特に壬申の乱と万葉集の沈痛調を中心として―
2 万葉集の周辺―神話・伝説からみる―
第二章 旧事紀と古事記
3 旧事紀所見の古事記の逸文について
―主としてその抄出構文の方法について―
4 旧事紀所見の古事記逸文集成(資料)
第三章 〔随想〕日本文芸にみる「ほたる」
著作目録
あとがき
索引
第Ⅰ編 記紀神話論
第一章 神話原論
1 日本神話研究と国文学
2 上代古典の神話・伝説・説話とその文学性
3 日本神話研究の課題―方法論を中心として―
第二章 神話の構造
4 記紀所収の日月眼生伝の一考察
―特に中国の日月眼生伝との対比を中心に―
5 日神・素神の「うけひ」神話の機構
6 大山津見神と大三島
―イザナキ・イザナミ両神の国生み神話考―
7 「塩こをろこをろに」考
―イザナキ・イザナミ両神の聖婚神話考―
第三章 神人の像
8 大国主と大物主
9 悲劇的英雄倭建命
10 古代史(書紀)に輝く三輪氏の偉業
11 記紀に現われた三輪の巫女
第Ⅱ編 風土論
第一章 風土原論
1 上代文学の環境
―歴史的風土的環境を中心に―
2 記紀神話の風土背景
―国生み神話を対象にして―
第二章 風土の諸相
3 天若日子神話所見の美濃国なる「喪山」考
―その所在と伝承の背景―
4 越(こし)のヌナカワヒメ(沼河比売)探訪記
―古事記神話の風土性―
5 古事記神話の伝承地について
―岐神の鎮座地、(再考)天若日子の美濃の喪山―
6 南九州神話の旅
―天孫ニニギノ命神話の旧跡を訪ねて―
7 「笠紗の御前(みさき)に真来(〇〇)通りて」考
―その訓義と歴史風土的背景―
第Ⅲ編 古事記研究書解題―古事記研究史―
第Ⅳ編 附編
第一章 万葉集論
1 天武朝文学に関する基礎的問題
―特に壬申の乱と万葉集の沈痛調を中心として―
2 万葉集の周辺―神話・伝説からみる―
第二章 旧事紀と古事記
3 旧事紀所見の古事記の逸文について
―主としてその抄出構文の方法について―
4 旧事紀所見の古事記逸文集成(資料)
第三章 〔随想〕日本文芸にみる「ほたる」
著作目録
あとがき
索引
