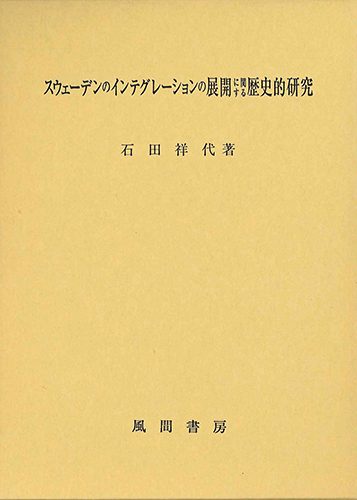
スウェーデンのインテグレーションの展開に関する歴史的研究
定価10,780円(本体 9,800円+税)
スウェーデンのインテグレーションを歴史的視点から論考することにより、その展開過程を明確にし、現代の障害児教育が抱える問題点と今後の方向性へ示唆を与える。
【著者略歴】
石田祥代(いしだ さちよ)
1969年 石川県金沢市に生まれる
1991年から1992年 スウェーデン王立ルンド大学社会福祉学部留学
1993年 岐阜大学教育学部教育学科卒業
1996年から1998年 スウェーデン王立ルンド大学社会福祉学部留学
1999年 筑波大学大学院博士課程心身障害学研究科修了
2000年 筑波大学助手、千葉大学非常勤講師などを経て、
東京成徳大学人文学部福祉心理学科講師
現在に至る
【著者略歴】
石田祥代(いしだ さちよ)
1969年 石川県金沢市に生まれる
1991年から1992年 スウェーデン王立ルンド大学社会福祉学部留学
1993年 岐阜大学教育学部教育学科卒業
1996年から1998年 スウェーデン王立ルンド大学社会福祉学部留学
1999年 筑波大学大学院博士課程心身障害学研究科修了
2000年 筑波大学助手、千葉大学非常勤講師などを経て、
東京成徳大学人文学部福祉心理学科講師
現在に至る
目次を表示
序文
はしがき
序章 研究の課題と方法
1.研究の意義
2.先行研究と課題の設定・研究の方法
3.構成と資料
4.インテグレーションとその関連概念について
5.用語について
文献および注
第一章 インテグレーションの萌芽とその要因(1940~1959)
第一節 障害児への教育の始まり
1.施設内学校の創立
2.盲聾院の設立と盲・聾唖教育の義務教育制
3.初等民衆学校における補助学級の設立
文献および注
第二節 初等民衆学校におけるインテグレーションの萌芽
1.教育組織の原則に関する提案と初等民衆学校への就学
2.初等民衆学校における受け入れ体制の整備
文献および注
第三節 教育制度におけるインテグレーションの萌芽
1.初等民衆学校から統一制学校への移行と盲・聾学校の教育組織の見直し
2.初等民衆学校付設の知的障害特別学校の誕生
文献および注
第二章 インテグレーションの発展と問題の発生(1960~1977)
第一節 集団的・個別的インテグレーションの展開
1.初等民衆学校への就学と学校教育のニーズ
2.基礎学校学習指導要領における特別指導の充実とそのための条件整備
3.特別な配慮を必要とする肢体不自由児のための教育組織
4.集団的・個別的インテグレーションの拡大とその実践
文献および注
第二節 敷地的インテグレーションの展開
1.ノーマライゼーション理念の提起とインテグレーションの具現化
2.敷地的インテグレーションの導入
3.敷地的インテグレーションの試みと問題の発生
文献および注
第三章 インテグレーションの確立とニーズに応じた指導への取り組み(1978~1988)
第一節 特別なニーズのある児童生徒への指導
1.政府の問題解決へ向けての取り組み
2.個々のニーズに相応する教育
3.活動単位指導モデル
文献および注
第二節 専門的な教育とインテグレーション
1.視覚障害特別学校の廃校とリソースセンターとしての存続
2.知的障害特別学校の学校教育法への統合
3.敷地的インテグレーションの実践と残された課題
文献および注
補節 脱インテグレーションの試み
1.手話の獲得へ向けた運動とインテグレーションへの批判
2.手話の第一言語化と教科としての導入
3.併設型聴覚障害特別学校案
文献および注
終章 まとめと今後の課題
文献一覧
補助資料
あとがき
はしがき
序章 研究の課題と方法
1.研究の意義
2.先行研究と課題の設定・研究の方法
3.構成と資料
4.インテグレーションとその関連概念について
5.用語について
文献および注
第一章 インテグレーションの萌芽とその要因(1940~1959)
第一節 障害児への教育の始まり
1.施設内学校の創立
2.盲聾院の設立と盲・聾唖教育の義務教育制
3.初等民衆学校における補助学級の設立
文献および注
第二節 初等民衆学校におけるインテグレーションの萌芽
1.教育組織の原則に関する提案と初等民衆学校への就学
2.初等民衆学校における受け入れ体制の整備
文献および注
第三節 教育制度におけるインテグレーションの萌芽
1.初等民衆学校から統一制学校への移行と盲・聾学校の教育組織の見直し
2.初等民衆学校付設の知的障害特別学校の誕生
文献および注
第二章 インテグレーションの発展と問題の発生(1960~1977)
第一節 集団的・個別的インテグレーションの展開
1.初等民衆学校への就学と学校教育のニーズ
2.基礎学校学習指導要領における特別指導の充実とそのための条件整備
3.特別な配慮を必要とする肢体不自由児のための教育組織
4.集団的・個別的インテグレーションの拡大とその実践
文献および注
第二節 敷地的インテグレーションの展開
1.ノーマライゼーション理念の提起とインテグレーションの具現化
2.敷地的インテグレーションの導入
3.敷地的インテグレーションの試みと問題の発生
文献および注
第三章 インテグレーションの確立とニーズに応じた指導への取り組み(1978~1988)
第一節 特別なニーズのある児童生徒への指導
1.政府の問題解決へ向けての取り組み
2.個々のニーズに相応する教育
3.活動単位指導モデル
文献および注
第二節 専門的な教育とインテグレーション
1.視覚障害特別学校の廃校とリソースセンターとしての存続
2.知的障害特別学校の学校教育法への統合
3.敷地的インテグレーションの実践と残された課題
文献および注
補節 脱インテグレーションの試み
1.手話の獲得へ向けた運動とインテグレーションへの批判
2.手話の第一言語化と教科としての導入
3.併設型聴覚障害特別学校案
文献および注
終章 まとめと今後の課題
文献一覧
補助資料
あとがき
