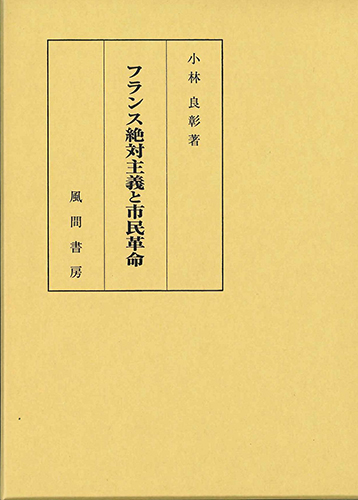
フランス絶対主義と市民革命
定価7,700円(本体 7,000円+税)
フランス絶対主義の領主、貴族、商人、銀行家などの実態を豊富な資料から紹介。これらの正しい解釈により各国市民革命の正確な時期の規定が可能であると論じる。
【著者略歴】
小林良彰(こばやし よしあき)
経済学博士
昭和7年 神戸市に生まれる。
昭和31年 東京大学文学部西洋史学科卒業
昭和43年 大阪大学大学院経済学研究科修士課程修了
同志社大学商学部教授を経て、
平成2年 日本大学経済学部教授
平成14年2月23日 定年退職。以後、日本大学経済学部、日本大学大学院経済学研究科、日本大学通信教育部講師。
【著者略歴】
小林良彰(こばやし よしあき)
経済学博士
昭和7年 神戸市に生まれる。
昭和31年 東京大学文学部西洋史学科卒業
昭和43年 大阪大学大学院経済学研究科修士課程修了
同志社大学商学部教授を経て、
平成2年 日本大学経済学部教授
平成14年2月23日 定年退職。以後、日本大学経済学部、日本大学大学院経済学研究科、日本大学通信教育部講師。
目次を表示
序文
第一章 総説 フランス絶対主義と市民革命
Ⅰ 本書の意義
Ⅱ フランス絶対主義の正確な解釈が必要である
Ⅲ フランス絶対主義の成立過程と日本の封建制度
Ⅳ 宮廷貴族の財政特権
Ⅴ 絶対主義時代の領地の構造を知る必要がある
Ⅵ 特権的商業資本の正確な位置付けが必要である
Ⅶ フランス絶対主義の何が市民革命によって変化したのか
Ⅷ 市民革命の正確な解釈
第二章 フランス絶対主義における高等法院貴族
Ⅰ 問題の所在
(1) 常識的な水準で知られていること(2)用語についての厳密な規定
(3) 絶対主義の均衡説にもとずく解釈(4)貴族とブルジョアジーの勢
力均(5)高等法院は最強の集団であったかどうか
Ⅱ 高等法院貴族の実態
(1)貴族と平民の比重(2)貴族は領主であった(3)高等法院貴族の官
職収入(4)ヴェナリテ(官職売買)の価格(5)歴史的変遷
Ⅲ 絶対主義の時代における高等法院貴族の位置付け
(1)宮廷貴族と高等法院貴族の関係(2)高等法院貴族の役割を過大評
価するべきではない
第三章 フランス絶対主義における法服貴族の役割
Ⅰ 問題提起
(1)絶対主義の支配者は新興貴族であるかどうか(2)宮廷入りした法
服貴族をどう解釈するか
Ⅱ 宮廷入りを許された法服貴族
(1) 財政官僚―財務総監と知事(2)ベルチエ・ド・ソヴィニ
(3)ネッケルの周辺(4)フルーリとラヴェルディ(5)フレッセルとド
ルメソン(6)テレー修道院長兼財務総監(7)財務総監を保護した有力
宮廷貴族
Ⅲ 財務総監コルベールとその一族
(1) コルベールをどう評価するか(2)多数のコルベールと大コルベー
ル(3)コルベール家の始祖(4)財務総監コルベールの系図
(5)マザラン公爵に推薦されて財務総監になった(6)コルベルティズ
ムの意義(7)コルベールの位置付け(8)コルベールの子孫
(9)コルベールの財産を過大評価するべきではない
Ⅳ 理論的要約
(1)理論的誤りの実例(2)正確な理論的解釈(3)フランス絶対主義の
問題点
第四章 フランス絶対主義における大領主
Ⅰ 問題の所在
(1)王権の支柱は大領主=宮廷貴族である(2)大領主を強調する理由
(3)なぜこの証明が必要か(4)宮廷貴族の正確な描写を出発点にする
べきである
Ⅱ 宮廷貴族の実態
(1)宮廷入りの条件(2)宮廷の官職(3)宮廷貴族の飲食費、宴会費 (4)国王一族の小宮延の乱立(5)高級官職を持つ宮廷貴族の実例
(6)主馬頭ランベスク大公(7)宮廷の浪費が貴族によって歓迎された
(8)外交、軍事の権力者(9)第一身分の上層(高級聖職者)
(10)宮廷貴族の領地
Ⅲ 残る問題点
(1)宮廷貴族が大臣に就任した(2)宮廷貴族に保護された者が大臣に
就任した(3)宮廷貴族のその他の特権
Ⅳ 市民革命の比較経済史的解釈
(1)フランス革命への展望(2)主要諸国の絶対主義と市民革命
(3)絶対主義と市民革命を日本史について考える
第五章 フランス革命前夜の財政問題
Ⅰ 問題の所在
(1)フランス革命の原因をどこに求めるか(2)経済的原因を漸進的な
ものとみるか、それとも急激なものとみるか(3)貴族革命説は正しい
かどうか(4)正確な対立の図式―宮廷貴族対ブルジョアジー
(5)財政問題がフランス革命のひきがねになった
Ⅱ 貴族の減免税特権
(1)基本的直接税の減免税特権(2)付加税についての減免税特権
(3)聖職者(第一身分)の減免税特権(4)宮廷貴族の実質的脱税行為
(5)当時は貴族減免税特権を批判することが出来なかった
Ⅲ 宮廷貴族による財政資金の浪費
(1)宮廷と王室の浪費(2)無用高級官職にともなう高額の俸給
(3)赤帳簿と宮廷貴族の財政特権
Ⅳ ルイ一五世の時期
(1)ルイ一五世時代初期の悪政(2)ルイ一五世中期の財政政策
(3)ルイ一五世による財政改革の試みとその失敗(4)テレー財務総監
Ⅴ ルイ一六世時代の初期
(1)財務総監テュルゴーの改革
(2)垂農主義者テュルゴーの成功と敗北
Ⅵ 結論―フランス革命への展望
(1)フランス絶対主義における王権の支柱(2)宮廷貴族(大領主)の
財政特権(3)財政的側面からみたフランス革命論(4)財政的側面から
みた市民革命の一般論
第六章 フランス革命における土地改革
Ⅰ 学説史的意義
(1)フランス革命における土地革命の理論(2)フランスにおける土地
問題の実証的研究(3)土地革命論に基づくフランス革命と明治維新の
比較(4)土地革命の理論は実証的研究と一致するかどうか(5)フラン
スでは領主権廃止ではなく国有財産の売却が問題になってきた
Ⅱ フランス革命直前の土地所有の分布状態
(1)地域的な相違(2)ノール県全体としての要約(3)土地所有の分布
状態
Ⅲ 領主権と土地所有権
(1)領主権の負担の相違―貴族の土地と平民の土地(2)領地の内部に
おける直領地の存在
Ⅳ 領主権廃止の過程
(1) 封建的権利の有償廃止(2)ジロンド派が推進した領主権の無償
廃止(3)国有財産売却の効果
Ⅴ 結論
(1)土地革命論は正しかったかどうか(2)フランス革命の正確な事実
を認めることが重要である
第七章 フランス革命期における銀行家
Ⅰ 問題提起
Ⅱ ルクツー
(1)フランス革命前の上層ブルジョアジー(2)フランス革命初期の革
命的銀行家(3)反革命の側に立った銀行家(4)恐怖政治の迫害を受け
た銀行家(5)ナポレオンと協力した銀行家
Ⅲ ペリエ
(1)グルノーブル市のブルジョアジー(2)クロード・ペリエの成功と
貴族社会への不満(3)革命に全面的な協力を続けたクロード・ペリエ
(4)恐怖政治で死んだ弟のオーギュスタン・ペリエ(5)銀行家、大工
業家として成功したクロード・ペリエ(6)貴族的ブルジョアジーとな
り、フランスの支配者を出した
Ⅳ フール
(1)ユダヤ系銀行家(2)恐怖政治の危機をまぬかれた銀行家
(3)第二帝制の支配者・ボナパルティズムの支柱
Ⅴ 市民革命の理論に対する影響
(1)ルクツー一族とフランス革命の関係(2)ペリエ一族とフランス革
命の関係(3)フール一族とフランス革命の関係(4)フランス革命にお
ける基本的変化(5)市民革命の普遍的法則(6)明治維新とフランス革
命の同一(7)コバン・テイラーの学説の誤り
第八章 市民革命の一般理論
Ⅰ 実証と理論
(1)『国民の歴史』との関係(2)大塚史学への批判者としての評価
(3)「土地革命論」への批判者でもあったと指摘しておきたい
Ⅱ 政治体制と市民革命の関係についての提言
(1)ビスマルク憲法は市民革命の一つの形態である(2)ドイツ帝国憲
法の原型は市民革命としてのプロイセン三月革命で成立した(3)議会
制民主主義、ドイツ帝国憲法のどちらもが市民革命の成果を実現する
(4)市民革命の政治形態として軍事的独裁制もありうる(5)明治維新
を世界の市民革命の中で位置付けることが目的である(6)とくに西洋
人に対して東洋と西洋の中の共通点(市民革命にかんする)を認識させ
ることが課題になる
Ⅲ 市民革命の定義をめぐる問題点
(1)「市民革命」という英語が存在しないことのむずかしさ(2)フラ
ンス人はフランス革命を認めて市民革命を認めない(3)市民革命の語
源はドイツ語に求められる(4)市民革命を町人革命と翻訳するべきで
あった
Ⅳ 市民革命の前提条件
(1)前提条件の多様性(2)多様性の中にひそむ一つの共通点(3)土地
支配の上に組織された権力―市民革命直前の権力組織(4)中央集権の
強弱は商工業の発達に対応する(5)絶対主義は領主階級の権力集中で
ある(6)絶対主義の下では商人、金融業者はまだ被支配者であった
Ⅴ 市民革命の基本法則
(1) 工業、金融業の発達が市民革命の前提になる(2)国家財政の赤字
が市命をひきおこす(3)市民革命で商工業者、金融業者が権力を握る
(4)商工業者、金融業者は旧支配者の一部と提携する(5)商工業者、
金融業者は人民代表の形式も採用する(6)フランス革命は貴族政治家
と人民代表の両面を含む(7)明治維新でもブルジョアジー支配の実質
が武士の背後に隠される(8)市民革命必ずしも議会制民主主義を作ら
ない
Ⅵ 市民革命の年代設定
(1)市民革命の基本法律(2)世界各国の市民革命
あとがき
研究業績一覧
第一章 総説 フランス絶対主義と市民革命
Ⅰ 本書の意義
Ⅱ フランス絶対主義の正確な解釈が必要である
Ⅲ フランス絶対主義の成立過程と日本の封建制度
Ⅳ 宮廷貴族の財政特権
Ⅴ 絶対主義時代の領地の構造を知る必要がある
Ⅵ 特権的商業資本の正確な位置付けが必要である
Ⅶ フランス絶対主義の何が市民革命によって変化したのか
Ⅷ 市民革命の正確な解釈
第二章 フランス絶対主義における高等法院貴族
Ⅰ 問題の所在
(1) 常識的な水準で知られていること(2)用語についての厳密な規定
(3) 絶対主義の均衡説にもとずく解釈(4)貴族とブルジョアジーの勢
力均(5)高等法院は最強の集団であったかどうか
Ⅱ 高等法院貴族の実態
(1)貴族と平民の比重(2)貴族は領主であった(3)高等法院貴族の官
職収入(4)ヴェナリテ(官職売買)の価格(5)歴史的変遷
Ⅲ 絶対主義の時代における高等法院貴族の位置付け
(1)宮廷貴族と高等法院貴族の関係(2)高等法院貴族の役割を過大評
価するべきではない
第三章 フランス絶対主義における法服貴族の役割
Ⅰ 問題提起
(1)絶対主義の支配者は新興貴族であるかどうか(2)宮廷入りした法
服貴族をどう解釈するか
Ⅱ 宮廷入りを許された法服貴族
(1) 財政官僚―財務総監と知事(2)ベルチエ・ド・ソヴィニ
(3)ネッケルの周辺(4)フルーリとラヴェルディ(5)フレッセルとド
ルメソン(6)テレー修道院長兼財務総監(7)財務総監を保護した有力
宮廷貴族
Ⅲ 財務総監コルベールとその一族
(1) コルベールをどう評価するか(2)多数のコルベールと大コルベー
ル(3)コルベール家の始祖(4)財務総監コルベールの系図
(5)マザラン公爵に推薦されて財務総監になった(6)コルベルティズ
ムの意義(7)コルベールの位置付け(8)コルベールの子孫
(9)コルベールの財産を過大評価するべきではない
Ⅳ 理論的要約
(1)理論的誤りの実例(2)正確な理論的解釈(3)フランス絶対主義の
問題点
第四章 フランス絶対主義における大領主
Ⅰ 問題の所在
(1)王権の支柱は大領主=宮廷貴族である(2)大領主を強調する理由
(3)なぜこの証明が必要か(4)宮廷貴族の正確な描写を出発点にする
べきである
Ⅱ 宮廷貴族の実態
(1)宮廷入りの条件(2)宮廷の官職(3)宮廷貴族の飲食費、宴会費 (4)国王一族の小宮延の乱立(5)高級官職を持つ宮廷貴族の実例
(6)主馬頭ランベスク大公(7)宮廷の浪費が貴族によって歓迎された
(8)外交、軍事の権力者(9)第一身分の上層(高級聖職者)
(10)宮廷貴族の領地
Ⅲ 残る問題点
(1)宮廷貴族が大臣に就任した(2)宮廷貴族に保護された者が大臣に
就任した(3)宮廷貴族のその他の特権
Ⅳ 市民革命の比較経済史的解釈
(1)フランス革命への展望(2)主要諸国の絶対主義と市民革命
(3)絶対主義と市民革命を日本史について考える
第五章 フランス革命前夜の財政問題
Ⅰ 問題の所在
(1)フランス革命の原因をどこに求めるか(2)経済的原因を漸進的な
ものとみるか、それとも急激なものとみるか(3)貴族革命説は正しい
かどうか(4)正確な対立の図式―宮廷貴族対ブルジョアジー
(5)財政問題がフランス革命のひきがねになった
Ⅱ 貴族の減免税特権
(1)基本的直接税の減免税特権(2)付加税についての減免税特権
(3)聖職者(第一身分)の減免税特権(4)宮廷貴族の実質的脱税行為
(5)当時は貴族減免税特権を批判することが出来なかった
Ⅲ 宮廷貴族による財政資金の浪費
(1)宮廷と王室の浪費(2)無用高級官職にともなう高額の俸給
(3)赤帳簿と宮廷貴族の財政特権
Ⅳ ルイ一五世の時期
(1)ルイ一五世時代初期の悪政(2)ルイ一五世中期の財政政策
(3)ルイ一五世による財政改革の試みとその失敗(4)テレー財務総監
Ⅴ ルイ一六世時代の初期
(1)財務総監テュルゴーの改革
(2)垂農主義者テュルゴーの成功と敗北
Ⅵ 結論―フランス革命への展望
(1)フランス絶対主義における王権の支柱(2)宮廷貴族(大領主)の
財政特権(3)財政的側面からみたフランス革命論(4)財政的側面から
みた市民革命の一般論
第六章 フランス革命における土地改革
Ⅰ 学説史的意義
(1)フランス革命における土地革命の理論(2)フランスにおける土地
問題の実証的研究(3)土地革命論に基づくフランス革命と明治維新の
比較(4)土地革命の理論は実証的研究と一致するかどうか(5)フラン
スでは領主権廃止ではなく国有財産の売却が問題になってきた
Ⅱ フランス革命直前の土地所有の分布状態
(1)地域的な相違(2)ノール県全体としての要約(3)土地所有の分布
状態
Ⅲ 領主権と土地所有権
(1)領主権の負担の相違―貴族の土地と平民の土地(2)領地の内部に
おける直領地の存在
Ⅳ 領主権廃止の過程
(1) 封建的権利の有償廃止(2)ジロンド派が推進した領主権の無償
廃止(3)国有財産売却の効果
Ⅴ 結論
(1)土地革命論は正しかったかどうか(2)フランス革命の正確な事実
を認めることが重要である
第七章 フランス革命期における銀行家
Ⅰ 問題提起
Ⅱ ルクツー
(1)フランス革命前の上層ブルジョアジー(2)フランス革命初期の革
命的銀行家(3)反革命の側に立った銀行家(4)恐怖政治の迫害を受け
た銀行家(5)ナポレオンと協力した銀行家
Ⅲ ペリエ
(1)グルノーブル市のブルジョアジー(2)クロード・ペリエの成功と
貴族社会への不満(3)革命に全面的な協力を続けたクロード・ペリエ
(4)恐怖政治で死んだ弟のオーギュスタン・ペリエ(5)銀行家、大工
業家として成功したクロード・ペリエ(6)貴族的ブルジョアジーとな
り、フランスの支配者を出した
Ⅳ フール
(1)ユダヤ系銀行家(2)恐怖政治の危機をまぬかれた銀行家
(3)第二帝制の支配者・ボナパルティズムの支柱
Ⅴ 市民革命の理論に対する影響
(1)ルクツー一族とフランス革命の関係(2)ペリエ一族とフランス革
命の関係(3)フール一族とフランス革命の関係(4)フランス革命にお
ける基本的変化(5)市民革命の普遍的法則(6)明治維新とフランス革
命の同一(7)コバン・テイラーの学説の誤り
第八章 市民革命の一般理論
Ⅰ 実証と理論
(1)『国民の歴史』との関係(2)大塚史学への批判者としての評価
(3)「土地革命論」への批判者でもあったと指摘しておきたい
Ⅱ 政治体制と市民革命の関係についての提言
(1)ビスマルク憲法は市民革命の一つの形態である(2)ドイツ帝国憲
法の原型は市民革命としてのプロイセン三月革命で成立した(3)議会
制民主主義、ドイツ帝国憲法のどちらもが市民革命の成果を実現する
(4)市民革命の政治形態として軍事的独裁制もありうる(5)明治維新
を世界の市民革命の中で位置付けることが目的である(6)とくに西洋
人に対して東洋と西洋の中の共通点(市民革命にかんする)を認識させ
ることが課題になる
Ⅲ 市民革命の定義をめぐる問題点
(1)「市民革命」という英語が存在しないことのむずかしさ(2)フラ
ンス人はフランス革命を認めて市民革命を認めない(3)市民革命の語
源はドイツ語に求められる(4)市民革命を町人革命と翻訳するべきで
あった
Ⅳ 市民革命の前提条件
(1)前提条件の多様性(2)多様性の中にひそむ一つの共通点(3)土地
支配の上に組織された権力―市民革命直前の権力組織(4)中央集権の
強弱は商工業の発達に対応する(5)絶対主義は領主階級の権力集中で
ある(6)絶対主義の下では商人、金融業者はまだ被支配者であった
Ⅴ 市民革命の基本法則
(1) 工業、金融業の発達が市民革命の前提になる(2)国家財政の赤字
が市命をひきおこす(3)市民革命で商工業者、金融業者が権力を握る
(4)商工業者、金融業者は旧支配者の一部と提携する(5)商工業者、
金融業者は人民代表の形式も採用する(6)フランス革命は貴族政治家
と人民代表の両面を含む(7)明治維新でもブルジョアジー支配の実質
が武士の背後に隠される(8)市民革命必ずしも議会制民主主義を作ら
ない
Ⅵ 市民革命の年代設定
(1)市民革命の基本法律(2)世界各国の市民革命
あとがき
研究業績一覧
