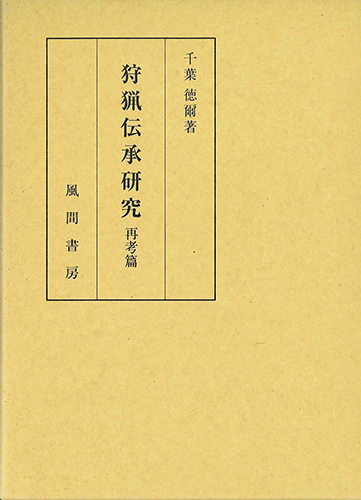
狩猟伝承研究 再考篇
定価16,500円(本体 15,000円+税)
著者四半世紀の山村採訪を軸に、信ずべき先学の報告記事を渉猟しつつ考察を加え、信仰や芸能の発生をも探り、猟師の古老たちからの聞書や狩の巻物の内容によって民族心意の深奥に迫る。【全6冊】
第20回秩父宮記念学術賞受賞
【著者略歴】
千葉徳爾(ちば とくじ)
1916年千葉県に生れる。同年東京に移り、1939年東京高等師範学校文科4部卒業。1950年東京高師助教授、以後、東京教育大、信州大、愛知大、筑波大、明治大を経て、1986年定年退職。理学博士(東北大)、文学博士(東京教育大)。
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示
はじめに
序論 その一 日本の人獣交渉史
その二 日本人の野生動物観
本 論
第一章 近世末期大和地方の狩猟慣行史料
一 大和の狩猟史料とその特性
二 資料の性質と価値
三 各地域における注意すべき慣行
四 若干の考察
五 狩猟文書の系統の再検討
第二章 各地狩猟伝承の残存と消滅
一 屋久島調査報告
二 只見川流域の狩猟伝承
三 青森県西津軽郡鰺ヶ沢の狩猟碑
四 中国山地の狩猟の状況
第三章 山中異界観の成立
一 異界とは何か
二 異界を領するもの
三 日本人にとっての異界の成立
四 平家谷の成立
五 一本足の山の神
六 海外知識の導入
七 日本人の山中異界への対応
八 山詞の分析と考察
第四章 山中異界と山言葉その他
一 山言葉の成立
二 山中秘儀の問題
三 日本人の野獣観と西欧人
四 野獣観あるいは異界観の功罪
第五章 山の神の一考察
一 はじめに
二 山中異界と山の神
三 ナウマン女史の著作の概要―その一―
四 ナウマン女史の著作の概要―その二―
五 山中異界の支配者と野獣
六 アジア・ヨーロッパの野獣観
第六章 山の神縁起文書
一 いわゆる狩猟伝承文書とは何か
二 狩猟文書の系統化
三 巻物の時代的新旧
四 下北半島の狩の巻物を手がかりに
五 筆をおくに当って
終りに
一 今後の課題
付論その一 研究対象(日本民族)の範囲
日本民族の形成と完了―その時代と学的意義―
一 この論考の趣旨
二 先学の認識
三 日本民族の統合過程
四 足利(戦国期)時代移住の家系伝承―上・信地方の事例―
五 足利時代が人心に与えたもの
六 結び
付論その二 調査技法の問題
「聞き取り」という調査法について
一 はじめに
二 ききとりという作業
三 民俗資料の現地調査
四 ききとりは対話法ではない
五 聞き手の能力
六 対話による「同情」の世界の構築
索 引
序論 その一 日本の人獣交渉史
その二 日本人の野生動物観
本 論
第一章 近世末期大和地方の狩猟慣行史料
一 大和の狩猟史料とその特性
二 資料の性質と価値
三 各地域における注意すべき慣行
四 若干の考察
五 狩猟文書の系統の再検討
第二章 各地狩猟伝承の残存と消滅
一 屋久島調査報告
二 只見川流域の狩猟伝承
三 青森県西津軽郡鰺ヶ沢の狩猟碑
四 中国山地の狩猟の状況
第三章 山中異界観の成立
一 異界とは何か
二 異界を領するもの
三 日本人にとっての異界の成立
四 平家谷の成立
五 一本足の山の神
六 海外知識の導入
七 日本人の山中異界への対応
八 山詞の分析と考察
第四章 山中異界と山言葉その他
一 山言葉の成立
二 山中秘儀の問題
三 日本人の野獣観と西欧人
四 野獣観あるいは異界観の功罪
第五章 山の神の一考察
一 はじめに
二 山中異界と山の神
三 ナウマン女史の著作の概要―その一―
四 ナウマン女史の著作の概要―その二―
五 山中異界の支配者と野獣
六 アジア・ヨーロッパの野獣観
第六章 山の神縁起文書
一 いわゆる狩猟伝承文書とは何か
二 狩猟文書の系統化
三 巻物の時代的新旧
四 下北半島の狩の巻物を手がかりに
五 筆をおくに当って
終りに
一 今後の課題
付論その一 研究対象(日本民族)の範囲
日本民族の形成と完了―その時代と学的意義―
一 この論考の趣旨
二 先学の認識
三 日本民族の統合過程
四 足利(戦国期)時代移住の家系伝承―上・信地方の事例―
五 足利時代が人心に与えたもの
六 結び
付論その二 調査技法の問題
「聞き取り」という調査法について
一 はじめに
二 ききとりという作業
三 民俗資料の現地調査
四 ききとりは対話法ではない
五 聞き手の能力
六 対話による「同情」の世界の構築
索 引
