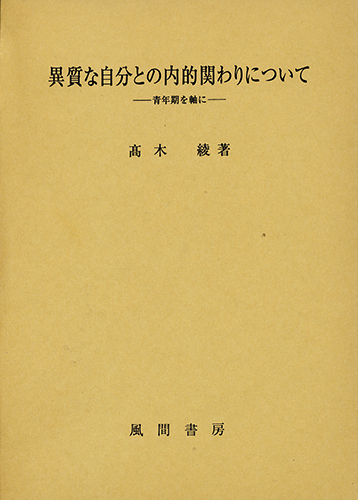
異質な自分との内的関わりについて
青年期を軸に
定価9,350円(本体 8,500円+税)
自分の中にありながら自分のものとは思い難い側面を「異質な自分」と名付け、特に青年期の人々がそれとどのように関わっているのかを動的に描き出すことを試みた。
【著者略歴】
髙木 綾(たかぎ あや)
静岡県出身
2001年 京都大学教育学部教育心理学科卒業
2003年 京都大学大学院教育学研究科修士課程修了
2009年 京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了
博士(教育学)
現在 京都文教大学臨床心理学部専任講師
臨床心理士
専攻 臨床心理学
【著者略歴】
髙木 綾(たかぎ あや)
静岡県出身
2001年 京都大学教育学部教育心理学科卒業
2003年 京都大学大学院教育学研究科修士課程修了
2009年 京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了
博士(教育学)
現在 京都文教大学臨床心理学部専任講師
臨床心理士
専攻 臨床心理学
目次を表示
まえがき
序 章
第1章 「異質な自分」との関わりをめぐって―心理臨床的な視点を踏まえて―
Ⅰ 自分であると思えるものと思えないもの
Ⅱ 自分との「関わり」という観点から
Ⅲ 青年期との関連
1.青年期心性と「異質な自分」
2.変化という観点から
Ⅳ 「異質な自分」の意義
1.中間的であることの意義
2.主体的に自己に関わること
Ⅴ 多面的な自己を捉える手法について
1.ダイナミックな主観的イメージを重視する観点から
2.主体のプロセスを重視する観点から
3.本研究で用いる方法論について
Ⅵ まとめ
第2章 青年期における異なる自己像とその関係性イメージについて
―いわゆる「本当の自分」と「借り物の自分」の観点から―
Ⅰ はじめに
Ⅱ 問題
Ⅲ 目的
Ⅳ 方法
Ⅴ 結果
1.個々の課題の結果
2.個々の課題間の関連の分析
Ⅵ 考察
1.異なる自己像それぞれのイメージ
2.描画に表れた二つの自分の関係性イメージ(主に他の尺度との関連から)
3.現在から理想への関係性イメージの変化の方向性
4.「借り物の自分」の位置付けに表れた青年期の自己像
5.まとめ
第3章 青年期における異なる自己像とその関係性イメージについて
―「本当の自分」と「本当の自分ではないような自分」の観点から―
Ⅰ 問題
Ⅱ 目的
Ⅲ 方法
1.「本当の自分ではないような自分」と「本当の自分」についてのイメージ
2.現在の関係性イメージの表現(言語、箱庭、円を用いた描画の3段階)
3.理想的な関係性イメージの表現(言語、箱庭、円を用いた描画の3段階)
Ⅳ 結果
1.「本当の自分ではないような自分」と「本当の自分」についてのイメージ
2.現在の関係性イメージの表現
3.理想的な関係性イメージの表現
4.現在のイメージから理想的なイメージへの変化について
Ⅴ 考察
1.「本当の自分」と「本当の自分ではないような自分」のイメージ
2.円を用いた描画法のカテゴリーが表しているもの(描画表現と言語表現の関連から)
3.円を用いた描画法の分類ごとの箱庭表現の特徴について
4.本章で明らかになったこと
Ⅵ まとめ
第4章 個人の中にあるものとしての「異質な自分」―箱庭、描画、言語表現の横断的分析から―
Ⅰ はじめに
Ⅱ 調査において表現された内容とその考察
1.Aさん(カテゴリー①)
2.Bさん(カテゴリー②)
3.Cさん(カテゴリー②または①)
4.Dさん(カテゴリー②)
5.Eさん(カテゴリー②)
6.Fさん(カテゴリー③)
Ⅲ 6事例を通しての考察
1.カテゴリー間の語り方の比較
2.「本当の自分」と「本当の自分ではないような自分」について問うことが引き起こす反応
3.箱庭表現における中心の存在
4.「本当の自分」と「本当の自分ではないような自分」について問うことの意味
Ⅳ まとめ
第5章 総合考察
Ⅰ はじめに―第1章から第4章の諸研究のまとめ―
Ⅱ 「異質な自分」のイメージ
Ⅲ 対のイメージから見えてくるもの
1.「本当の自分」について
2.「異質な自分」との関わり―異なる自己像の関係性をどう生きているかという視点から―
Ⅳ 「異質な自分」との関わりから生まれる力動性
1.時間軸の役割
2.「異質な自分」について語るとはどういうことか
3.内なる他者としての「異質な自分」とその両価性
4.「異質な自分」を自分の中に位置付ける視点
Ⅴ 結び―今後に向けて―
文献リスト
付表
添付資料
初出
あとがき
序 章
第1章 「異質な自分」との関わりをめぐって―心理臨床的な視点を踏まえて―
Ⅰ 自分であると思えるものと思えないもの
Ⅱ 自分との「関わり」という観点から
Ⅲ 青年期との関連
1.青年期心性と「異質な自分」
2.変化という観点から
Ⅳ 「異質な自分」の意義
1.中間的であることの意義
2.主体的に自己に関わること
Ⅴ 多面的な自己を捉える手法について
1.ダイナミックな主観的イメージを重視する観点から
2.主体のプロセスを重視する観点から
3.本研究で用いる方法論について
Ⅵ まとめ
第2章 青年期における異なる自己像とその関係性イメージについて
―いわゆる「本当の自分」と「借り物の自分」の観点から―
Ⅰ はじめに
Ⅱ 問題
Ⅲ 目的
Ⅳ 方法
Ⅴ 結果
1.個々の課題の結果
2.個々の課題間の関連の分析
Ⅵ 考察
1.異なる自己像それぞれのイメージ
2.描画に表れた二つの自分の関係性イメージ(主に他の尺度との関連から)
3.現在から理想への関係性イメージの変化の方向性
4.「借り物の自分」の位置付けに表れた青年期の自己像
5.まとめ
第3章 青年期における異なる自己像とその関係性イメージについて
―「本当の自分」と「本当の自分ではないような自分」の観点から―
Ⅰ 問題
Ⅱ 目的
Ⅲ 方法
1.「本当の自分ではないような自分」と「本当の自分」についてのイメージ
2.現在の関係性イメージの表現(言語、箱庭、円を用いた描画の3段階)
3.理想的な関係性イメージの表現(言語、箱庭、円を用いた描画の3段階)
Ⅳ 結果
1.「本当の自分ではないような自分」と「本当の自分」についてのイメージ
2.現在の関係性イメージの表現
3.理想的な関係性イメージの表現
4.現在のイメージから理想的なイメージへの変化について
Ⅴ 考察
1.「本当の自分」と「本当の自分ではないような自分」のイメージ
2.円を用いた描画法のカテゴリーが表しているもの(描画表現と言語表現の関連から)
3.円を用いた描画法の分類ごとの箱庭表現の特徴について
4.本章で明らかになったこと
Ⅵ まとめ
第4章 個人の中にあるものとしての「異質な自分」―箱庭、描画、言語表現の横断的分析から―
Ⅰ はじめに
Ⅱ 調査において表現された内容とその考察
1.Aさん(カテゴリー①)
2.Bさん(カテゴリー②)
3.Cさん(カテゴリー②または①)
4.Dさん(カテゴリー②)
5.Eさん(カテゴリー②)
6.Fさん(カテゴリー③)
Ⅲ 6事例を通しての考察
1.カテゴリー間の語り方の比較
2.「本当の自分」と「本当の自分ではないような自分」について問うことが引き起こす反応
3.箱庭表現における中心の存在
4.「本当の自分」と「本当の自分ではないような自分」について問うことの意味
Ⅳ まとめ
第5章 総合考察
Ⅰ はじめに―第1章から第4章の諸研究のまとめ―
Ⅱ 「異質な自分」のイメージ
Ⅲ 対のイメージから見えてくるもの
1.「本当の自分」について
2.「異質な自分」との関わり―異なる自己像の関係性をどう生きているかという視点から―
Ⅳ 「異質な自分」との関わりから生まれる力動性
1.時間軸の役割
2.「異質な自分」について語るとはどういうことか
3.内なる他者としての「異質な自分」とその両価性
4.「異質な自分」を自分の中に位置付ける視点
Ⅴ 結び―今後に向けて―
文献リスト
付表
添付資料
初出
あとがき
