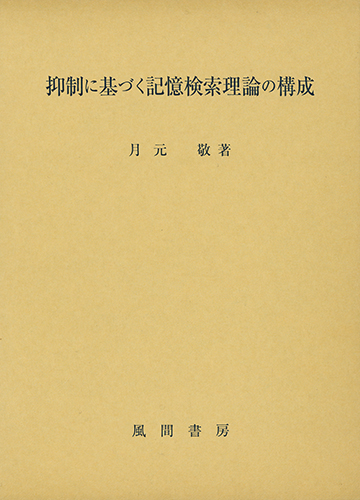
抑制に基づく記憶検索理論の構成
定価8,800円(本体 8,000円+税)
抑制プロセスを含む基礎的な記憶検索メカニズムを、計算理論やシミュレーション・モデルといった認知科学的なアプローチによって明らかにすることを試みた。
【著者略歴】
月元敬(つきもと たかし)
1976年 兵庫県に生まれる
1999年 関西大学総合情報学部卒業
2001年 名古屋大学大学院人間情報学研究科社会情報学専攻博士前期課程修了
2005年 名古屋大学大学院環境学研究科社会環境学専攻博士後期課程修了
博士(心理学)(名古屋大学)
名古屋大学大学院研究生を経て
現在 東京大学大学院人文社会系研究科助教
【著者略歴】
月元敬(つきもと たかし)
1976年 兵庫県に生まれる
1999年 関西大学総合情報学部卒業
2001年 名古屋大学大学院人間情報学研究科社会情報学専攻博士前期課程修了
2005年 名古屋大学大学院環境学研究科社会環境学専攻博士後期課程修了
博士(心理学)(名古屋大学)
名古屋大学大学院研究生を経て
現在 東京大学大学院人文社会系研究科助教
目次を表示
はじめに
第1章 研究対象と目的
1.1 理論と実験の均衡の重要性
1.2 記憶課題の前提としての検索メカニズム
1.3 感知不能な仕組み:シミュレーション・モデルの要請
1.4 本論文の構成
第2章 記憶検索の理論構成の手がかりとなる現象及びその説明概念に関する検討
2.1 理論化のためのデータ選択の基準
2.2 検索経験
2.3 検索誘導性忘却
2.3.1 検索経験パラダイム
2.3.2 未知の情報における検索誘導性忘却
2.4 現行のモデル:抑止説とブロッキング説
2.4.1 抑止説
2.4.2 ブロッキング説
2.5 検索誘導性忘却の特性
2.5.1 連合強度の影響
2.5.2 手がかり独立
2.5.3 検索固有性
2.6 現行の抑止説の理論的問題
2.6.1 正の効果の取り扱い
2.6.2 手がかりに対する活性化
2.6.3 何が抑止されるのか?
2.6.4 抑止の主体:抑止概念は必要か?
第3章 検索誘導性忘却における抑止の対象
3.1 実験1:潜在記憶パラダイムによる抑止の所在に関する検討
3.1.1 方法
3.1.2 結果
3.1.3 考察
第4章 記憶の計算理論を求めて
4.1 記憶の目的
4.2 活性化=情報補完への貢献
4.3 抑止の主体は何か?
4.4 表象の相互作用とアクセスの関係
4.5 アクセスに替わる計算概念
4.5.1 生成:表象による情報補完
4.5.2 生成概念と表象概念について
4.5.3 グローバル・マッチング
4.6 まとめ
第5章 EMILE:記憶検索のシミュレーション・モデル
5.1 MINERVA 2の概略
5.1.1 表現に関する仮定
5.1.2 アルゴリズムに関する仮定
5.2 EMILEモデル
5.2.1 EMILEにおける表現
5.2.2 EMILEのアルゴリズム
5.3 シミュレーションの一般的設定
5.4 シミュレーション1:典型的な検索誘導性忘却
5.4.1 方法
5.4.2 結果と考察
5.5 シミュレーション2:反復呈示によるRp+の強化
5.5.1 方法
5.5.2 結果と考察
5.6 シミュレーション3:カテゴリ情報の検索経験
5.6.1 方法
5.6.2 結果と考察
5.7 まとめ
第6章 検索誘導性忘却における学習エピソード情報の役割
6.1 Nrpに関する分析
6.2 シミュレーション4:検索誘導性忘却における学習エピソード情報の影響
6.2.1 方法
6.2.2 結果と考察
6.3 実験2:被験者間ベースラインによるNrpへの抑制効果に関する検討
6.3.1 方法
6.3.2 結果
6.3.3 考察
6.4 被験者間要因に基づくパフォーマンス比較の妥当性
6.5 変形版検索経験パラダイムの提案
6.6 実験3:カテゴリ競合とエピソード競合が共に関与する条件についての検討
6.6.1 方法
6.6.2 結果と考察
6.7 実験4:カテゴリ競合のみが関与する条件についての検討
6.7.1 方法
6.7.2 結果と考察
6.8 実験5:エピソード競合のみが関与する条件についての検討
6.8.1 方法
6.8.2 結果と考察
6.9 シミュレーション5:カテゴリなしの刺激における検索誘導性忘却の検討
6.9.1 方法
6.9.2 結果と考察
6.10 まとめ
第7章 EMILEの適用拡大:検索誘導性忘却以外の記憶現象のシミュレーション
7.1 出力干渉
7.1.1 シミュレーション6:1対1関係のS-R連合における出力干渉に関する検討
7.1.2 シミュレーション7:出力干渉に関する検討
7.2 記憶の文脈依存性
7.2.1 シミュレーション8:文脈依存記憶の検討
7.3 逆向干渉
7.3.1 シミュレーション9:“基本的手続き”による逆向干渉の検討
7.4 老齢者の再生記憶
7.4.1 シミュレーション10:手がかり再生における加齢効果
第8章 本研究の総括:記憶検索の理論的インプリケーション
8.1 本研究で得られた知見
8.1.1 モデル構成のための理論的検討
8.1.2 モデルの心理学的実在性の検証
8.2 心理学における理論的アプローチの重要性
8.3 心理学における記憶観の“転回”可能性についての試論
8.3.1 アクセス説の学問的経緯
8.3.2 ブレイン・メタファの導入
8.3.3 二つのメタファの整合不能性
8.3.4 認知心理学に対する生成説の貢献
引用文献
付録
第1章 研究対象と目的
1.1 理論と実験の均衡の重要性
1.2 記憶課題の前提としての検索メカニズム
1.3 感知不能な仕組み:シミュレーション・モデルの要請
1.4 本論文の構成
第2章 記憶検索の理論構成の手がかりとなる現象及びその説明概念に関する検討
2.1 理論化のためのデータ選択の基準
2.2 検索経験
2.3 検索誘導性忘却
2.3.1 検索経験パラダイム
2.3.2 未知の情報における検索誘導性忘却
2.4 現行のモデル:抑止説とブロッキング説
2.4.1 抑止説
2.4.2 ブロッキング説
2.5 検索誘導性忘却の特性
2.5.1 連合強度の影響
2.5.2 手がかり独立
2.5.3 検索固有性
2.6 現行の抑止説の理論的問題
2.6.1 正の効果の取り扱い
2.6.2 手がかりに対する活性化
2.6.3 何が抑止されるのか?
2.6.4 抑止の主体:抑止概念は必要か?
第3章 検索誘導性忘却における抑止の対象
3.1 実験1:潜在記憶パラダイムによる抑止の所在に関する検討
3.1.1 方法
3.1.2 結果
3.1.3 考察
第4章 記憶の計算理論を求めて
4.1 記憶の目的
4.2 活性化=情報補完への貢献
4.3 抑止の主体は何か?
4.4 表象の相互作用とアクセスの関係
4.5 アクセスに替わる計算概念
4.5.1 生成:表象による情報補完
4.5.2 生成概念と表象概念について
4.5.3 グローバル・マッチング
4.6 まとめ
第5章 EMILE:記憶検索のシミュレーション・モデル
5.1 MINERVA 2の概略
5.1.1 表現に関する仮定
5.1.2 アルゴリズムに関する仮定
5.2 EMILEモデル
5.2.1 EMILEにおける表現
5.2.2 EMILEのアルゴリズム
5.3 シミュレーションの一般的設定
5.4 シミュレーション1:典型的な検索誘導性忘却
5.4.1 方法
5.4.2 結果と考察
5.5 シミュレーション2:反復呈示によるRp+の強化
5.5.1 方法
5.5.2 結果と考察
5.6 シミュレーション3:カテゴリ情報の検索経験
5.6.1 方法
5.6.2 結果と考察
5.7 まとめ
第6章 検索誘導性忘却における学習エピソード情報の役割
6.1 Nrpに関する分析
6.2 シミュレーション4:検索誘導性忘却における学習エピソード情報の影響
6.2.1 方法
6.2.2 結果と考察
6.3 実験2:被験者間ベースラインによるNrpへの抑制効果に関する検討
6.3.1 方法
6.3.2 結果
6.3.3 考察
6.4 被験者間要因に基づくパフォーマンス比較の妥当性
6.5 変形版検索経験パラダイムの提案
6.6 実験3:カテゴリ競合とエピソード競合が共に関与する条件についての検討
6.6.1 方法
6.6.2 結果と考察
6.7 実験4:カテゴリ競合のみが関与する条件についての検討
6.7.1 方法
6.7.2 結果と考察
6.8 実験5:エピソード競合のみが関与する条件についての検討
6.8.1 方法
6.8.2 結果と考察
6.9 シミュレーション5:カテゴリなしの刺激における検索誘導性忘却の検討
6.9.1 方法
6.9.2 結果と考察
6.10 まとめ
第7章 EMILEの適用拡大:検索誘導性忘却以外の記憶現象のシミュレーション
7.1 出力干渉
7.1.1 シミュレーション6:1対1関係のS-R連合における出力干渉に関する検討
7.1.2 シミュレーション7:出力干渉に関する検討
7.2 記憶の文脈依存性
7.2.1 シミュレーション8:文脈依存記憶の検討
7.3 逆向干渉
7.3.1 シミュレーション9:“基本的手続き”による逆向干渉の検討
7.4 老齢者の再生記憶
7.4.1 シミュレーション10:手がかり再生における加齢効果
第8章 本研究の総括:記憶検索の理論的インプリケーション
8.1 本研究で得られた知見
8.1.1 モデル構成のための理論的検討
8.1.2 モデルの心理学的実在性の検証
8.2 心理学における理論的アプローチの重要性
8.3 心理学における記憶観の“転回”可能性についての試論
8.3.1 アクセス説の学問的経緯
8.3.2 ブレイン・メタファの導入
8.3.3 二つのメタファの整合不能性
8.3.4 認知心理学に対する生成説の貢献
引用文献
付録
