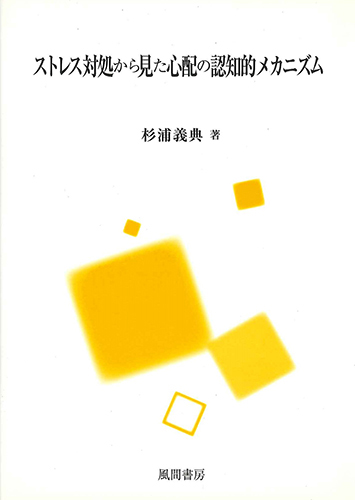
ストレス対処から見た心配の認知的メカニズム
定価6,600円(本体 6,000円+税)
日常生活上の問題を解決する努力が、制御困難な心配に変容するプロセスを明らかにした研究書。ストレス対処研究と異常心理学のインターフェースを提供する。
【著者略歴】
杉浦義典(すぎうら よしのり)
1973年 愛知県に生まれる
1996年 東京大学教育学部教育心理学科卒業
1998年 東京大学大学院教育学研究科修士課程修了
2000年 日本学術振興会特別研究員(DC2)
2001年 日本学術振興会特別研究員(PD)
2002年 東京大学大学院教育学研究科博士課程修了(博士(教育学))
現在 信州大学人文学部助教授
※略歴は刊行当時のものです※
専攻
異常心理学・臨床心理学
著書
『Problem-Solving Model of Worrying』(風間書房 2005)など
目次を表示
緒言
はじめに
第1部 研究の展望
第1章 先行研究の概観
1.1 心配とは何か
1.2 心配の現象的性質
1.3 不安認知のメカニズム:自動的処理と制御的処理
1.4 心配の背後の自動的処理に着目した研究
1.5 心配の能動性に着目した研究
1.6 問題解決という目的に着目する重要性
第2章 研究の目的と方法論
2.1 研究の概念的枠組み
2.2 研究の方法論
2.3 研究の構成
第2部 問題解決の動機と方略に着日した心配の実証研究
第3章 研究1 問題解決の動機と心配の制御困難性の関連
3.1 問題意識
3.2 先行研究の知見:心配の問題解決志向性
3.3 目的
3.4 方法
3.5 結果
3.6 考察
3.7 要約
第4章 研究2 問題解決方略と思考の制御困難性の関連
4.1 問題意識
4.2 先行研究の知見:対処方略と思考の制御困難性
4.3 目的
4.4 方法
4.5 結果と考察
4.6 総合的考察
4.7 要約
第5章 研究3 問題解決方略と思考の制御困難性の関連を媒介する要因
5.1 問題意識
5.2 先行研究の知見:思考を持続させる認知
5.3 目的
5.4 方法
5.5 結果と考察
5.6 総合的考察
5.7 要約
第3部 結 論
第6章 研究の結論とその示唆
6.1 心配のメカニズム
6.2 動機づけ理論の枠組みによる心配のメカニズムの再定式化
6.3 研究の位置付け:ストレス対処との関連で
6.4 今後の研究への示唆
6.5 結語
引用文献
あとがき
はじめに
第1部 研究の展望
第1章 先行研究の概観
1.1 心配とは何か
1.2 心配の現象的性質
1.3 不安認知のメカニズム:自動的処理と制御的処理
1.4 心配の背後の自動的処理に着目した研究
1.5 心配の能動性に着目した研究
1.6 問題解決という目的に着目する重要性
第2章 研究の目的と方法論
2.1 研究の概念的枠組み
2.2 研究の方法論
2.3 研究の構成
第2部 問題解決の動機と方略に着日した心配の実証研究
第3章 研究1 問題解決の動機と心配の制御困難性の関連
3.1 問題意識
3.2 先行研究の知見:心配の問題解決志向性
3.3 目的
3.4 方法
3.5 結果
3.6 考察
3.7 要約
第4章 研究2 問題解決方略と思考の制御困難性の関連
4.1 問題意識
4.2 先行研究の知見:対処方略と思考の制御困難性
4.3 目的
4.4 方法
4.5 結果と考察
4.6 総合的考察
4.7 要約
第5章 研究3 問題解決方略と思考の制御困難性の関連を媒介する要因
5.1 問題意識
5.2 先行研究の知見:思考を持続させる認知
5.3 目的
5.4 方法
5.5 結果と考察
5.6 総合的考察
5.7 要約
第3部 結 論
第6章 研究の結論とその示唆
6.1 心配のメカニズム
6.2 動機づけ理論の枠組みによる心配のメカニズムの再定式化
6.3 研究の位置付け:ストレス対処との関連で
6.4 今後の研究への示唆
6.5 結語
引用文献
あとがき
