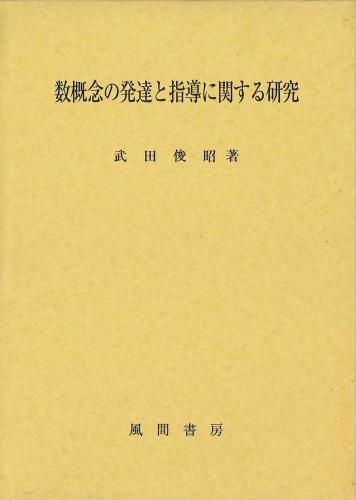
数概念の発達と指導に関する研究
定価8,580円(本体 7,800円+税)
数概念の発達と指導に関する著者の30年にわたる実験研究を集大成したものである。教育要領の「数量の扱い」の内容を実証的に裏づけている点で価値がある。
【著者略歴】
武田俊昭(たけだ としあき)
1968年 関西学院大学文学部教育学科(教育心理学専修)卒業(文学士)
1970年 関西学院大学大学院文学研究科教育学専攻修士課程修了(文学修士)
1970年 米国University of Hawaii(発達心理学)短期留学
1973年 関西学院大学大学院文学研究科教育学専攻博士課程単位取得満期退学
1983~1984年 米国University of Illinois(幼児教育学)客員研究員
1989~1991年 広島大学大学院教育学研究科幼児学専攻(幼児心理学)研究生
1997年 博士(教育学)
現在、聖和大学教育学部教授・副学長・同附属聖和幼稚園長、大阪教育大学、関西学院大学非常勤講師、学校法人芦屋みどり幼稚園理事長
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示
まえがき
第1章 序論
Ⅰ 論文の構成
Ⅱ 研究の要旨
第2章 子どもの数概念
Ⅰ 子どもと数の関わり
1.集合数の理解
2.順序数の理解
3.数の理解の発達
Ⅱ 子どもと量の関わり
1.保存の理解
2.粒子観の理解
3.量の理解の発達
Ⅲ 遊びの中での数量の指導
1.遊びと数量的経験
2.数量の指導上の留意点
3.数量の指導
第3章 ピアジェの保存概念に関する先行研究
Ⅰ 問題
Ⅱ 研究の分摂
1.年代による分頼
2.刺激材料を変数とした分類
3.被験児の年齢を変数とした分頬
4.被験児の特性を変数とした分類
5.保存の訓練をとりあつかった研究
6.異文化における比較研究
Ⅲ 文献目録
Ⅳ 要約
第4章 幼年期における量概念の発達
Ⅰ 問題
Ⅱ 方法
1.被験者
2.実験手続き
Ⅲ 結果
1.年齢
2.量のタイプ
3.道具のタイプ
4.年齢と量のタイプの交互作用
5.量のタイプと道具のタイプの交互作用
6.道具間の相関
7.知能およびことばの成熟と量比較との相関
Ⅳ 考察
V 要約
第5章 児童・青年期における量概念の発達
Ⅰ 問題
Ⅱ 研究 Ⅰ ―小学生を対象にして―
Ⅲ 研究 Ⅱ ―中・高・大学生を対象にして―
Ⅳ 要約
第6章 数・量概念の研究における方法論的問題
―言語反応について―
Ⅰ 問題
Ⅱ 方法
1.被験児
2.用 具
3.手続き
4.得点化
Ⅲ 結果
1.関係語
2.内容範囲
3.関係語と内容範囲の交互作用
4.関係語の普遍性
5.自発的応答と誘発的応答
6.自発的応答と正しい応答のパーセント
7.自発的応答の分析
Ⅳ 考察
Ⅴ 要約
第7章 幼児における保存研究
―質問の種類,保存課題との関係―
Ⅰ 問題
Ⅱ 方法
1.被験児
2.手続き
3.説明の分類
4.得点化
Ⅲ 結果
1.年齢水準
2.課題の型
3.質問の種額
4.各年齢における保存課題の型と質問の種頬
5.説明の分類
Ⅳ 考察
Ⅴ 要約
第8章 数に関することばの発達
Ⅰ 問題
Ⅱ 研究 Ⅰ ―発達カリキュラム作成への一資料―
1.被験児
2.実験用具
3.手続き
4.結果と考察
Ⅲ 研究 Ⅱ ―縦断的研究―
1.被験児
2.実験用具
3.手続き
4.結果と考察
Ⅳ 要約
第9章 幼児期における数の保存獲得に関する3段階指導
Ⅰ 問題
Ⅱ 方法
1.被験児
2.実験材料
3.数の指導内容
4.指導タイプ分け
5.実験手続き
Ⅲ 結果
1.年齢別からみた各段階における指導効果
2.数の指導による長さ,多さの概念への般化
3.数の指導の維持効果
4.年齢と指導タイプの関係
5.4,5歳児における指導タイプと指導段階の関係
Ⅳ 考察
Ⅴ 要約
第10章 幼児期における数の指導
Ⅰ 知的活動における数
Ⅱ 子どもの生活と数
1.子どもの生活環境
2.ことばと数
Ⅲ 数の指導上の留意点
1.子どもの生活の中で
2.子どもの発達を知る
3.指導の原則
Ⅳ 数の指導
1.数の指導内容
2.数の指導
3.量の指導
4.図形・空間の指導
引用・参考文献
SUMMARY:A STUDY OF DEVELOPMENT AND TEACHING
OF NUMBER CONCEPTS
第1章 序論
Ⅰ 論文の構成
Ⅱ 研究の要旨
第2章 子どもの数概念
Ⅰ 子どもと数の関わり
1.集合数の理解
2.順序数の理解
3.数の理解の発達
Ⅱ 子どもと量の関わり
1.保存の理解
2.粒子観の理解
3.量の理解の発達
Ⅲ 遊びの中での数量の指導
1.遊びと数量的経験
2.数量の指導上の留意点
3.数量の指導
第3章 ピアジェの保存概念に関する先行研究
Ⅰ 問題
Ⅱ 研究の分摂
1.年代による分頼
2.刺激材料を変数とした分類
3.被験児の年齢を変数とした分頬
4.被験児の特性を変数とした分類
5.保存の訓練をとりあつかった研究
6.異文化における比較研究
Ⅲ 文献目録
Ⅳ 要約
第4章 幼年期における量概念の発達
Ⅰ 問題
Ⅱ 方法
1.被験者
2.実験手続き
Ⅲ 結果
1.年齢
2.量のタイプ
3.道具のタイプ
4.年齢と量のタイプの交互作用
5.量のタイプと道具のタイプの交互作用
6.道具間の相関
7.知能およびことばの成熟と量比較との相関
Ⅳ 考察
V 要約
第5章 児童・青年期における量概念の発達
Ⅰ 問題
Ⅱ 研究 Ⅰ ―小学生を対象にして―
Ⅲ 研究 Ⅱ ―中・高・大学生を対象にして―
Ⅳ 要約
第6章 数・量概念の研究における方法論的問題
―言語反応について―
Ⅰ 問題
Ⅱ 方法
1.被験児
2.用 具
3.手続き
4.得点化
Ⅲ 結果
1.関係語
2.内容範囲
3.関係語と内容範囲の交互作用
4.関係語の普遍性
5.自発的応答と誘発的応答
6.自発的応答と正しい応答のパーセント
7.自発的応答の分析
Ⅳ 考察
Ⅴ 要約
第7章 幼児における保存研究
―質問の種類,保存課題との関係―
Ⅰ 問題
Ⅱ 方法
1.被験児
2.手続き
3.説明の分類
4.得点化
Ⅲ 結果
1.年齢水準
2.課題の型
3.質問の種額
4.各年齢における保存課題の型と質問の種頬
5.説明の分類
Ⅳ 考察
Ⅴ 要約
第8章 数に関することばの発達
Ⅰ 問題
Ⅱ 研究 Ⅰ ―発達カリキュラム作成への一資料―
1.被験児
2.実験用具
3.手続き
4.結果と考察
Ⅲ 研究 Ⅱ ―縦断的研究―
1.被験児
2.実験用具
3.手続き
4.結果と考察
Ⅳ 要約
第9章 幼児期における数の保存獲得に関する3段階指導
Ⅰ 問題
Ⅱ 方法
1.被験児
2.実験材料
3.数の指導内容
4.指導タイプ分け
5.実験手続き
Ⅲ 結果
1.年齢別からみた各段階における指導効果
2.数の指導による長さ,多さの概念への般化
3.数の指導の維持効果
4.年齢と指導タイプの関係
5.4,5歳児における指導タイプと指導段階の関係
Ⅳ 考察
Ⅴ 要約
第10章 幼児期における数の指導
Ⅰ 知的活動における数
Ⅱ 子どもの生活と数
1.子どもの生活環境
2.ことばと数
Ⅲ 数の指導上の留意点
1.子どもの生活の中で
2.子どもの発達を知る
3.指導の原則
Ⅳ 数の指導
1.数の指導内容
2.数の指導
3.量の指導
4.図形・空間の指導
引用・参考文献
SUMMARY:A STUDY OF DEVELOPMENT AND TEACHING
OF NUMBER CONCEPTS
