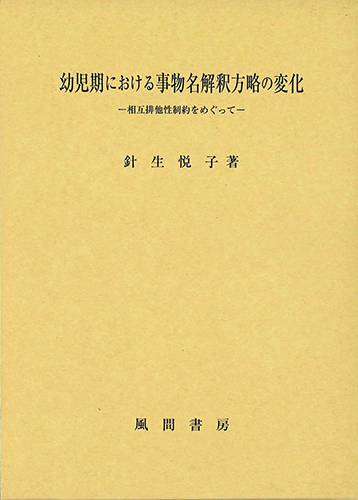
幼児期における事物名解釈方略の変化
相互排他性制約をめぐって
定価10,450円(本体 9,500円+税)
子どもが、発達初期の“一事物一名称”へのこだわりから、どのように抜け出し、言語の豊かな使い手になっていくのか、その発達的変化のメカニズムを明確にした書。
【著者略歴】
針生悦子(はりゅう えつこ)
1988年 お茶の水女子大学文教育学部卒業
1995年 東京大学大学院教育学研究科博士課程(教育心理学専攻)修了
博士(教育学)
現在 青山学院大学文学部専任講師
【著者略歴】
針生悦子(はりゅう えつこ)
1988年 お茶の水女子大学文教育学部卒業
1995年 東京大学大学院教育学研究科博士課程(教育心理学専攻)修了
博士(教育学)
現在 青山学院大学文学部専任講師
目次を表示
第1章 問題
(1.1)指示定義の曖昧さ
(1.2)語意仮説の源泉(制約)を明らかにすることの重要性
(1.3)古典的な語意発達理論の展開とその挫折
(1.4)非言語的な反応バイアスを語意仮説の源泉と見なす理論
(1.5)Markmanの語意制約の理論
(1.6)制約の生得性をめぐる議論
(1.7)制約の領域(内容)固有性をめぐる議論
(1.8)問題
第2章 3歳(年少)児は相互排他性制約を持つか
(2.1)第2章の目的と構成
(2.2)研究1:3歳(年少)児の物事選択における相互排他性原理
(2.3)研究2:文脈とラベルの提示順序が3歳(年少)児の事物選択に及ぼす効果
(2.4)研究3:事物選択の発達的変化
(2.5)研究4:3歳(年少)児のラベル解釈における相互排他性原理
(2.6)第2章のまとめ
第3章 相互排他性原理、文脈をめぐる事物名(ラベル)解釈方略の発達的変化
(3.1)第3章の目的と構成
(3.2)研究5:事物名解釈方略の発達的変化
(3.3)研究6:事物選択経験が後続のラベル解釈に及ぼす影響
(3.4)第3章のまとめ
(3.5)事物名解釈方略の発達的変化はどのようにして起こるか
(3.5.1)“解釈方略を決定するやり方の変化”としての発達的変化
(3.5.2)“言語観の変化”による説明
(3.5.3)“処理容量の拡大”による説明
(3.5.4)第4章以降での検討課題
第4章 外国語に関する知識が解釈方略に及ぼす影響
(4.1)第4章の目的と構成
(4.2)研究7:外国語ラベルに対する幼児の解釈方略
(4.3)研究8:言語間での複数ラベル受容と言語内での複数ラベル受容との関連
(4.4)第4章のまとめ
第5章 文脈と相互排他的な解釈との矛盾認識が解釈方略に及ぼす影響
(5.1)第5章の目的と構成
(5.2)研究9:子どもはラベルの指示対象のことをどのように説明するか
(5.3)研究10:未知物に関する説明が相互排他的な解釈に及ぼす影響
(5.4)第5章のまとめ
第6章 結論
(6.1)本論文の目的
(6.2)知見の要約
(6.2.1)3歳(年少)児は語意学習において相互排他性制約に従う
(6.2.2)大部分の子どもが文脈次第では積極的に1つの事物に複数の名称を認めるようになるのは5歳(年長)以降である
(6.2.3)事物名解釈方略の発達的変化を“処理容量の拡大”と“(それを前提とした)言語観の変化”によって説明する
(6.2.4)4歳(年中)以降の子どもでは外国語を知ることと事物名解釈方略とのあいだに関連が見られる
(6.2.5)4歳(年中)以降の子どもにおいて文脈と相互排他的な解釈との矛盾認識は事物名解釈方略の変化につながる
(6.3)結論
引用文献
おわりに
(1.1)指示定義の曖昧さ
(1.2)語意仮説の源泉(制約)を明らかにすることの重要性
(1.3)古典的な語意発達理論の展開とその挫折
(1.4)非言語的な反応バイアスを語意仮説の源泉と見なす理論
(1.5)Markmanの語意制約の理論
(1.6)制約の生得性をめぐる議論
(1.7)制約の領域(内容)固有性をめぐる議論
(1.8)問題
第2章 3歳(年少)児は相互排他性制約を持つか
(2.1)第2章の目的と構成
(2.2)研究1:3歳(年少)児の物事選択における相互排他性原理
(2.3)研究2:文脈とラベルの提示順序が3歳(年少)児の事物選択に及ぼす効果
(2.4)研究3:事物選択の発達的変化
(2.5)研究4:3歳(年少)児のラベル解釈における相互排他性原理
(2.6)第2章のまとめ
第3章 相互排他性原理、文脈をめぐる事物名(ラベル)解釈方略の発達的変化
(3.1)第3章の目的と構成
(3.2)研究5:事物名解釈方略の発達的変化
(3.3)研究6:事物選択経験が後続のラベル解釈に及ぼす影響
(3.4)第3章のまとめ
(3.5)事物名解釈方略の発達的変化はどのようにして起こるか
(3.5.1)“解釈方略を決定するやり方の変化”としての発達的変化
(3.5.2)“言語観の変化”による説明
(3.5.3)“処理容量の拡大”による説明
(3.5.4)第4章以降での検討課題
第4章 外国語に関する知識が解釈方略に及ぼす影響
(4.1)第4章の目的と構成
(4.2)研究7:外国語ラベルに対する幼児の解釈方略
(4.3)研究8:言語間での複数ラベル受容と言語内での複数ラベル受容との関連
(4.4)第4章のまとめ
第5章 文脈と相互排他的な解釈との矛盾認識が解釈方略に及ぼす影響
(5.1)第5章の目的と構成
(5.2)研究9:子どもはラベルの指示対象のことをどのように説明するか
(5.3)研究10:未知物に関する説明が相互排他的な解釈に及ぼす影響
(5.4)第5章のまとめ
第6章 結論
(6.1)本論文の目的
(6.2)知見の要約
(6.2.1)3歳(年少)児は語意学習において相互排他性制約に従う
(6.2.2)大部分の子どもが文脈次第では積極的に1つの事物に複数の名称を認めるようになるのは5歳(年長)以降である
(6.2.3)事物名解釈方略の発達的変化を“処理容量の拡大”と“(それを前提とした)言語観の変化”によって説明する
(6.2.4)4歳(年中)以降の子どもでは外国語を知ることと事物名解釈方略とのあいだに関連が見られる
(6.2.5)4歳(年中)以降の子どもにおいて文脈と相互排他的な解釈との矛盾認識は事物名解釈方略の変化につながる
(6.3)結論
引用文献
おわりに
