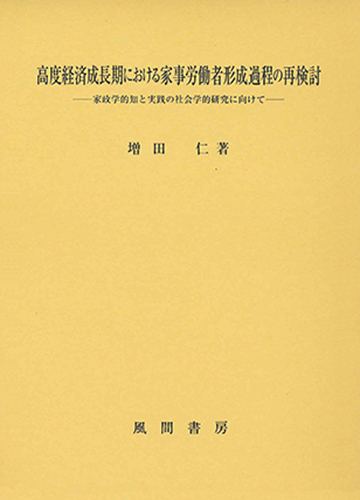
高度経済成長期における家事労働者形成過程の再検討
家政学的知と実践の社会学的研究に向けて
定価6,050円(本体 5,500円+税)
高度経済成長期において家政学的な教育実践が学校現場や地域社会でいかに展開したかを検討し、戦後日本における女性の労働、とりわけ家事労働者の再編過程を考察。
【著者略歴】
増田 仁(ますだ めぐみ)
1999年 京都大学教育学部教育社会学科卒業
2002年 京都大学大学院教育学研究科 教育科学専攻修士課程修了
修士(教育学)
2005年 京都大学大学院教育学研究科 教育科学専攻博士後期課程
研究指導認定退学
2008年 白大学教育学部 専任講師(2009年退職)
2014年 博士号(教育学)取得
現 在 熊本大学教育学部 講師(2009年より)
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示
第1章 本稿の目的・対象と分析枠組み
1-1 本稿の目的
1-2 本稿の分析対象
1-3 先行研究の検討と本稿の視点
1-3-1 家政学教育の学校・地域社会における位置づけ―過程に介入する知の形成と諸実践
1-3-2 学校現場における女性の家事労働者化―「ジェンダーと教育」研究と労働者形成
1-3-3 地域社会における女性の家事労働者化―「女性と労働」研究と農村社会
1-3-4 高度経済成長期論の再検討
第2章 家庭科教育という場―学校における「家事労働」教育の展開過程―
2-1 本章の対象と課題
2-2 発足当時の「家庭科」をめぐる葛藤
2-3 「主婦論争」と家庭科教育
2-4 女子必修化という戦略―雑誌『家庭科教育』派の教師による教育実践
2-5 日教組教研集会家庭科部会における教科論の変容―「労働力再生産論」を援用した教科論の形成
2-6 「労働力再生産論」と家庭科教育の臨界面―日教組の家庭科教師による教育実践
2-7 小括
第3章 高等学校商業科という場―学校における女子「労働者」の産出過程―
3-1 本章の対象と課題
3-2 戦後初期における商業科の教育実践―教育界と財界の視線の交差
3-3 「高度経済成長期」における商業科の教育実践―教育現場における葛藤とその「克服」過程
3-3-1 「高度経済成長期」における商業科をめぐる状況
3-3-2 「高度経済成長期」の商業教育をめぐる言説の展開
3-3-3 商業教育「無用論」と「体質改善」論
3-4 商業科の〈ジェンダー〉化
3-4-1 女子「特性」論の展開
3-4-2 カリキュラムの制度化
3-5 商業教育における〈隠れたカリキュラム〉の実践
3-5-1 〈隠れたカリキュラム〉を通した女子賃労働者の産出
3-5-2 〈隠れたカリキュラム〉を通した家事労働者の産出
3-6 小括
第4章 ホームプロジェクトという場―農村地域における「家事労働」教育の展開過程―
4-1 本章の対象と課題
4-2 調査地域の特徴と調査の概要
4-3 戦後日本におけるホームプロジェクト・家庭クラブの系譜―生活の「合理化」を担う女性の組織化
4-4 生徒から見た農村における女性労働
4-5 ホームプロジェクト・家庭クラブによる離乳食指導の展開過程―栃木県芳賀地区の上層部をターゲットに
4-6 生活の「合理化」をめぐって―中下層農村女性による「合理的」な生活の読みかえ
4-7 小括
第5章 共同炊事という場―女性「労働者」の多様な編成過程―
5-1 本章の対象と課題
5-2 共同炊事現象の概観と本章の調査対象
5-2-1 日本における共同炊事の系譜
5-2-2 調査地域における共同炊事の特質
5-3 調査の概要と調査地域の特徴
5-4 富裕農民による家事労働の〈外部化〉―栃木県氏家町における共同炊事の意味
5-5 零細農民による家事労働の〈共同化〉―栃木県喜連川町における共同炊事の意味
5-6 小括
第6章 結論
6-1 本論の総括
6-2 家政学的知と実践の社会学的研究に向けて
注
参考文献
謝辞
1-1 本稿の目的
1-2 本稿の分析対象
1-3 先行研究の検討と本稿の視点
1-3-1 家政学教育の学校・地域社会における位置づけ―過程に介入する知の形成と諸実践
1-3-2 学校現場における女性の家事労働者化―「ジェンダーと教育」研究と労働者形成
1-3-3 地域社会における女性の家事労働者化―「女性と労働」研究と農村社会
1-3-4 高度経済成長期論の再検討
第2章 家庭科教育という場―学校における「家事労働」教育の展開過程―
2-1 本章の対象と課題
2-2 発足当時の「家庭科」をめぐる葛藤
2-3 「主婦論争」と家庭科教育
2-4 女子必修化という戦略―雑誌『家庭科教育』派の教師による教育実践
2-5 日教組教研集会家庭科部会における教科論の変容―「労働力再生産論」を援用した教科論の形成
2-6 「労働力再生産論」と家庭科教育の臨界面―日教組の家庭科教師による教育実践
2-7 小括
第3章 高等学校商業科という場―学校における女子「労働者」の産出過程―
3-1 本章の対象と課題
3-2 戦後初期における商業科の教育実践―教育界と財界の視線の交差
3-3 「高度経済成長期」における商業科の教育実践―教育現場における葛藤とその「克服」過程
3-3-1 「高度経済成長期」における商業科をめぐる状況
3-3-2 「高度経済成長期」の商業教育をめぐる言説の展開
3-3-3 商業教育「無用論」と「体質改善」論
3-4 商業科の〈ジェンダー〉化
3-4-1 女子「特性」論の展開
3-4-2 カリキュラムの制度化
3-5 商業教育における〈隠れたカリキュラム〉の実践
3-5-1 〈隠れたカリキュラム〉を通した女子賃労働者の産出
3-5-2 〈隠れたカリキュラム〉を通した家事労働者の産出
3-6 小括
第4章 ホームプロジェクトという場―農村地域における「家事労働」教育の展開過程―
4-1 本章の対象と課題
4-2 調査地域の特徴と調査の概要
4-3 戦後日本におけるホームプロジェクト・家庭クラブの系譜―生活の「合理化」を担う女性の組織化
4-4 生徒から見た農村における女性労働
4-5 ホームプロジェクト・家庭クラブによる離乳食指導の展開過程―栃木県芳賀地区の上層部をターゲットに
4-6 生活の「合理化」をめぐって―中下層農村女性による「合理的」な生活の読みかえ
4-7 小括
第5章 共同炊事という場―女性「労働者」の多様な編成過程―
5-1 本章の対象と課題
5-2 共同炊事現象の概観と本章の調査対象
5-2-1 日本における共同炊事の系譜
5-2-2 調査地域における共同炊事の特質
5-3 調査の概要と調査地域の特徴
5-4 富裕農民による家事労働の〈外部化〉―栃木県氏家町における共同炊事の意味
5-5 零細農民による家事労働の〈共同化〉―栃木県喜連川町における共同炊事の意味
5-6 小括
第6章 結論
6-1 本論の総括
6-2 家政学的知と実践の社会学的研究に向けて
注
参考文献
謝辞
