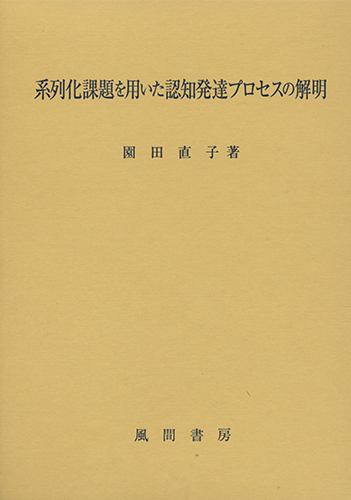
系列化課題を用いた認知発達プロセスの解明
定価7,150円(本体 6,500円+税)
幼児期から青年期までの系列化課題の解決方略の発達的変化を通じ、知覚に依存した認知構造がどのような位相を辿って論理思考に到達していくのかを明らかにする。
【著者略歴】
園田直子(そのだ なおこ)
1984年 九州大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程単位取得満期退学。
1987年 九州帝京短期大学勤務。
1995年 久留米大学文学部勤務。現在に至る。
2009年 博士(心理学)(九州大学大学院人間環境学府行動システム専攻 人環博乙 第35号)取得。
【著者略歴】
園田直子(そのだ なおこ)
1984年 九州大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程単位取得満期退学。
1987年 九州帝京短期大学勤務。
1995年 久留米大学文学部勤務。現在に至る。
2009年 博士(心理学)(九州大学大学院人間環境学府行動システム専攻 人環博乙 第35号)取得。
目次を表示
まえがき(丸野俊一)
本書の概要
第Ⅰ部 研究の背景
第1章 認知発達プロセスをとらえる手段としての系列化課題
はじめに
1.1. 系列化課題が解決できるためには
1.1.1. 系列化課題の構造
1.1.2. 系列化課題を解決するために必要な認知操作
1.1.3. 系列化課題を通してPiagetが仮定している認知発達過程:Piagetの発達段階論との対応
1.2. 系列化課題解決の基底に流れている推移律
1.2.1. 推移律とは何か
1.2.2. 推移律研究の歴史的展開
① 第Ⅰ期:推移律にもとづく思考操作の有無を決定づける要因に関する論争の時期(1950年代~1970年まで)
② 第Ⅱ期:推移律をめぐる構造論的アプローチと情報論的アプローチの発達論争の時期(1971年~1980年代頃まで)
③ 第Ⅲ期:系統発生の立場からの推移律研究から推移律課題の解決プロセスのシミュレーションへ(1980年代以降)
第Ⅱ部 問題と目的
第2章 系列化課題解決にはどのような認知ステップが必要か?
2.1. 推移律研究の論争を踏まえての系列化の発達プロセスモデルの提案
2.1.1. 学習型推移律課題と系列化課題の差異
2.1.2. 学習型推移律課題と系列化課題に共通する解決方略
2.1.3. 系列化の解決方略の発達的変化から想定される推移律の形成過程の3位相モデル
2.2. 本稿の目的と研究の指針 その1:位相1から位相2への移行
2.2.1. 推移律の形成段階における解決方略の発達プロセスの分析
2.2.2. 3位相モデルにもとづく研究1~3の位置づけ
2.2.3. 研究1~3で用いる系列化課題の限界点
2.3. 本稿の目的と研究の指針 その2:系列化の完成期に至る発達プロセス
2.3.1. 3位相モデルにもとづく研究4の位置づけ
2.3.2. 新たな系列化課題の創案
第Ⅲ部 推移律判断による系列化課題の解決に至るまでのプロセスの分析と訓練実験による操作的思考の形成の試み
第3章 研究1:位相1から位相2への発達的変化に関わる下位操作と認知プロセスの分析
3.1. 実験1:系列化のパフォーマンスを決定する課題条件とその背景にある認知プロセスの分析
3.1.1. 問題と目的
3.1.2. 方法
3.1.3. 結果と考察
3.2. 実験2:円の大きさと棒の長さの系列化の比較と系列化の遂行過程の分析
3.2.1. 問題と目的
3.2.2. 方法
3.2.3. 結果
3.2.4. 考察
第4章 研究2:系列化課題の解決に及ぼす言語能力および表現力の影響
4.1. 研究2の目的
4.2. 実験1:系列化の発達段階と言語の表現方法との対応関係
4.2.1. 目的
4.2.2. 方法
4.2.3. 結果と考察
4.3. 実験2:比較をあらわす言語能力の獲得が思考の形成に及ぼす影響
4.3.1. 目的
4.3.2. 方法
4.3.3. 結果と考察
4.4. 総合考察
第5章 研究3:下位操作を統合するモニタリングにもとづく比較方略の訓練実験
5.1. 系列化の構成過程におけるモニタリングの発達
5.1.1. 問題と目的
5.2. 実験1:系列化の遂行過程におけるモニタリングの発達
5.2.1. 目的
5.2.2. 方法
5.2.3. 結果
5.2.4. 考察
5.3. 実験2:モニタリングにもとづく自己教示訓練の効果
5.3.1. 問題と目的
5.3.2. 方法
5.3.3. 結果と考察
5.4. 研究3のまとめ
5.5. 研究1~3で残された課題
第Ⅳ部 新たな系列化課題を用いた推移律の完成期に至る発達プロセスの探究
第6章 研究4:知覚的判断から推移律判断にもとづく系列化への変化過程~重さ課題を用いて~
6.1. 問題と目的
6.2. 方法
6.3. 結果と考察
6.3.1. 正答率の結果
6.3.2. 方略の分析
6.4. 総合考察
第Ⅴ部 総合考察
第7章 系列化課題を用いることによって明らかになった認知発達プロセスとは
7.1. 本稿のまとめ
7.1.1. 3位相モデルにもとづく研究1~4の位置づけと概要
7.1.2. 系列化課題の解決における比較方略に焦点をあてた本研究の特色と意義
7.1.3. 重さの系列化課題における双方向の比較の達成時期のズレについて
7.2. 今後の課題と展望
文献
各章の内容と研究発表との対応関係
おわりに
本書の概要
第Ⅰ部 研究の背景
第1章 認知発達プロセスをとらえる手段としての系列化課題
はじめに
1.1. 系列化課題が解決できるためには
1.1.1. 系列化課題の構造
1.1.2. 系列化課題を解決するために必要な認知操作
1.1.3. 系列化課題を通してPiagetが仮定している認知発達過程:Piagetの発達段階論との対応
1.2. 系列化課題解決の基底に流れている推移律
1.2.1. 推移律とは何か
1.2.2. 推移律研究の歴史的展開
① 第Ⅰ期:推移律にもとづく思考操作の有無を決定づける要因に関する論争の時期(1950年代~1970年まで)
② 第Ⅱ期:推移律をめぐる構造論的アプローチと情報論的アプローチの発達論争の時期(1971年~1980年代頃まで)
③ 第Ⅲ期:系統発生の立場からの推移律研究から推移律課題の解決プロセスのシミュレーションへ(1980年代以降)
第Ⅱ部 問題と目的
第2章 系列化課題解決にはどのような認知ステップが必要か?
2.1. 推移律研究の論争を踏まえての系列化の発達プロセスモデルの提案
2.1.1. 学習型推移律課題と系列化課題の差異
2.1.2. 学習型推移律課題と系列化課題に共通する解決方略
2.1.3. 系列化の解決方略の発達的変化から想定される推移律の形成過程の3位相モデル
2.2. 本稿の目的と研究の指針 その1:位相1から位相2への移行
2.2.1. 推移律の形成段階における解決方略の発達プロセスの分析
2.2.2. 3位相モデルにもとづく研究1~3の位置づけ
2.2.3. 研究1~3で用いる系列化課題の限界点
2.3. 本稿の目的と研究の指針 その2:系列化の完成期に至る発達プロセス
2.3.1. 3位相モデルにもとづく研究4の位置づけ
2.3.2. 新たな系列化課題の創案
第Ⅲ部 推移律判断による系列化課題の解決に至るまでのプロセスの分析と訓練実験による操作的思考の形成の試み
第3章 研究1:位相1から位相2への発達的変化に関わる下位操作と認知プロセスの分析
3.1. 実験1:系列化のパフォーマンスを決定する課題条件とその背景にある認知プロセスの分析
3.1.1. 問題と目的
3.1.2. 方法
3.1.3. 結果と考察
3.2. 実験2:円の大きさと棒の長さの系列化の比較と系列化の遂行過程の分析
3.2.1. 問題と目的
3.2.2. 方法
3.2.3. 結果
3.2.4. 考察
第4章 研究2:系列化課題の解決に及ぼす言語能力および表現力の影響
4.1. 研究2の目的
4.2. 実験1:系列化の発達段階と言語の表現方法との対応関係
4.2.1. 目的
4.2.2. 方法
4.2.3. 結果と考察
4.3. 実験2:比較をあらわす言語能力の獲得が思考の形成に及ぼす影響
4.3.1. 目的
4.3.2. 方法
4.3.3. 結果と考察
4.4. 総合考察
第5章 研究3:下位操作を統合するモニタリングにもとづく比較方略の訓練実験
5.1. 系列化の構成過程におけるモニタリングの発達
5.1.1. 問題と目的
5.2. 実験1:系列化の遂行過程におけるモニタリングの発達
5.2.1. 目的
5.2.2. 方法
5.2.3. 結果
5.2.4. 考察
5.3. 実験2:モニタリングにもとづく自己教示訓練の効果
5.3.1. 問題と目的
5.3.2. 方法
5.3.3. 結果と考察
5.4. 研究3のまとめ
5.5. 研究1~3で残された課題
第Ⅳ部 新たな系列化課題を用いた推移律の完成期に至る発達プロセスの探究
第6章 研究4:知覚的判断から推移律判断にもとづく系列化への変化過程~重さ課題を用いて~
6.1. 問題と目的
6.2. 方法
6.3. 結果と考察
6.3.1. 正答率の結果
6.3.2. 方略の分析
6.4. 総合考察
第Ⅴ部 総合考察
第7章 系列化課題を用いることによって明らかになった認知発達プロセスとは
7.1. 本稿のまとめ
7.1.1. 3位相モデルにもとづく研究1~4の位置づけと概要
7.1.2. 系列化課題の解決における比較方略に焦点をあてた本研究の特色と意義
7.1.3. 重さの系列化課題における双方向の比較の達成時期のズレについて
7.2. 今後の課題と展望
文献
各章の内容と研究発表との対応関係
おわりに
