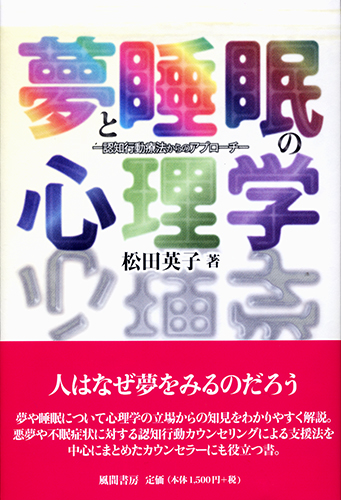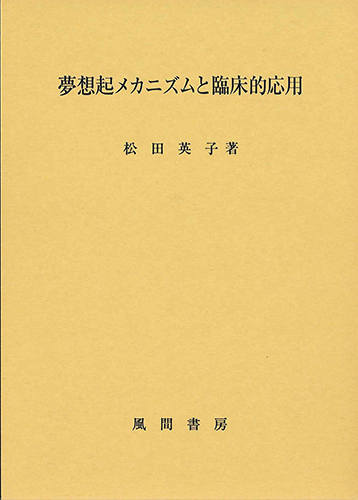
夢想起メカニズムと臨床的応用
定価9,350円(本体 8,500円+税)
本書は、夢想起メカニズムについて生理・心理・社会的要因から明らかにした上で、悪夢症状の治療モデルを提案し証拠に基づく臨床心理学の実践を試みたものである。
【著者略歴】
松田英子(まつだ えいこ)
1971年9月 石川県金沢市生まれ
1994年3月 お茶の水女子大学文教育学部教育学科(心理学)卒業
1996年3月 お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修士課程修了
2000年3月 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科単位取得退学
2000年4月 江戸川大学社会学部人間社会学科専任講師
2003年4月 江戸川大学社会学部人間社会学科助教授
現在に至る
博士(人文科学)(乙第187号、2003年3月 お茶の水女子大学)
臨床心理士、専門健康心理士
専攻
臨床心理学、人格心理学、健康心理学
【著者略歴】
松田英子(まつだ えいこ)
1971年9月 石川県金沢市生まれ
1994年3月 お茶の水女子大学文教育学部教育学科(心理学)卒業
1996年3月 お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修士課程修了
2000年3月 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科単位取得退学
2000年4月 江戸川大学社会学部人間社会学科専任講師
2003年4月 江戸川大学社会学部人間社会学科助教授
現在に至る
博士(人文科学)(乙第187号、2003年3月 お茶の水女子大学)
臨床心理士、専門健康心理士
専攻
臨床心理学、人格心理学、健康心理学
目次を表示
序 文
第I部 夢研究の現状と本研究による問題提起
第1章 夢研究の史的背景と動向
1-1.本研究の視点
1-2.精神分析モデルによる古典的夢理論
1-3.夢生起メカニズムとレム睡眠
1-4.情報処理モデルによる夢理論
第2章 本研究の課題―臨床的応用に向けた夢想起研究―
2-1.夢想起研究の必要性
2-2.夢想起と大脳の情報処理特性
2-3.夢想起メカニズムと関連要因
2-4.臨床的応用に向けた夢想起メカニズムの検討
2-5.本研究の位置づけと目的
2-6.本研究における仮説
2-7.本研究の構成
第Ⅱ部 夢想起メカニズムの検討
第Ⅱ部の概要一方法論と目的
第3章 夢想起と人格特性(研究1)―MMPIによる夢想起頻度と内容の分析―
3-1.問題の所在と目的
3-2.方法
3-3.結果
3-4.考察
第4章 夢想起頻度に人格特性とストレスフルライフイベント
及ぼす影響(研究2)
4-1.問題の所在と目的(研究2-1)
4-2.方法(研究2-1)
4-3.結果と考察(研究2-1)
4-4.問題の所在と目的(研究2-2)
4-5.方法(研究2-2)
4-6.結果と考察(研究2-2)
4-7.総合的考察
第5章 夢想起と覚醒水準(研究3)
一睡眠中のレムに関する実験的検討-
5-1.問題の所在と目的(研究3-1)
5-2.方法(研究3-1)
5-3.結果と考察(研究3-1)
5-4.問題の所在と目的(研究3-2)
5-5.方法(研究3-2)
5-6.結果と考察(研究3-2)
5-7.総合的考察
第Ⅱ部の全般的考察―夢想起の発現モデル―
第Ⅲ部 夢想起の臨床的応用
第Ⅲ部の概要―悪夢障害の治療法開発の必要性―
第6章 非臨床者の不安夢への認知療法的支援(研究4)
―レムによる治療効果の実験的検討―
6-1.問題の所在と目的
6-2.方法
6-3.結果
6-4.考察
第7章 臨床者の悪夢への認知療法DMCT
(DreamMediateとCognitiveTherapy)の適用(研究5)
7-1.問題の所在と目的
7-2.方法
7-3.治療経過
7-4.考察
第Ⅲ部の全般的考察―ネガティブな夢想起の消去モデル―
第Ⅳ部 本研究の成果と今後の夢研究の展望
第8章 本研究で得られた知見の総括
8-1.夢想起の発現モデル
8-2.ネガティブな夢想起の治療モデル
8-3.DMCTモデルによる情報処理促進効果・
8-4.本研究全体の意義
8-5.悪夢障害と情動情報流出過多仮説の提出
第9章 今後の夢想起研究と課題
9-1.夢想起と精神病理の関連
9-2.レムの機能について
―眼球運動を利用した心理療法EMDRとの関連―
9-3.夢想起の制御可能性について
9-4.治療媒体としての夢一悪夢の認知療法利用と適用可能性-
9-5.夢想起の機能について
9-6.夢想起研究と今後の課題
引用文献
謝辞
第I部 夢研究の現状と本研究による問題提起
第1章 夢研究の史的背景と動向
1-1.本研究の視点
1-2.精神分析モデルによる古典的夢理論
1-3.夢生起メカニズムとレム睡眠
1-4.情報処理モデルによる夢理論
第2章 本研究の課題―臨床的応用に向けた夢想起研究―
2-1.夢想起研究の必要性
2-2.夢想起と大脳の情報処理特性
2-3.夢想起メカニズムと関連要因
2-4.臨床的応用に向けた夢想起メカニズムの検討
2-5.本研究の位置づけと目的
2-6.本研究における仮説
2-7.本研究の構成
第Ⅱ部 夢想起メカニズムの検討
第Ⅱ部の概要一方法論と目的
第3章 夢想起と人格特性(研究1)―MMPIによる夢想起頻度と内容の分析―
3-1.問題の所在と目的
3-2.方法
3-3.結果
3-4.考察
第4章 夢想起頻度に人格特性とストレスフルライフイベント
及ぼす影響(研究2)
4-1.問題の所在と目的(研究2-1)
4-2.方法(研究2-1)
4-3.結果と考察(研究2-1)
4-4.問題の所在と目的(研究2-2)
4-5.方法(研究2-2)
4-6.結果と考察(研究2-2)
4-7.総合的考察
第5章 夢想起と覚醒水準(研究3)
一睡眠中のレムに関する実験的検討-
5-1.問題の所在と目的(研究3-1)
5-2.方法(研究3-1)
5-3.結果と考察(研究3-1)
5-4.問題の所在と目的(研究3-2)
5-5.方法(研究3-2)
5-6.結果と考察(研究3-2)
5-7.総合的考察
第Ⅱ部の全般的考察―夢想起の発現モデル―
第Ⅲ部 夢想起の臨床的応用
第Ⅲ部の概要―悪夢障害の治療法開発の必要性―
第6章 非臨床者の不安夢への認知療法的支援(研究4)
―レムによる治療効果の実験的検討―
6-1.問題の所在と目的
6-2.方法
6-3.結果
6-4.考察
第7章 臨床者の悪夢への認知療法DMCT
(DreamMediateとCognitiveTherapy)の適用(研究5)
7-1.問題の所在と目的
7-2.方法
7-3.治療経過
7-4.考察
第Ⅲ部の全般的考察―ネガティブな夢想起の消去モデル―
第Ⅳ部 本研究の成果と今後の夢研究の展望
第8章 本研究で得られた知見の総括
8-1.夢想起の発現モデル
8-2.ネガティブな夢想起の治療モデル
8-3.DMCTモデルによる情報処理促進効果・
8-4.本研究全体の意義
8-5.悪夢障害と情動情報流出過多仮説の提出
第9章 今後の夢想起研究と課題
9-1.夢想起と精神病理の関連
9-2.レムの機能について
―眼球運動を利用した心理療法EMDRとの関連―
9-3.夢想起の制御可能性について
9-4.治療媒体としての夢一悪夢の認知療法利用と適用可能性-
9-5.夢想起の機能について
9-6.夢想起研究と今後の課題
引用文献
謝辞