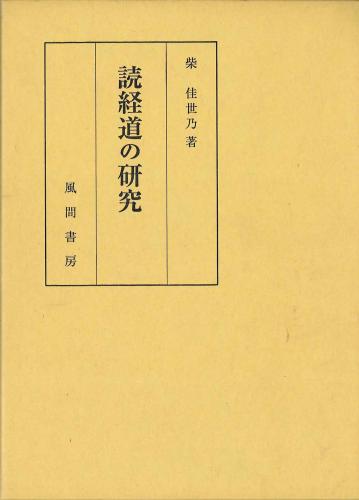
読経道の研究
定価15,400円(本体 14,000円+税)
申し訳ございませんが、只今品切れ中です。
読経は正確な字音の読みに加えて音曲面が重視され、秘事を伴って平安末期から鎌倉初期にかけて徐々に芸道として形成された。その様相を文学的見地から論じる。
【著者略歴】
柴佳世乃(しば かよの)
1966年 静岡県に生まれる
1989年 お茶の水女子大学文教育学部国文学科卒業
1988年 お茶の水女子大学大学院博士課程人間文化研究科単位取得退学、お茶の水女子大学助手、日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、
2001年10月より 千葉大学文学部助教授
2001年6月 博士(人文科学)(お茶の水女子大学)
第28回財団法人日本古典文学会賞受賞(2002年)
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示
序 説
論考編
第一部 「読経道」考
第一章 法華経読誦の盛行―読経道形成前夜―
はじめに
一 一条朝における読経の盛行
二 読経道の萌芽
第二章 「読経道」考
はじめに
一 読経道の存在
1 『元享釈書』
2 『読経口伝明鏡集』
3 但馬温泉寺蔵『法華経音曲』
二 良能の活躍
おわりに ―能誉の編纂意識
第三章 読経道の形成と展開
はじめに
一 読経道の隆盛―後嵯峨院
二 読経道の形成―後白河院
三 読経道の展開―後鳥羽院
おわりに
第二部 書写山と読経道
第一章 書写山をめぐる法華経読誦
はじめに
一 書写山に伝えられた読誦の流
二 性空上人をめぐる言説
おわりに
第二章 法華経はいかに読誦されたか―但馬温泉寺蔵『法華経音曲』をよむ―
はじめに
一 但馬温泉寺蔵『法華経音曲』
二 書写山と法華経音曲
三 『法華経音曲』の検討
おわりに
第三章 但馬温泉寺蔵「法華経音曲相承血脈」の位相
はじめに
一 書写山における読経の相承
二 書写山と後白河院、ならびに真性
おわりに
第四章 書写山の秘説をめぐって―書写山と慶政に関する新出資料―
はじめに
一 書写山の秘説―『書写山真言書』
二 『書写山真言書』と慶政
三 慶政と書写山
おわりに
第三部 能読の道命阿闍梨
第一章 能読の道命阿闍梨
はじめに
一 読経音曲の始祖道命
二 道命像を辿る
おわりに
第二章 道命と法輪寺―西行から見た―
はじめに
一 法輪寺の空仁と西行
二 法輪寺と道命阿闍梨
三 道命と西行
四 西行時代の法輪寺
おわりに
第三章 『宇治拾遺物語』第一話考
はじめに
一 読経道の形成と道命への視線
二 道命和泉式部説話の萌芽
三 『宇治拾遺』第一話への一視角
おわりに
第四部 明覚流の法華経読誦
第一章 明覚と読経道
はじめに
一 字音史における明覚
二 『法華秘中略歎抄』
三 明覚流の師資相承の実態
四 明覚流の系譜
おわりに―明覚流読経の位相
第二章 読経道の説話形成―明覚流を基点として―
はじめに
一 禽獣の声を聴く
二 龍宮相承
三 読経道の説話形成の一側面
おわりに
資料編
一 三千院円融蔵『読経口伝明鏡集』解題と影印
二 薬師寺蔵『法華声口伝』解題と翻刻
三 但馬温泉寺蔵『法華経音曲』解題と翻刻
四 法明院蔵『法華秘中略歎鈔』ならびに明覚流伝書 解題と翻刻
1 『法華秘中略歎鈔』
2 『法華経声図』『陀羅尼品相伝』『随訓抄』『閑語抄』
むすびにかえて
引用資料一覧
あとがき
索引
人名索引
書名・事項索引
論考編
第一部 「読経道」考
第一章 法華経読誦の盛行―読経道形成前夜―
はじめに
一 一条朝における読経の盛行
二 読経道の萌芽
第二章 「読経道」考
はじめに
一 読経道の存在
1 『元享釈書』
2 『読経口伝明鏡集』
3 但馬温泉寺蔵『法華経音曲』
二 良能の活躍
おわりに ―能誉の編纂意識
第三章 読経道の形成と展開
はじめに
一 読経道の隆盛―後嵯峨院
二 読経道の形成―後白河院
三 読経道の展開―後鳥羽院
おわりに
第二部 書写山と読経道
第一章 書写山をめぐる法華経読誦
はじめに
一 書写山に伝えられた読誦の流
二 性空上人をめぐる言説
おわりに
第二章 法華経はいかに読誦されたか―但馬温泉寺蔵『法華経音曲』をよむ―
はじめに
一 但馬温泉寺蔵『法華経音曲』
二 書写山と法華経音曲
三 『法華経音曲』の検討
おわりに
第三章 但馬温泉寺蔵「法華経音曲相承血脈」の位相
はじめに
一 書写山における読経の相承
二 書写山と後白河院、ならびに真性
おわりに
第四章 書写山の秘説をめぐって―書写山と慶政に関する新出資料―
はじめに
一 書写山の秘説―『書写山真言書』
二 『書写山真言書』と慶政
三 慶政と書写山
おわりに
第三部 能読の道命阿闍梨
第一章 能読の道命阿闍梨
はじめに
一 読経音曲の始祖道命
二 道命像を辿る
おわりに
第二章 道命と法輪寺―西行から見た―
はじめに
一 法輪寺の空仁と西行
二 法輪寺と道命阿闍梨
三 道命と西行
四 西行時代の法輪寺
おわりに
第三章 『宇治拾遺物語』第一話考
はじめに
一 読経道の形成と道命への視線
二 道命和泉式部説話の萌芽
三 『宇治拾遺』第一話への一視角
おわりに
第四部 明覚流の法華経読誦
第一章 明覚と読経道
はじめに
一 字音史における明覚
二 『法華秘中略歎抄』
三 明覚流の師資相承の実態
四 明覚流の系譜
おわりに―明覚流読経の位相
第二章 読経道の説話形成―明覚流を基点として―
はじめに
一 禽獣の声を聴く
二 龍宮相承
三 読経道の説話形成の一側面
おわりに
資料編
一 三千院円融蔵『読経口伝明鏡集』解題と影印
二 薬師寺蔵『法華声口伝』解題と翻刻
三 但馬温泉寺蔵『法華経音曲』解題と翻刻
四 法明院蔵『法華秘中略歎鈔』ならびに明覚流伝書 解題と翻刻
1 『法華秘中略歎鈔』
2 『法華経声図』『陀羅尼品相伝』『随訓抄』『閑語抄』
むすびにかえて
引用資料一覧
あとがき
索引
人名索引
書名・事項索引
