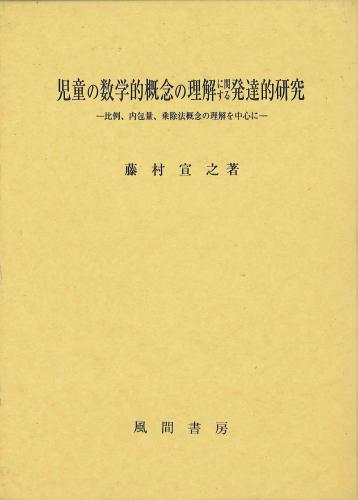
児童の数学的概念の理解に関する発達的研究
比例、内包量、乗除法概念の理解を中心に
定価12,100円(本体 11,000円+税)
申し訳ございませんが、只今品切れ中です。
小学生が、比例、内包量(単位あたり量)、乗除法といった数学的概念を理解するプロセスを、12の実験と調査から発達的に検討し、算数教育への示唆を導いた意欲作。
【著者略歴】
藤村宣之(ふじむら のぶゆき)
1965年 大阪府吹田市に生まれる
1989年 京都大学教育学部教育学科卒業
1994年 京都大学大学院教育学研究科博士後期課程学修認定退学
1995年 博士(教育学)(京都大学)
現在 埼玉大学教育学部助教授
専攻
教育心理学
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示
第1章 序論
第1節 児童期の認知発達と学習
第2節 数学的概念の理解の発達
第2章 比例,内包量,乗除法の理解に関する諸モデルと本研究の課題
第1節 比例・内包量理解の発達に関する諸モデル
1-1 Piaget派の発達モデル
1-2 認知発達研究における諸モデル
1-2-1 情報処理モデル
1-2-2 情報統合モデル
1-2-3 認知発達研究における諸モデル―まとめ
1-3 数学教育研究における諸モデル
1-3-1 Noeltingの発達モデル
1-3-2 Karplusのモデル―推理パターン理論
1-3-3 Vergnaudのモデル―測度の同型性
1-3-4 数学教育研究における諸モデル―まとめ
第2節 比例・内包量理解の発達に関する研究課題
2-1 モデル間の主張の相違に関する研究課題
2-1-1 定量推理の下位段階
2-1-2 定量推理の出現年齢
2-1-3 領域の効果
2-2 理解を規定する要因に関する研究課題
2-2-1 定量推理と定性推理の関連
2-2-2 課題に対する推理過程
2-3 比例・内包量理解の発達に関する本研究の課題(第2節のまとめ)
第3節 比例・内包量理解の促進に関する諸研究と本研究の課題
第4節 乗除法の理解に関する諸研究と本研究の課題
第3章 比例・内包量理解の発達に関する研究Ⅰ:理解の段階,出現年齢,
領域差
第1節 問題の設定
1-1 内包量理解の段階,出現年齢
1-2 比例・内包量理解の領域固有性
第2節 研究1:内包量理解の横断的検討
2-1 目的
2-2 方法
2-3 結果
2-4 考察
第3節 研究2:内包量理解の縦断的検討
3-1 目的
3-2 方法
3-3 結果
3-4 考察
第4節 研究3:比例・内包量理解における領域固有性の検討
4-1 目的
4-2 方法
4-3 結果
4-4 考察
第5節 総合考察
第4章 比例・内包量理解の発達に関する研究Ⅱ:理解を規定する要因
第1節 問題の設定
1-1 定性推理と定量推理の関連
1-2 内包量に関する推理過程
1-2-1 内包量に関する推理過程のモデル化
1-2-2 内包量の推理過程に関する先行研究
第2節 研究4:比例理解における定性推理と定量推理の関連
2-1 目的
2-2 方法
2-3 結果
2-4 考察
第3節 研究5:内包量に関する推理過程の検討Ⅰ
3-1 目的
3-2 方法
3-3 結果と考察
第4節 研究6:内包量に関する推理過程の検討Ⅱ
4-1 目的
4-2 方法
4-3 結果
4-4 考察
第5節 総合考察
第5章 内包量理解の促進に関する研究
第1節 問題の設定
第2節 研究7:比例的推理を特質とした具体物の操作による内包量理解の促進
2-1 目的
2-2 方法
2-3 結果
2-4 考察
第3節 研究8:関係表象の精緻化による内包量理解の促進Ⅰ
3-1 目的
3-2 方法
3-3 結果と考察
第4節 研究9:関係表象の精緻化による内包量理解の促進Ⅱ
4-1 目的
4-2 方法
4-3 結果と考察
第5節 総合考察
第6章 乗除法の意味理解の発達に関する研究
第1節 問題の設定
1-1 算数教育上の問題と本研究の課題
1-2 乗除法の理解に関する先行研究と本研究の課題
第2節 研究10:乗除法作問能力の横断的検討
2-1 目的
2-2 方法
2-3 結果
2-4 考察
第3節 研究11:乗除法作問能力の縦断的検討
3-1 目的
3-2 方法
3-3 結果と考察
第4節 研究12:乗除法における作問と文章題解決の関連
4-1 目的
4-2 方法
4-3 結果と考察
第5節 総合考察
第7章 総括
第1節 全体的考察
第2節 算数教育への示唆
要約
引用文献
事項索引
人名索引
第1節 児童期の認知発達と学習
第2節 数学的概念の理解の発達
第2章 比例,内包量,乗除法の理解に関する諸モデルと本研究の課題
第1節 比例・内包量理解の発達に関する諸モデル
1-1 Piaget派の発達モデル
1-2 認知発達研究における諸モデル
1-2-1 情報処理モデル
1-2-2 情報統合モデル
1-2-3 認知発達研究における諸モデル―まとめ
1-3 数学教育研究における諸モデル
1-3-1 Noeltingの発達モデル
1-3-2 Karplusのモデル―推理パターン理論
1-3-3 Vergnaudのモデル―測度の同型性
1-3-4 数学教育研究における諸モデル―まとめ
第2節 比例・内包量理解の発達に関する研究課題
2-1 モデル間の主張の相違に関する研究課題
2-1-1 定量推理の下位段階
2-1-2 定量推理の出現年齢
2-1-3 領域の効果
2-2 理解を規定する要因に関する研究課題
2-2-1 定量推理と定性推理の関連
2-2-2 課題に対する推理過程
2-3 比例・内包量理解の発達に関する本研究の課題(第2節のまとめ)
第3節 比例・内包量理解の促進に関する諸研究と本研究の課題
第4節 乗除法の理解に関する諸研究と本研究の課題
第3章 比例・内包量理解の発達に関する研究Ⅰ:理解の段階,出現年齢,
領域差
第1節 問題の設定
1-1 内包量理解の段階,出現年齢
1-2 比例・内包量理解の領域固有性
第2節 研究1:内包量理解の横断的検討
2-1 目的
2-2 方法
2-3 結果
2-4 考察
第3節 研究2:内包量理解の縦断的検討
3-1 目的
3-2 方法
3-3 結果
3-4 考察
第4節 研究3:比例・内包量理解における領域固有性の検討
4-1 目的
4-2 方法
4-3 結果
4-4 考察
第5節 総合考察
第4章 比例・内包量理解の発達に関する研究Ⅱ:理解を規定する要因
第1節 問題の設定
1-1 定性推理と定量推理の関連
1-2 内包量に関する推理過程
1-2-1 内包量に関する推理過程のモデル化
1-2-2 内包量の推理過程に関する先行研究
第2節 研究4:比例理解における定性推理と定量推理の関連
2-1 目的
2-2 方法
2-3 結果
2-4 考察
第3節 研究5:内包量に関する推理過程の検討Ⅰ
3-1 目的
3-2 方法
3-3 結果と考察
第4節 研究6:内包量に関する推理過程の検討Ⅱ
4-1 目的
4-2 方法
4-3 結果
4-4 考察
第5節 総合考察
第5章 内包量理解の促進に関する研究
第1節 問題の設定
第2節 研究7:比例的推理を特質とした具体物の操作による内包量理解の促進
2-1 目的
2-2 方法
2-3 結果
2-4 考察
第3節 研究8:関係表象の精緻化による内包量理解の促進Ⅰ
3-1 目的
3-2 方法
3-3 結果と考察
第4節 研究9:関係表象の精緻化による内包量理解の促進Ⅱ
4-1 目的
4-2 方法
4-3 結果と考察
第5節 総合考察
第6章 乗除法の意味理解の発達に関する研究
第1節 問題の設定
1-1 算数教育上の問題と本研究の課題
1-2 乗除法の理解に関する先行研究と本研究の課題
第2節 研究10:乗除法作問能力の横断的検討
2-1 目的
2-2 方法
2-3 結果
2-4 考察
第3節 研究11:乗除法作問能力の縦断的検討
3-1 目的
3-2 方法
3-3 結果と考察
第4節 研究12:乗除法における作問と文章題解決の関連
4-1 目的
4-2 方法
4-3 結果と考察
第5節 総合考察
第7章 総括
第1節 全体的考察
第2節 算数教育への示唆
要約
引用文献
事項索引
人名索引
