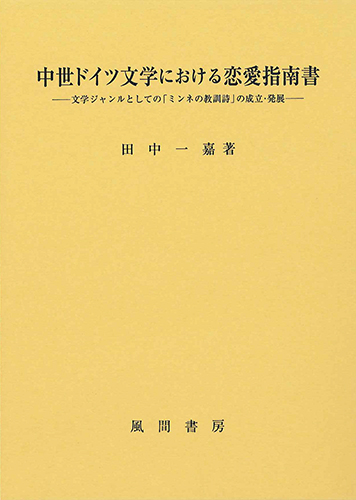ことばと文化の饗宴
西洋古典の源流と芸術・思想・社会の視座
定価3,080円(本体 2,800円+税)
文学・音楽・哲学・思想・歴史など各執筆者の専門領域によって「ことば」から「文化」をとらえ、その可能性を追求。
【執筆者紹介】
古澤ゆう子(ふるさわ ゆうこ)
国際基督教大学卒業、ヴュルツブルク大学博士課程修了(Dr.Phil.)。一橋大学大学院言語社会研究科特任教授。西洋古典学、独語文学における古典受容研究。
アルボガスト・シュミット(Arbogast Schmitt)
ヴュルツブルク大学哲学科にて博士学位(Dr.Phil.)・教授資格取得。マインツ大学教授、マールブルク大学教授歴任。ベルリン自由大学名誉教授。古代哲学〈プラトン、アリストテレス)、古典文献学(ホメロス叙事詩、悲劇)研究。
栗原雅美(くりはら まさみ)
早稲田大学第一文学部哲学専修卒業、一橋大学大学院言語社会研究科修士課程修了、同博士課程単位取得退学。マールブルク大学西洋古典学科、ドイツ語教授法コース留学(現在ドイツ在住)。アリストテレス哲学、余暇(スコレー)研究、ドイツ語教授法、ドイツと日本相互間における思想受容史。
田中一嘉(たなか かずよし)
一橋大学大学院言語社会研究科博士課程修了(学術博士)。成蹊大学文学部助手。中世ドイツ文学・文化研究。
尾方一郎(おがた いちろう)
東京大学大学院博士課程中退(文学修士)。一橋大学大学院言語社会研究科教授。ドイツ文学、文化史研究。
布川恭子(ぬのかわ やすこ)
中央大学卒業。一橋大学大学院言語社会研究科博士課程修了(学術博士)。共立女子大学非常勤講師、明治大学附属高等学校非常勤講師その他を経て、現在ドイツ在住。世紀転換期のドイツ語圏、特にオーストリアにおける文学、社会、思想、哲学。ドイツ語圏現代文学。ドイツ語教授法。
田中奈津子(たなか なつこ)
岡山大学卒業。一橋大学大学院言語社会研究科博士課程在籍。カストラートの流行・受容史研究。
小場瀬純子(おばせ じゅんこ)
東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学院音楽研究科修士課程修了。一橋大学大学院言語社会研究科修士課程修了。現在、同博士課程在籍。東京藝術大学演奏芸術センター非常勤講師。シューマン研究。
中村美智太郎(なかむら みちたろう)
慶應義塾大学卒業。一橋大学大学院言語社会研究科博士課程修了。博士(学術)。静岡大学教育学部講師。哲学・倫理学・近代ドイツ思想・教育思想。
比嘉徹徳(ひが てつのり)
法政大学社会学部卒。一橋大学大学院言語社会研究科博士課程修了。博士(学術)。精神分析、社会思想史。
石浜裕子(いしはま ひろこ)
一橋大学大学院言語社会研究科博士後期課程単位取得退学。フランス語マグレブ文学研究。
植松なつみ(うえまつ なつみ)
一橋大学大学院言語社会研究科博士課程単位取得満期退学。東京都立西高等学校ドイツ語非常勤講師ほか。第二次世界大戦後のドイツ文学。ドイツ語圏現代文学。
金 賢信(キム ヒョンシン)
韓国外国語大学卒業。一橋大学大学院言語社会研究科博士課程修了(学術博士)。中央大学総合政策研究科非常勤講師。異文化間コミュニケーション、外国語教育、日韓関係史研究。
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示
はじめに
第一章 古典のアウロラ
1 アポロンの神託―ソフォクレス『オイディプス王』と『ソクラテスの弁明』に即して 古澤ゆう子
2 幸福について―行為における充全な自己表現の発現としての幸福 アルボガスト・シュミット/栗原雅美訳
3 「魂の翼」―魂の不死なる本性について 栗原雅美
第二章 テクストからの跳躍
1 ハインリヒ・フォン・フォルデケの『エネアス物語』に見られる恋愛力学―中世ヨーロッパにおける古典受容の一形態 田中一嘉
2 『魔の山』にみる中断の意味 尾方一郎
3 ピュグマリオン神話の普遍性―ローベルト・ムージルを手がかりとして 布川恭子
第三章 音楽の転調
1 カストラートの流行と声の特徴性 田中奈津子
2 スフィンクスの謎―シューマンの《謝肉祭》作品九における「音」と「ことば」 木場瀬純子
第四章 思考の場
1 醜のダイナミズム―カントにおける「吐き気」をめぐる問題とアドルノの「市民意識」 中村美智太郎
2 メランコリー論の系譜―フロイト、アブラハム、ライク 比嘉徹徳
3 書くことのできる言語で何を書いたのだろうか 石浜裕子
第五章 戦争体験とテクスト
1 過去、現在、未来―ハインリヒ・ベル『九時半の玉突き』 植村なつみ
2 韓国で原爆を考える―三つの小説を中心に 金 賢信
おわりに
執筆者プロフィール
第一章 古典のアウロラ
1 アポロンの神託―ソフォクレス『オイディプス王』と『ソクラテスの弁明』に即して 古澤ゆう子
2 幸福について―行為における充全な自己表現の発現としての幸福 アルボガスト・シュミット/栗原雅美訳
3 「魂の翼」―魂の不死なる本性について 栗原雅美
第二章 テクストからの跳躍
1 ハインリヒ・フォン・フォルデケの『エネアス物語』に見られる恋愛力学―中世ヨーロッパにおける古典受容の一形態 田中一嘉
2 『魔の山』にみる中断の意味 尾方一郎
3 ピュグマリオン神話の普遍性―ローベルト・ムージルを手がかりとして 布川恭子
第三章 音楽の転調
1 カストラートの流行と声の特徴性 田中奈津子
2 スフィンクスの謎―シューマンの《謝肉祭》作品九における「音」と「ことば」 木場瀬純子
第四章 思考の場
1 醜のダイナミズム―カントにおける「吐き気」をめぐる問題とアドルノの「市民意識」 中村美智太郎
2 メランコリー論の系譜―フロイト、アブラハム、ライク 比嘉徹徳
3 書くことのできる言語で何を書いたのだろうか 石浜裕子
第五章 戦争体験とテクスト
1 過去、現在、未来―ハインリヒ・ベル『九時半の玉突き』 植村なつみ
2 韓国で原爆を考える―三つの小説を中心に 金 賢信
おわりに
執筆者プロフィール