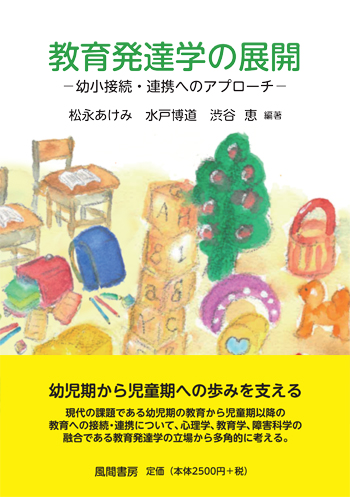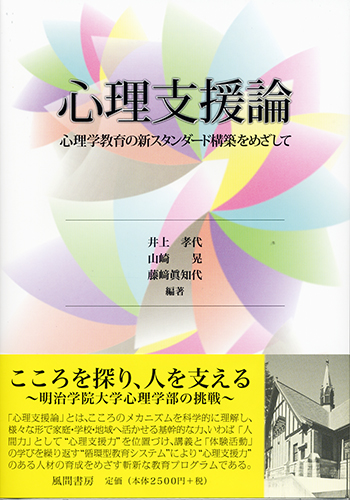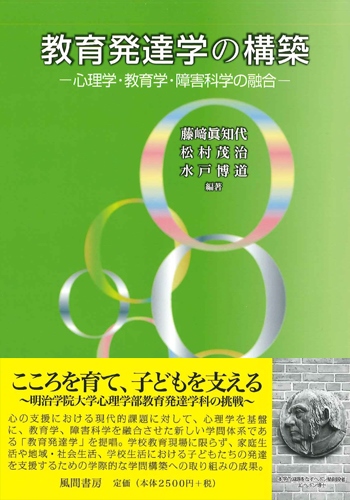
教育発達学の構築
心理学・教育学・障害科学の融合
定価2,750円(本体 2,500円+税)
明治学院大学教育発達学科の挑戦。心理学を基盤に、教育学・障害科学を融合させた新しい学問体系である教育発達学から、子どもの様々な問題を支援する。
【編者紹介】
藤﨑眞知代(ふじさき まちよ)(第Ⅰ部第2章、第Ⅳ部循環型教育システムによる学び、第15章)
お茶の水女子大学大学院博士課程人間文化研究科単位取得退学。現職:明治学院大学教授。修士(家政学)。臨床発達心理士スーパーヴァイザー。
松村茂治(まつむら しげはる)(第Ⅰ部第3章、第Ⅳ部第18章)
東京教育大学大学院博士課程単位取得退学。現職:明治学院大学教授。修士(教育学)。学校心理士、特別支援教育士スーパーヴァイザー。
水戸博道(みと ひろみち)(第Ⅱ部第8章)
ローハンプトン大学博士課程修了。現職:明治学院大学教授。PhD。
【執筆者紹介】
新井哲夫(あらい てつお)(第Ⅱ部第9章、第Ⅳ部第15,18,19章)
横浜国立大学大学院修士課程教育学研究科修了。現職:明治学院大学教授。修士(教育学)
井 陽介(い ようすけ)(第Ⅳ部第15,17章)
横浜国立大学大学院教育学研究科学校教育学専攻修了。現職:明治学院大学助手、修士(教育学)
緒方明子(おがた あきこ)(第Ⅲ部第11章、第Ⅳ部第14章)
筑波大学大学院博士課程心身障害学研究科修了。現職:明治学院大学教授。博士(教育学)。特別支援教育士スーパーヴァイザー、学校心理士。
金子 健(かねこ たけし)(第Ⅲ部第11章、第Ⅳ部第14章)
筑波大学大学院博士課程心身障害学研究科単位取得満期退学。現職:明治学院大学教授。修士(教育学)。
川渕竜也(かわぶち たつや)(第Ⅳ部第14章)
明治学院大学大学院文学研究科心理学専攻修了。現職:明治学院大学助手。修士(心理学)。臨床心理士。
小林潤一郎(こばやし じゅんいちろう)(第Ⅲ部第12章、第Ⅳ部循環型教育システムによる学び、第16章)
筑波大学医学専門学群卒業。明治学院大学教授。小児科専門医、心身医療「小児科」専門医。
佐藤 公(さとう こう)(第Ⅰ部第4章)
筑波大学大学院博士課程教育学研究科単位取得退学。現職:明治学院大学准教授。修士(教育学)。
辻 宏子(つじ ひろこ)(第Ⅱ部第6章、第Ⅳ部第19章)
筑波大学博士課程教育学研究科単位取得退学。現職:明治学院大学准教授。修士(教育学)。
出井雄二(でい ゆうじ)(第Ⅱ部第10章)
千葉大学教育学部小学校教員養成課程卒業。現職:明治学院大学准教授。学士(教育学)。
中村敦雄(なかむら あつお)(第Ⅱ部第5章)
東京学芸大学大学院修士課程教育学研究科国語教育専攻修了。現職:明治学院大学教授。修士(教育学)。
長谷川康男(はせがわ やすお)(第Ⅱ部第7章、第Ⅳ部第15章)
早稲田大学教育学部社会科社会科学専修卒。現職:明治学院大学准教授。
溝川 藍(みぞかわ あい)(第Ⅰ部第1章、第Ⅳ部第14,17章)
京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。現職:明治学院大学助教。博士(教育学)。
渡邉 流理也(わたなべ るりや)(第Ⅳ部第16、17章)
東京学芸大学連合大学院学校教育学研究科修了。現職:明治学院大学助手。博士(教育学)。
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示
まえがき
第Ⅰ部 子どもの生活と発達の姿
第1章 子どもの生活と認知発達
―幼児期・児童期の世界を捉える心の働き―溝川 藍
はじめに
1 ピアジェの認知発達理論
2 ピアジェ以後の認知発達研究
3 幼児期・児童期の「心の理論」の発達
4 認知発達の現代的課題
5 まとめにかえて―認知発達の今後の学び―
第2章 子どもの生活と自己の発達 藤﨑眞知代
はじめに
1 人の存在をどのように捉えるか
2 自分に気づくプロセス
3 生活習慣の自立と遊びを通した自己への気づき
4 自己肯定感としてのコンピテンスからレジリエンスへ
5 社会・文化のなかでの自己の発達と大人のかかわり
6 今後の課題
第3章 子どもの学校生活と発達 松村茂治
はじめに
1 時間的な流れの中での発達
2 子どもの学校生活と発達
おわりに
第4 子どもの発達を支える教育方法 佐藤 公
はじめに
1 教育の本質と教育方法のあり方
2 教育の方法をめぐる考え方の広がりと多様性
3 社会の変化に伴う教育方法の発想とその転換
4 現代社会の要請を具体化する教育方法
おわりに
第Ⅱ部 子どもの生活と学習
第5章 国語科授業の歴史にみる子どもの発達
―教材「せんこう花火」の実践から― 中村敦雄
はじめに
1 小学校高学年教材「せんこう花火」
2 「せんこう花火」を扱った授業の変化
3 今後の課題
第6章 数や図形との出会いと発達 辻 宏子
はじめに
1 算数・数学に関わる子どもの現状
2 「何を教えるか」から「どのような経験を実現するか」への転換
3 これからの数と図形の学びとは
第7章 社会との出会いと発達
はじめに
1 子どもの社会との出会いと社会認識の発達
2 子どもの社会との出会いと発達の具体的な姿
―4年「ごみの処理と利用」を通して―
おわりに
第8章 音楽との出会いと発達 水戸博道
はじめに
1 音楽的発達研究の変遷
2 音楽的発達の出発点、過程、到達点
3 音楽的発達の到達点
4 何が発達するのか
5 どのように発達するのか
まとめ
第9章 造形活動との出会いと発達 新井哲夫
はじめに
1 子どもの描画への関心
2 子どもの描画への発達研究―発達的アプローチ―
3 子どもの描画の発達とその道筋
おわりに
第10章 運動との出会いと発達 出井雄二
はじめに
1 身体の発育と運動能力の発達
2 日本の子どもの現状
3 運動との出会いと教育
4 今後の課題―運動との望ましい出会いのために―
第Ⅲ部 障害児の生活と発達
第11章 障害児の発達と学校における支援 緒方明子
はじめに
1 乳幼児期の気づきと支援
2 児童期における気づきと支援
3 今後の課題
第12章 障害児の病理と特別支援教育 小林 潤一郎
はじめに
1 特別支援教育と小児医療
2 障害のある子どもの医療
3 子どもに生じる障害
4 障害のある子どもの教育と健康支援
5 今後の課題
第13章 障害児の発達と教育制度 金子 健
はじめに
1 教育発達学における特別支援教育学
2 特別支援教育制度の構築
3 特別支援教育からユニバーサルデザインへ
4 共生社会をめざした教育改革
第Ⅳ部 教員養成の新たなスタンダードをめざして
《循環型教育システムによる学び》 藤﨑眞知代・小林潤一郎
《学生の学び》
第14章 体験活動を通した学び 川渕竜也・緒方明子・溝川 藍
はじめに
1 体験活動とは
2 体験活動を通した学び
第15章 幼稚園・小学校での教育実習を通して 井 陽介・新井哲夫・長谷川康男・藤﨑眞知代
はじめに
1 幼稚園教育実習を通した学び
2 小学校教育実習を通した学び
第16章 特別支援学校での教育実習を通して 渡邉流理也・小林潤一郎・金子 健
はじめに
1 特別支援学校教員免許状とは
2 本学科における特別支援学校教員免許状取得者及び取得希望者
3 特別支援学校教諭一種免許状取得に必要な授業科目
4 特別支援学校教育実習の前提条件
5 特別支援学校教育実習オリエンテーション
6 特別支援学校教育実習
まとめ
第17章 「教育発達学」の4年間の学びと進路選択 溝川 藍・井 陽介・渡邉流理也
はじめに
1 教員免許状取得希望の動向(2010年度入学生、2011年度入学生:資料調査)
2 2年次の体験活動が進路選択に及ぼす影響(2011年度入学生、4年次春学期、質問紙調査)
3 進路決定の契機、教職の魅力・気がかりの認知(2010年度入学生、4年次秋学期、質問紙調査)
4 まとめと今後の展望
《教員の学び》
第18章 Faculty Development(FD)を通した学び 松村茂治・新井哲夫
はじめに
1 教育発達学科の教育目標
2 教員の構成とFD研修
3 FD研修の実際
第19章 PSY-PORTFOLIOシステムの構築と活用 辻 宏子・新井哲夫
1 大学教育に求められる質的転換
2 大学教育におけるデジタル・ポートフォリオの可能性
3 PSY-PORTFOLIO
4 今後の課題
あとがき
第Ⅰ部 子どもの生活と発達の姿
第1章 子どもの生活と認知発達
―幼児期・児童期の世界を捉える心の働き―溝川 藍
はじめに
1 ピアジェの認知発達理論
2 ピアジェ以後の認知発達研究
3 幼児期・児童期の「心の理論」の発達
4 認知発達の現代的課題
5 まとめにかえて―認知発達の今後の学び―
第2章 子どもの生活と自己の発達 藤﨑眞知代
はじめに
1 人の存在をどのように捉えるか
2 自分に気づくプロセス
3 生活習慣の自立と遊びを通した自己への気づき
4 自己肯定感としてのコンピテンスからレジリエンスへ
5 社会・文化のなかでの自己の発達と大人のかかわり
6 今後の課題
第3章 子どもの学校生活と発達 松村茂治
はじめに
1 時間的な流れの中での発達
2 子どもの学校生活と発達
おわりに
第4 子どもの発達を支える教育方法 佐藤 公
はじめに
1 教育の本質と教育方法のあり方
2 教育の方法をめぐる考え方の広がりと多様性
3 社会の変化に伴う教育方法の発想とその転換
4 現代社会の要請を具体化する教育方法
おわりに
第Ⅱ部 子どもの生活と学習
第5章 国語科授業の歴史にみる子どもの発達
―教材「せんこう花火」の実践から― 中村敦雄
はじめに
1 小学校高学年教材「せんこう花火」
2 「せんこう花火」を扱った授業の変化
3 今後の課題
第6章 数や図形との出会いと発達 辻 宏子
はじめに
1 算数・数学に関わる子どもの現状
2 「何を教えるか」から「どのような経験を実現するか」への転換
3 これからの数と図形の学びとは
第7章 社会との出会いと発達
はじめに
1 子どもの社会との出会いと社会認識の発達
2 子どもの社会との出会いと発達の具体的な姿
―4年「ごみの処理と利用」を通して―
おわりに
第8章 音楽との出会いと発達 水戸博道
はじめに
1 音楽的発達研究の変遷
2 音楽的発達の出発点、過程、到達点
3 音楽的発達の到達点
4 何が発達するのか
5 どのように発達するのか
まとめ
第9章 造形活動との出会いと発達 新井哲夫
はじめに
1 子どもの描画への関心
2 子どもの描画への発達研究―発達的アプローチ―
3 子どもの描画の発達とその道筋
おわりに
第10章 運動との出会いと発達 出井雄二
はじめに
1 身体の発育と運動能力の発達
2 日本の子どもの現状
3 運動との出会いと教育
4 今後の課題―運動との望ましい出会いのために―
第Ⅲ部 障害児の生活と発達
第11章 障害児の発達と学校における支援 緒方明子
はじめに
1 乳幼児期の気づきと支援
2 児童期における気づきと支援
3 今後の課題
第12章 障害児の病理と特別支援教育 小林 潤一郎
はじめに
1 特別支援教育と小児医療
2 障害のある子どもの医療
3 子どもに生じる障害
4 障害のある子どもの教育と健康支援
5 今後の課題
第13章 障害児の発達と教育制度 金子 健
はじめに
1 教育発達学における特別支援教育学
2 特別支援教育制度の構築
3 特別支援教育からユニバーサルデザインへ
4 共生社会をめざした教育改革
第Ⅳ部 教員養成の新たなスタンダードをめざして
《循環型教育システムによる学び》 藤﨑眞知代・小林潤一郎
《学生の学び》
第14章 体験活動を通した学び 川渕竜也・緒方明子・溝川 藍
はじめに
1 体験活動とは
2 体験活動を通した学び
第15章 幼稚園・小学校での教育実習を通して 井 陽介・新井哲夫・長谷川康男・藤﨑眞知代
はじめに
1 幼稚園教育実習を通した学び
2 小学校教育実習を通した学び
第16章 特別支援学校での教育実習を通して 渡邉流理也・小林潤一郎・金子 健
はじめに
1 特別支援学校教員免許状とは
2 本学科における特別支援学校教員免許状取得者及び取得希望者
3 特別支援学校教諭一種免許状取得に必要な授業科目
4 特別支援学校教育実習の前提条件
5 特別支援学校教育実習オリエンテーション
6 特別支援学校教育実習
まとめ
第17章 「教育発達学」の4年間の学びと進路選択 溝川 藍・井 陽介・渡邉流理也
はじめに
1 教員免許状取得希望の動向(2010年度入学生、2011年度入学生:資料調査)
2 2年次の体験活動が進路選択に及ぼす影響(2011年度入学生、4年次春学期、質問紙調査)
3 進路決定の契機、教職の魅力・気がかりの認知(2010年度入学生、4年次秋学期、質問紙調査)
4 まとめと今後の展望
《教員の学び》
第18章 Faculty Development(FD)を通した学び 松村茂治・新井哲夫
はじめに
1 教育発達学科の教育目標
2 教員の構成とFD研修
3 FD研修の実際
第19章 PSY-PORTFOLIOシステムの構築と活用 辻 宏子・新井哲夫
1 大学教育に求められる質的転換
2 大学教育におけるデジタル・ポートフォリオの可能性
3 PSY-PORTFOLIO
4 今後の課題
あとがき