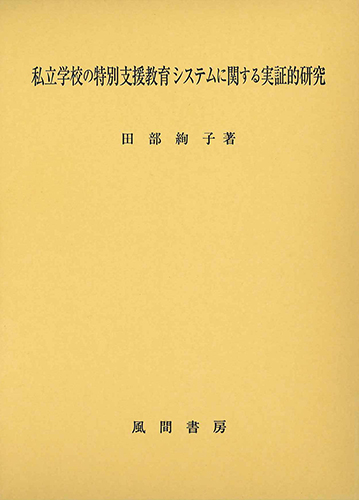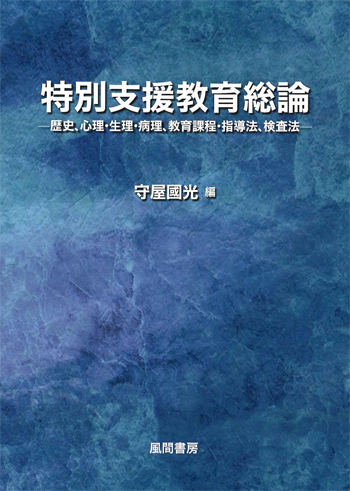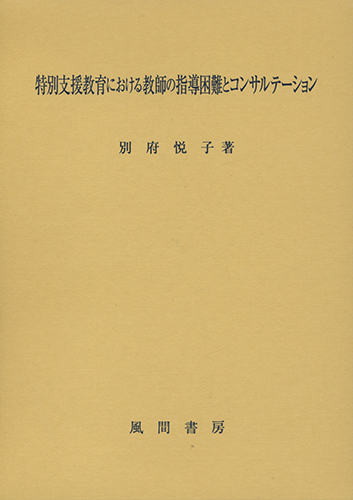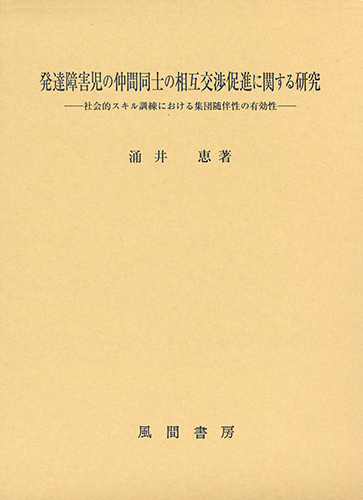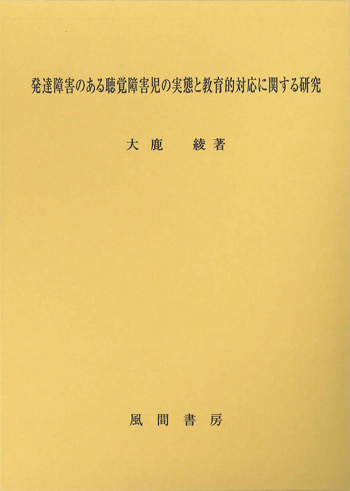
発達障害のある聴覚障害児の実態と教育的対応に関する研究
定価7,700円(本体 7,000円+税)
発達障害を併せ持つ聴覚障害児の存在に着目した先駆的著。全国聾学校及び通級指導教室への実態調査から困難の類型化、事例検討までを総合的に考察。関係者必携の書。
【著者略歴】
大鹿 綾(おおしか あや)
2005年 東京学芸大学教育学部障害児教育教員養成課程言語障害教育専攻卒業
2007年 東京学芸大学大学院教育学研究科(修士課程)特別支援教育専攻支援方法コース修了
2010年 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(博士課程)学校教育学専攻発達支援講座修了
博士(教育学)取得
2011年 広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践支援センター
特任助教
2013年 日本学術振興会特別研究員(PD)
現在に至る
※データは刊行当時のものです※
目次を表示
序論
1.聴覚障害児教育におけるコミュニケーション手段の変遷とその多様化
2.聴覚障害児教育の現状と課題
3.特殊教育から特別支援教育へ
4.目的
第1章 PRSを用いた発達障害のある聴覚障害児の実態調査【研究1】
1-1.基礎的資料(聾学校小学部)
1-1-1.目的
1-1-2.方法
1-1-3.結果
1-1-4.考察
1-2.発達障害のある聴覚障害児の類型化
1-2-1.目的
1-2-2.方法
1-2-3.結果
1-2-4.考察
1-3.第1章のまとめ
第2章 文部科学省調査(2002)を用いた発達障害のある聴覚障害児の実態調査【研究2】
2-1.聾学校幼稚部~中学部の実態調査
2-1-1.基礎的資料(聾学校幼稚部~中学部)
2-1-2.発達障害のある聴覚障害児の類型化
2-1-3.まとめ
2-2.難聴特別支援学級・通級指導教室の実態調査
2-2-1.基礎的資料(難聴特別支援学級・通級指導教室)
2-2-2.発達障害のある聴覚障害児の類型化
2-2-3.まとめ
2-3.第2章のまとめ
第3章 発達障害のある聴覚障害児に対する評価基準の検討【研究3】
3-1.聴覚障害児版評価基準の提案
3-1-1.目的
3-1-2.方法
3-1-3.結果
3-1-4.考察
3-2.聴覚障害児版評価基準の妥当性の検証
3-2-1.目的
3-2-2.方法
3-2-3.結果
3-2-4.考察
3-3.第3章のまとめ
第4章 類型化から得られた典型事例による困難の整理【研究4】
―継続的な支援を通じての変容と課題―
4-1.目的と手続き
4-2.事例
4-2-1.アスペルガー症候群の診断をうけている事例(第1クラスタ)
4-2-2.音読に特徴的な困難のある事例(第2クラスタ)
4-2-3.複数の項目を同時に扱う学習や不注意に困難のある事例(第2クラスタ)
4-3.第4章のまとめ
総合考察
1.発達障害のある聴覚障害児の割合について
2.発達障害のある聴覚障害児における特徴に応じた支援について
3.今後の課題
文献
資料
謝辞
1.聴覚障害児教育におけるコミュニケーション手段の変遷とその多様化
2.聴覚障害児教育の現状と課題
3.特殊教育から特別支援教育へ
4.目的
第1章 PRSを用いた発達障害のある聴覚障害児の実態調査【研究1】
1-1.基礎的資料(聾学校小学部)
1-1-1.目的
1-1-2.方法
1-1-3.結果
1-1-4.考察
1-2.発達障害のある聴覚障害児の類型化
1-2-1.目的
1-2-2.方法
1-2-3.結果
1-2-4.考察
1-3.第1章のまとめ
第2章 文部科学省調査(2002)を用いた発達障害のある聴覚障害児の実態調査【研究2】
2-1.聾学校幼稚部~中学部の実態調査
2-1-1.基礎的資料(聾学校幼稚部~中学部)
2-1-2.発達障害のある聴覚障害児の類型化
2-1-3.まとめ
2-2.難聴特別支援学級・通級指導教室の実態調査
2-2-1.基礎的資料(難聴特別支援学級・通級指導教室)
2-2-2.発達障害のある聴覚障害児の類型化
2-2-3.まとめ
2-3.第2章のまとめ
第3章 発達障害のある聴覚障害児に対する評価基準の検討【研究3】
3-1.聴覚障害児版評価基準の提案
3-1-1.目的
3-1-2.方法
3-1-3.結果
3-1-4.考察
3-2.聴覚障害児版評価基準の妥当性の検証
3-2-1.目的
3-2-2.方法
3-2-3.結果
3-2-4.考察
3-3.第3章のまとめ
第4章 類型化から得られた典型事例による困難の整理【研究4】
―継続的な支援を通じての変容と課題―
4-1.目的と手続き
4-2.事例
4-2-1.アスペルガー症候群の診断をうけている事例(第1クラスタ)
4-2-2.音読に特徴的な困難のある事例(第2クラスタ)
4-2-3.複数の項目を同時に扱う学習や不注意に困難のある事例(第2クラスタ)
4-3.第4章のまとめ
総合考察
1.発達障害のある聴覚障害児の割合について
2.発達障害のある聴覚障害児における特徴に応じた支援について
3.今後の課題
文献
資料
謝辞