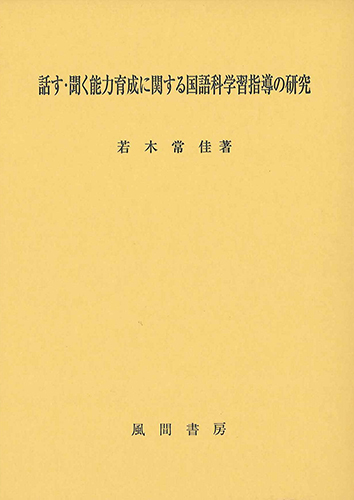大村はまの「学習の手びき」についての研究
授業における個性化と個別化の実現
定価9,350円(本体 8,500円+税)
大村はまの実践と教育観を取り上げ、その中核である「学習の手びき」の特性を解明。一般的教室での国語科の指導において、個性化と個別化を実現するための具体的方法を示した。
【著者略歴】
若木常佳(わかき つねか)
1962年 広島県生まれ
広島大学大学院教育学研究科博士課程後期文化教育開発専攻(国語文化教育学分野)修了(2007年3月)博士(教育学)
福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻 教授
1985~2007年 広島県内の公立中学校に国語科教員として勤務
2007~2009年 大阪体育大学健康福祉学部 准教授
2009~2011年 福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻 准教授
2012年より現職
※データは刊行当時のものです※
主要著書・論文
『話し合う力を育てる授業の実際―系統性を意識した三年間―』(2001)渓水社
『話す・聞く能力育成に関する国語科学習指導の研究』(2011)風間書房
「対話能力を育成するためのカリキュラムについての研究―「方略的知識」と「関係づける力」を中心に―」(2005)(「国語科教育」全国大学国語教育学会 第58集)「小・中学生における聞き取り能力の実際と指導上の課題―「並列的複数情報の関係づけを支える心的作業」について―」(2009)(「国語科教育」全国大学国語教育学会 第65集)「授業リフレクションの実践と課題」(「教育学研究紀要」中国四国教育学会 第58巻)「話し合い指導における「尋ね合い」の存在―表出したものから「道のり」への視点転換―」(2016)(「福岡教育大学紀要」第65号)「教師教育において集積させる経験について」(2016)(「九州国語教育学会紀要」九州国語教育学会 第5号)「教師教育とリフレクション―「8つの問い」を活用した「気づき」の実際」(2016)(「教育学研究紀要」中国四国教育学会 第61巻)
目次を表示
序文(世羅博昭)
はじめに
序章 研究の目的・方法・意義
第1節 研究の目的と方法
第1項 研究の目的
第2項 研究の方法
第2節 本研究の意義
第1項 大村研究からの意義
第2項 授業改善からの意義
第3項 教師教育からの意義
第1章 学校における授業が抱える課題と改善の道筋
第1節 学校における授業が抱える課題
第1項 今後において求められる能力と授業構造
1 学習者に求められる能力
2 求められる授業構造
第2項 求められる能力に対する現実的な問題
1 能力の二重性という問題
2 教室の中の現実的問題
第3項 学校という「装置」がもたらす問題
1 学校という「装置」
2 学校という「装置」と学習者の問題
3 学校という「装置」と教師の問題
第2節 授業改善の道筋
第1項 求められる変革
1 学校の中にある「観」の変革
2 個性化につながる個別化という考え方
第2項 授業改善への道筋
1 教師の煩悶
2 「典型」への照射
3 授業改善への道筋の提示
第2章 大村はまの国語科単元学習
第1節 大村はまのめざした世界とその背景
第1項 大村はまの教育観とその背景
1 学習者に対する視線と教えることの意味
2 大村はまの理想とする教室のイメージ
3 それらの背景となること
第2項 大村はまの教育観とそれに基づく実践の現代的価値
1 学校における授業が抱える課題との関係から捉えられる価値
2 教師の資質・能力の伸長との関係から捉えられる価値
第2節 大村はまと国語科単元学習
第1項 国語科における単元学習
1 単元学習における思想
2 展開される学習活動
3 国語科における単元学習の原理
第2項 大村はまの国語科単元学習
1 その成立
2 大村はまの国語科単元学習
第3章 大村はまの「学習の手びき」の実際と分析1―通覧―
第1節 大村はまの「学習の手びき」の実際
第1項 「学習の手びき」の整理
1 整理の方法
2 整理した「学習の手びき」一覧
第2項 「学習の手びき」の実際
1 「学習の手びき」の内容
2 「学習の手びき」の表現
3 「学習の手びき」が導く学習
第2節 通覧から見出せる「学習の手びき」の機能
第1項 「学習の手びき」の使われ方から導出される機能
1 端から丁寧に読んで使うタイプの「学習の手びき」の場合
2 眺めながらヒントとして使うタイプの「学習の手びき」の場合
3 繰り返し読んで使うタイプの「学習の手びき」の場合
第2項 学習者と指導者に対しての機能
1 学習者に対する機能
2 指導者に対する機能
第3項 通覧から導出した「学習の手びき」の特性
1 「学習の手びき」の役割
2 「学習の手びき」の特性
第4章 大村はまの「学習の手びき」の実際と分析2―詳察―
第1節 対象とする実践の選択と詳察の方法
第1項 対象とする実践
1 選択の条件
2 詳察のする対象について
第2項 詳察の方法
第2節 「学習の手びき」の詳察
第1項 単元「私たちの読書力〈図表を読む〉」の場合
1 概略
2 本授業における「学習の手びき」について
3 「学習の手びき」の考察と検証
4 「学習の手びき」に見出される工夫
第2項 「古典への入門―枕草子によって―」の場合
1 概略
2 本授業における「学習の手びき」について
3 「学習の手びき」の考察と検証
4 「学習の手びき」に見出される工夫
第3項 「楽しくつくる『旅の絵本』」の場合
1 概略
2 本授業における「学習の手びき」について
3 「学習の手びき」の考察と検証
4 「学習の手びき」に見出される工夫
第4項 詳察から導出した「学習の手びき」の特性
1 「学習の手びき」の役割
2 「学習の手びき」の特性
第5章 授業における個性化と個別化の実現に向けて
第1節 授業における個性化と個別化を実現するための「学習の手びき」
第1項 個性化と個別化について
1 実現すべき個性化と個別化の状態
2 個性化のために重要な個別化
第2項 個性化と個別化を実現する「学習の手びき」に必要なこと
1 大村はまの「学習の手びき」に示されたこと
2 個性化と個別化を実現する「学習の手びき」のあり方
第2節 個性化と個別化を実現する「学習の手びき」に至るまでの道筋
第1項 大村はまの辿った道筋
1 基盤となる教育観の醸成と学習者としての体験
2 「学習の手びき」作成までの実際のプロセス
第2項 教師が大村はまの「学習の手びき」から「典型」を得るための道筋
1 大村はまの「学習の手びき」を体験すること
2 自己の教育観と対面すること
3 教師が大村はまの「学習の手びき」から「典型」を得るための道筋
第3項 授業における個性化と個別化の実現に向けて
1 学習者からの出発の必要性
2 授業研究の場の活用による学習者理解
終章 研究のまとめ
第1節 研究の総括
第1項 学校における授業が抱える課題と改善の道筋(第1章の内容)
1 授業に存在する解決すべき課題
2 課題に対する改善の道筋
第2項 大村はまの国語科単元学習(第2章の内容)
1 大村はまの教育観と現代の教育課題との関わり
2 大村はまの国語科単元学習の内実
第3項 大村はまの「学習の手びき」の実際と分析1―通覧―(第3章の内容)
1 「学習の手びき」の整理
2 通覧から見出せる「学習の手びき」の機能と特性
第4項 大村はまの「学習の手びき」の実際と分析2―詳察―(第4章の内容)
1 学習過程を再現して考察・検証するという方法
2 詳察から見出せる「学習の手びき」の機能と特性
第5項 授業における個性化と個別化の実現(第5章の内容)
1 個性化と個別化を実現する「学習の手びき」のあり方の整理
2 教師が大村はまの「学習の手びき」から「典型」を得るための道筋
第2節 今後の課題
第1項 研究成果に基づく学校現場での解説についての研究
第2項 授業研究のあり方についての研究
第3項 教師教育のあり方についての研究
おわりに
主要参考・引用文献
索引
はじめに
序章 研究の目的・方法・意義
第1節 研究の目的と方法
第1項 研究の目的
第2項 研究の方法
第2節 本研究の意義
第1項 大村研究からの意義
第2項 授業改善からの意義
第3項 教師教育からの意義
第1章 学校における授業が抱える課題と改善の道筋
第1節 学校における授業が抱える課題
第1項 今後において求められる能力と授業構造
1 学習者に求められる能力
2 求められる授業構造
第2項 求められる能力に対する現実的な問題
1 能力の二重性という問題
2 教室の中の現実的問題
第3項 学校という「装置」がもたらす問題
1 学校という「装置」
2 学校という「装置」と学習者の問題
3 学校という「装置」と教師の問題
第2節 授業改善の道筋
第1項 求められる変革
1 学校の中にある「観」の変革
2 個性化につながる個別化という考え方
第2項 授業改善への道筋
1 教師の煩悶
2 「典型」への照射
3 授業改善への道筋の提示
第2章 大村はまの国語科単元学習
第1節 大村はまのめざした世界とその背景
第1項 大村はまの教育観とその背景
1 学習者に対する視線と教えることの意味
2 大村はまの理想とする教室のイメージ
3 それらの背景となること
第2項 大村はまの教育観とそれに基づく実践の現代的価値
1 学校における授業が抱える課題との関係から捉えられる価値
2 教師の資質・能力の伸長との関係から捉えられる価値
第2節 大村はまと国語科単元学習
第1項 国語科における単元学習
1 単元学習における思想
2 展開される学習活動
3 国語科における単元学習の原理
第2項 大村はまの国語科単元学習
1 その成立
2 大村はまの国語科単元学習
第3章 大村はまの「学習の手びき」の実際と分析1―通覧―
第1節 大村はまの「学習の手びき」の実際
第1項 「学習の手びき」の整理
1 整理の方法
2 整理した「学習の手びき」一覧
第2項 「学習の手びき」の実際
1 「学習の手びき」の内容
2 「学習の手びき」の表現
3 「学習の手びき」が導く学習
第2節 通覧から見出せる「学習の手びき」の機能
第1項 「学習の手びき」の使われ方から導出される機能
1 端から丁寧に読んで使うタイプの「学習の手びき」の場合
2 眺めながらヒントとして使うタイプの「学習の手びき」の場合
3 繰り返し読んで使うタイプの「学習の手びき」の場合
第2項 学習者と指導者に対しての機能
1 学習者に対する機能
2 指導者に対する機能
第3項 通覧から導出した「学習の手びき」の特性
1 「学習の手びき」の役割
2 「学習の手びき」の特性
第4章 大村はまの「学習の手びき」の実際と分析2―詳察―
第1節 対象とする実践の選択と詳察の方法
第1項 対象とする実践
1 選択の条件
2 詳察のする対象について
第2項 詳察の方法
第2節 「学習の手びき」の詳察
第1項 単元「私たちの読書力〈図表を読む〉」の場合
1 概略
2 本授業における「学習の手びき」について
3 「学習の手びき」の考察と検証
4 「学習の手びき」に見出される工夫
第2項 「古典への入門―枕草子によって―」の場合
1 概略
2 本授業における「学習の手びき」について
3 「学習の手びき」の考察と検証
4 「学習の手びき」に見出される工夫
第3項 「楽しくつくる『旅の絵本』」の場合
1 概略
2 本授業における「学習の手びき」について
3 「学習の手びき」の考察と検証
4 「学習の手びき」に見出される工夫
第4項 詳察から導出した「学習の手びき」の特性
1 「学習の手びき」の役割
2 「学習の手びき」の特性
第5章 授業における個性化と個別化の実現に向けて
第1節 授業における個性化と個別化を実現するための「学習の手びき」
第1項 個性化と個別化について
1 実現すべき個性化と個別化の状態
2 個性化のために重要な個別化
第2項 個性化と個別化を実現する「学習の手びき」に必要なこと
1 大村はまの「学習の手びき」に示されたこと
2 個性化と個別化を実現する「学習の手びき」のあり方
第2節 個性化と個別化を実現する「学習の手びき」に至るまでの道筋
第1項 大村はまの辿った道筋
1 基盤となる教育観の醸成と学習者としての体験
2 「学習の手びき」作成までの実際のプロセス
第2項 教師が大村はまの「学習の手びき」から「典型」を得るための道筋
1 大村はまの「学習の手びき」を体験すること
2 自己の教育観と対面すること
3 教師が大村はまの「学習の手びき」から「典型」を得るための道筋
第3項 授業における個性化と個別化の実現に向けて
1 学習者からの出発の必要性
2 授業研究の場の活用による学習者理解
終章 研究のまとめ
第1節 研究の総括
第1項 学校における授業が抱える課題と改善の道筋(第1章の内容)
1 授業に存在する解決すべき課題
2 課題に対する改善の道筋
第2項 大村はまの国語科単元学習(第2章の内容)
1 大村はまの教育観と現代の教育課題との関わり
2 大村はまの国語科単元学習の内実
第3項 大村はまの「学習の手びき」の実際と分析1―通覧―(第3章の内容)
1 「学習の手びき」の整理
2 通覧から見出せる「学習の手びき」の機能と特性
第4項 大村はまの「学習の手びき」の実際と分析2―詳察―(第4章の内容)
1 学習過程を再現して考察・検証するという方法
2 詳察から見出せる「学習の手びき」の機能と特性
第5項 授業における個性化と個別化の実現(第5章の内容)
1 個性化と個別化を実現する「学習の手びき」のあり方の整理
2 教師が大村はまの「学習の手びき」から「典型」を得るための道筋
第2節 今後の課題
第1項 研究成果に基づく学校現場での解説についての研究
第2項 授業研究のあり方についての研究
第3項 教師教育のあり方についての研究
おわりに
主要参考・引用文献
索引