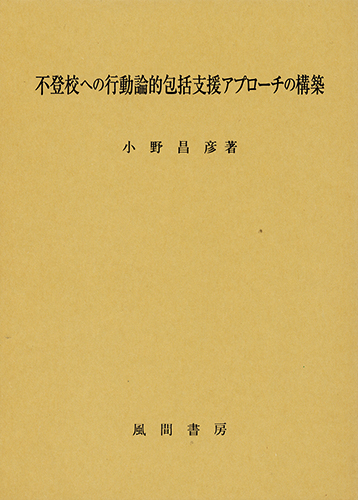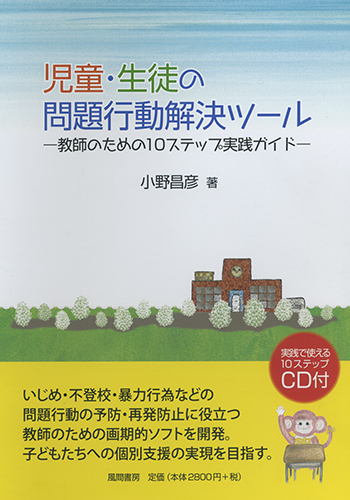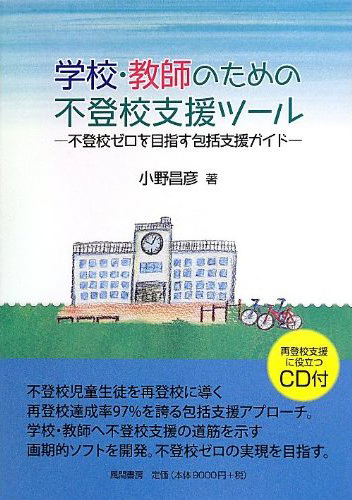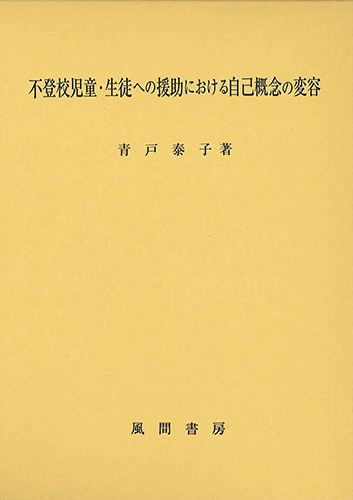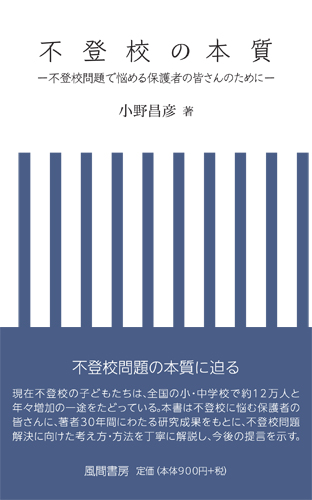
不登校の本質
不登校問題で悩める保護者の皆さんのために
定価990円(本体 900円+税)
不登校問題の本質に迫る
現在不登校の子どもたちは、全国の小・中学校で約12万人と年々増加の一途をたどっている。本書は不登校に悩む保護者の皆さんに、著者30年間にわたる研究成果をもとに、不登校問題解決に向けた考え方・方法を丁寧に解説し、今後の提言を示す。
【著者紹介】
小野 昌彦(おの まさひこ)
明治学院大学心理学部教育発達学科教授。筑波大学大学院修士課程教育学研究科修了、同大学大学院博士課程心身障害学研究科中退。奈良教育大学教育学部附属教育実践総合センター准教授、宮崎大学大学院教育学研究科教授を経て、現職。博士(障害科学:筑波大学)。2016年度筑波大学心理・発達教育相談室功労賞受賞、宮崎大学名誉教授。専門は、教育臨床、障害科学。
目次を表示
はじめに
序 不登校支援における契約の考えと嫌を嫌でなくするアプローチの未普及
1章 不登校の現状(日本2016)
1 再登校支援事例:日本教育新聞の記事より
2 学校、家庭の往復パターンの中断
3 不登校認定は曖昧である
4 学校に行く、行かないではなく問題解決が重要
5 再登校は、子どもの嫌なところにもどること、抵抗はつきもの
6 法的には、問題解決責任者は保護者
7 学校と家庭の状況に影響を受ける問題
8 文部科学省の不登校対策の問題
2章 不登校に対する対応が変化した学校と家庭
1 29年前の不登校生徒の再登校支援の光景
2 再登校準備の山場―回避は容認しないで対応法を教える―
3 再登校予定日前後のかかわり
4 29年前とは真逆の不登校支援の現状
5 アセスメントなし放置の悲劇―楽をしていては苦痛が沁みる―
6 不登校に対する学校、家庭の4タイプ
7 多様な学校、家庭が出現した背景―文部科学省通知の影響―
8 回避容認の文部科学省不登校通知による不登校児童生徒に対する教育保障機会欠如と教育の質の低下
9 学校教育法施行令未遵守と曖昧な卒業認定の容認
3章 学校、保護者のタイプの組み合わせによって決まる不登校パターン
1 16タイプの組み合わせパターンの特徴
2 子どもの不登校の4つのタイプ
3 不登校の子どもの目標
4 子どもが不登校となる要因について
5 4つの子どものタイプと学校と保護者の組み合わせの関係
6 16パターン別の再登校支援
4章 子どもの嫌を嫌でなくするアプローチについて
1 不登校の行動アセスメントとは
2 不登校をめぐる情報
3 評価方法
4 再登校以降の評価
5 行動アセスメントとしての情報統合
5章 嫌を嫌でなくするアプローチにおける再登校支援の基本的方法
1 支援関係の設定と個別支援計画の進め方
2 個別支援計画の進め方
6章 こうやって再登校した―再登校事例―
1 不登校形成プロセスと再登校・登校維持までの典型的プロセス
2 Ⅲ・B型への支援例:対人ストレスからの不安反応による不登校事例
3 Ⅳ・D型への支援例:病弱対応による中学生不登校
4 Ⅳ・A型への支援例:養育者交代による混乱のために生じた不登校
5 Ⅳ・B型への支援例:体育回避による小学生不登校
7章 契約・嫌を嫌でなくするアプローチのやり取りの実際
8章 すべての日本の子どもたちに義務教育を保障する為に必要なこと
1 子どもの再登校が困難なパターンへの対策
2 学校・保護者が非契約型、嫌を嫌のままのアプローチ型にならないために
あとがき
引用文献
序 不登校支援における契約の考えと嫌を嫌でなくするアプローチの未普及
1章 不登校の現状(日本2016)
1 再登校支援事例:日本教育新聞の記事より
2 学校、家庭の往復パターンの中断
3 不登校認定は曖昧である
4 学校に行く、行かないではなく問題解決が重要
5 再登校は、子どもの嫌なところにもどること、抵抗はつきもの
6 法的には、問題解決責任者は保護者
7 学校と家庭の状況に影響を受ける問題
8 文部科学省の不登校対策の問題
2章 不登校に対する対応が変化した学校と家庭
1 29年前の不登校生徒の再登校支援の光景
2 再登校準備の山場―回避は容認しないで対応法を教える―
3 再登校予定日前後のかかわり
4 29年前とは真逆の不登校支援の現状
5 アセスメントなし放置の悲劇―楽をしていては苦痛が沁みる―
6 不登校に対する学校、家庭の4タイプ
7 多様な学校、家庭が出現した背景―文部科学省通知の影響―
8 回避容認の文部科学省不登校通知による不登校児童生徒に対する教育保障機会欠如と教育の質の低下
9 学校教育法施行令未遵守と曖昧な卒業認定の容認
3章 学校、保護者のタイプの組み合わせによって決まる不登校パターン
1 16タイプの組み合わせパターンの特徴
2 子どもの不登校の4つのタイプ
3 不登校の子どもの目標
4 子どもが不登校となる要因について
5 4つの子どものタイプと学校と保護者の組み合わせの関係
6 16パターン別の再登校支援
4章 子どもの嫌を嫌でなくするアプローチについて
1 不登校の行動アセスメントとは
2 不登校をめぐる情報
3 評価方法
4 再登校以降の評価
5 行動アセスメントとしての情報統合
5章 嫌を嫌でなくするアプローチにおける再登校支援の基本的方法
1 支援関係の設定と個別支援計画の進め方
2 個別支援計画の進め方
6章 こうやって再登校した―再登校事例―
1 不登校形成プロセスと再登校・登校維持までの典型的プロセス
2 Ⅲ・B型への支援例:対人ストレスからの不安反応による不登校事例
3 Ⅳ・D型への支援例:病弱対応による中学生不登校
4 Ⅳ・A型への支援例:養育者交代による混乱のために生じた不登校
5 Ⅳ・B型への支援例:体育回避による小学生不登校
7章 契約・嫌を嫌でなくするアプローチのやり取りの実際
8章 すべての日本の子どもたちに義務教育を保障する為に必要なこと
1 子どもの再登校が困難なパターンへの対策
2 学校・保護者が非契約型、嫌を嫌のままのアプローチ型にならないために
あとがき
引用文献