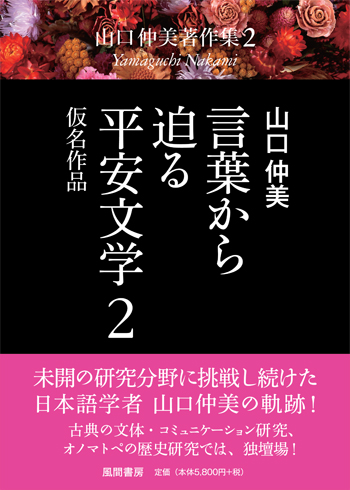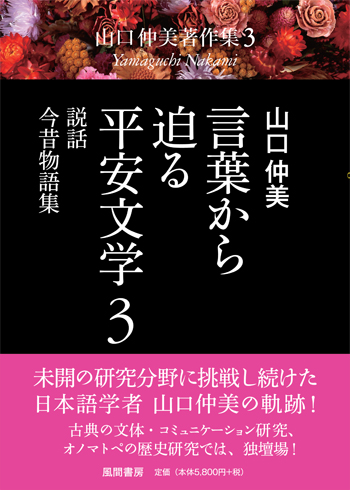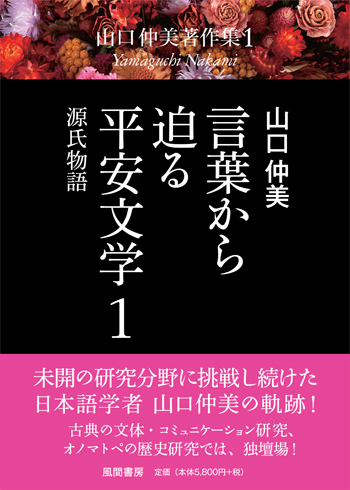
山口仲美著作集 1
言葉から迫る平安文学 1
源氏物語
定価6,380円(本体 5,800円+税)
第一巻は、言葉や文体、そしてコミュニケーションといった言語学的な
立場から、『源氏物語』のさまざまな問題を追究。三部から成る。
Ⅰ部は、「『源氏物語』男と女のコミュニケーション」。源氏物語に登場
する男と女は、どんなコミュニケーションをとっていたのか? その様相
を具体的に解明している。
Ⅱ部は、「『源氏物語』の言葉と文体」。比喩や象徴詞(=オノマトペ)や形容語などに注目して、『源氏物語』独自の問題を解明する。
Ⅲ部は、「文章・文体研究の軌跡と展望」。『言葉から迫る平安文学』1巻・2巻・3巻に共通する著者の立場を明確にしている。文章・文体研究の草創期の状態も明らかになる。
【著者略歴】
山口仲美(やまぐち なかみ)
1943年静岡県生まれ。お茶の水女子大学卒業。
東京大学大学院修士課程修了。文学博士。
現在―埼玉大学名誉教授。
専門―日本語学( 日本語史・古典の文体・オノマトペの歴史)
著書―『平安文学の文体の研究』( 明治書院、第12回金田一京助博士記念賞)、『平安朝の言葉と文体』(風間書房)、『日本語の歴史』(岩波書店、第55回日本エッセイスト・クラブ賞)、『犬は「びよ」と鳴いていた』(光文社)、『日本語の古典』(岩波書店)など多数。
2008年紫綬褒章、2016年瑞宝中綬章受章。
専門分野関係のテレビ・ラジオ番組にも多数出演。
☆☆☆メディアで紹介されました☆☆☆
2018年11月5日 秋田魁新報に紹介されました。「日本語論、硬軟織り交ぜ 山口仲美著作集発刊」
2018年11月11日 東京新聞に紹介されました。「出版情報」
2018年11月16日 週刊読書人(特集 全集・講座・シリーズ)に先生が執筆されたエッセイが掲載されました。「全集・著作集が役に立つ時 筆者が考える3つのメリット」
2018年12月26日 日本経済新聞(夕刊)にインタビュー記事が掲載されました。「日本語学者・山口仲美の著作集刊行」
2019年1月18日 週刊読書人に『言葉から迫る平安文学3 説話・今昔物語集』が紹介されました。
2019年3月9日 図書新聞(3390号) に『言葉から迫る平安文学1 源氏物語』の書評が掲載されました。
「言語学的な方法に拠る分析の数々 山口仲美の長く充実した研究人生の、豊饒なその成果」評者は浅川哲也先生(首都大学東京教授)です。
目次を表示
著作集の刊行にあたって
まえがき
I 『源氏物語』男と女のコミュニケーション
男の表現・女の表現
1 はじめに
2 男と女の会話場面
3 会話のイニシアチブをとるのは、誰か
4 男と女の発言内容
5 女は態度でもコミュニケーションをとる
6 愛の告白―男性多用表現(1)―
7 質問―男性多用表現(2)―
8 弁解・事情説明―男性多用表現(3)―
9 教え・言い聞かせ―男性多用表現(4)―
10 批評・見解―男性多用表現(5)―
11 要求―男性多用表現(6)―
12 その他の男性多用表現
13 拒否―女性多用表現(1)―
14 反論・異論―女性多用表現(2)―
15 同意・同調―女性多用表現(3)―
16 その他の女性多用表現
17 感情表出―男女共用表現―
18 おわりに
男と女の会話のダイナミクス
1 はじめに
2 光源氏と空蝉―理詰めの会話―
3 光源氏と夕顔―余韻のある会話―
4 光源氏と藤壺―究極の愛の会話―
5 光源氏と源典侍―露骨な会話―
6 光源氏と葵の上・六条御息所―傷つけ合う会話―
7 光源氏と紫の上(1)―無垢な会話―
8 光源氏と玉鬘―「下燃え」の愛の会話―
9 光源氏と紫の上(2)―諦観の会話―
10 光源氏と女三の宮―苦悩の会話―
11 夕霧と雲居雁―夫婦暄嘩の会話―
12 夕霧と落葉の宮―不器用な会話―
13 薫と大君―すれ違う会話―
14 薫・匂宮と浮舟―理性の会話と感性の会話―
15 おわりに
Ⅱ 『源氏物語』の言葉と文体
文体論の新しい課題
1 はじめに
2 直喩と隠喩
3 つくられた直喩
4 新鮮な印象
5 源氏物語以前
6 おわりに
比喩の表現論的性格と「文体論」への応用
1 はじめに
2 比喩の成立契機
3 比喩の効果
4 比喩と個性
5 分析の方法
6 古典を例にとって
7 源氏物語と宇津保物語の比喩の素材
8 源氏物語と宇津保物語の個的特性
9 おわりに
『源氏物語』の比喩表現と作者
1 はじめに
2 対象とする比喩
3 比喩の用例数
4 比喩のあらわれ方―差異点(1)―
5 技巧的な比喩―差異点(2)―
6 観念的な比喩―差異点(3)―
7 複雑な文構造―差異点(4)―
8 「花」のイメージ―差異点(5)―
9 差異点(1)の意味
10 差異点(2)(3)(4)の意味
11 差異点(5)の意味
12 同一の作者の影
13 共通性をさぐる
14 一致する比喩―共通点(1)―
15 「死」に関する比喩―共通点(2)―
16 「光」に関する比喩―共通点(3)―
17 比喩の種類と用法―共通点(4)―
18 体言性の比喩―共通点(5)―
19 個性をえがく比喩―共通点(6)―
20 鮮明なイメージ―共通点(7)―
21 適切な関係―共通点(8)―
22 共通点と作者同一人説
『源氏物語』の擬人法
1 「藤」が「なよぶ」
2 「白き花」は「笑みの眉ひらけたる」
3 「空」は「見知り顔」
4 「鹿」は「たたずみ」「愁へ顔」
5 「真木の戸口」は「月入れたる」
6 説話文学の動物たち
7 和歌の擬人法
8 新しい言葉で積極的に
9 おわりに
『源氏物語』のテクニック―破局への布石―
1 発端
2 偶然の契り
3 日撃される
4 当てこすられる
5 雷鳴とともに露見
『源氏物語』の歌語と文体
1 はじめに
2 「呉竹」の用法
3 「泡」の用法
4 「玉水」の用法
5 「きりぎりす」の用法
6 おわりに
『源氏物語』の象徴詞の独自用法
1 はじめに
2 人物造型のために
3 人柄の描写
4 前期物語では
5 後期物語では
6 黒髪の描写
7 物語文学では
8 泣哭・落涙の描写
9 全体のなかで位置づけられる語
『源氏物語』の並列形容語
1 はじめに
2 並列形容語の概念
3 並列形容語の用例
4 異質な語の並列(1)
5 異質な語の並列(2)
6 同質な語の並列
7 源氏物語の並列形容語の特色
8 異質な語の並列にみる特色
9 情意語の並列にみる特色
10 相反する情意語の並列
11 異なる立場からする情意語の並列
12 宇津保物語の情意語の並列
13 状態語の並列にみる特色
14 おわりに
『源氏物語』の女性語
1 はじめに
2 女性語はどこに
3 平安時代では
4 「ここ」と「まろ」
5 「まろ」は光源氏、「ここ」は薫
6 女性特有語を求めて
7 男性特有語
8 「まま」は、女性語
9 おわりに
『源氏物語』の雅語・卑俗語
1 はじめに
2 典型的な雅語
3 散文部分に出現する歌語
4 高く張った和歌の調子を
5 美的な情景を演出
6 人物造型に
7 重層効果を狙って
8 他作品では
9 卑俗語とは
10 大夫の監の言葉
11 近江の君と常陸の介の言葉
12 洗練されていない人物の造型
13 おわりに
『源氏物語』の漢語
1 はじめに
2 漢語の割合
3 地の文で活躍する漢語
4 男性だけが用いる漢語
5 僧侶だけが用いる漢語
6 女性が用いる漢語
7 特殊な女性が使う漢語
8 おわりに
「『つぶつぶと』肥えたまへる人」考
1 肉体のふくよかさを表す「つぶつぶと」
2 紫式部の造語か
3 その根拠(1)
4 その根拠(2)
「『つと』抱く」考
1 意味不明
2 辞書の説明
3 第三の意味がある
「そら」をめぐる恋愛情緒表現
1 はじめに
2 辞書では、すべて「うわのそら」
3 「空なり」は、心が空虚な状態ではない
4 「心も空に」なるのは、男性
5 他作品では
6 「上の空なり」は、女の気持
7 「上の空」は、より所なく心細い
8 『源氏物語』が初出
9 「中空なり」は、男と女の気持
10 「中空」は、どっちつかずの状態
11 三語の違い
『源氏物語』と『細雪』の表現
1 はじめに
2 人物造型
3 揺れる心
4 他者への思いやり
5 世間の眼
6 身分意識
7 死の場面
8 おわりに
Ⅲ 文章・文体研究の軌跡と展望
文章・文体研究の軌跡
1 はじめに
2 文体論
3 文章論
4 表現論
5 文章作法論
文章・文体研究参考文献
1 文章論
2 文体論
3 表現論
4 文章作法
5 文章文体関係の研究史・展望・文献目録・特集号・講座
昭和49・50年における国語学界の展望―文章・文体―
1 はじめに
2 単行本(個人の論文集)
3 文体関係論文(1)―文体一般―
4 文体関係論文(2)―個性面に関する研究―
5 文体関係論文(3)―類型面に関する研究―
6 文章・表現関係論文
7 史的研究の論文
8 おわりに
文体研究の回顧と展望
1 文体研究の危機
2 文章心理学の誕生
3 統計学の導入
4 直観による文体把握
5 文学的文体論の隆盛
6 語学的文体論の隆盛
7 文学的文体論と語学的文体論の対立
8 活性化の道を求めて(1)
9 活性化の道を求めて(2)
10 活性化の道を求めて(3)
既発表論文・著書との関係