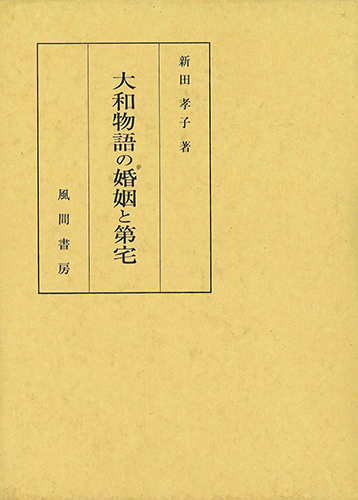
大和物語の婚姻と第宅
定価19,800円(本体 18,000円+税)
当代の婚姻と第宅の関係に視点を定め人的構成の側面から大和物語の文芸性を明らかにする。女性名称・北家所領の第宅に関する緻密な考証・成立論を含む全4篇。
【著者略歴】
新田孝子(にった たかこ)
昭和7年 宮城県に生まれる
昭和38年 東北大学大学院文学研究科
博士課程期間満了単位取得退学
平成元年 文学博士(東北大学)
平成8年 東北大学附属図書館調査研究室
研究員(文学部助手)停年退官
【主な著書】
『多武峰少将物語の様式』(風間書房,昭和62年)
白井たつ子と共著『蜻蛉日記の風姿』(風間書房,平成8年)
【著者略歴】
新田孝子(にった たかこ)
昭和7年 宮城県に生まれる
昭和38年 東北大学大学院文学研究科
博士課程期間満了単位取得退学
平成元年 文学博士(東北大学)
平成8年 東北大学附属図書館調査研究室
研究員(文学部助手)停年退官
【主な著書】
『多武峰少将物語の様式』(風間書房,昭和62年)
白井たつ子と共著『蜻蛉日記の風姿』(風間書房,平成8年)
目次を表示
緒言
起篇 『大和物語』の婚姻と第宅
序章 問題のありか
第一章 「亭子院のわか宮」(一一段)
―醍醐皇女について―
一 韶子内親王と源清蔭
二 「東の方」の居宅
三 本院第西の対屋に据えられた時平室
四 高経女「兵衛」
五 韶子内親王の斎院退下
六 醍醐皇女一覧
七 源清蔭と「亭子院」
第二章 「桂のみこ」(二〇段)
―光孝皇女について―
一 「桂のみこ」の婚姻
二 「桂ノ宮」第は〈西六条院〉
三 后腹の光孝皇女
四 「仲野親王六条亭」
五 敦慶親王の私第
六 元良親王と「かつらの宮」
第三章 「刑部の君」(四八段)
―宇多皇女について―
一 刑部卿のむすめ
二 宇多皇女一覧
三 第五女で第六(’’)内親王(’’’)の成子内親王
四 「女五のみこ」の所伝
五 敦固親王の私第
六 源湛の女子〈内蔵の更衣〉
七 「閑院の五のみこ」再考
第四章 「京極御息所」(六一段)
―法皇御所について―
一 時平のむすめ褒子
二 「河原院」への移御
三 宇多上皇の御所
四 「東院」と「東洞院」
五 「河原院」と「宇多院」
六 行明親王の小八条第
七 敦実親王と「宇多院」
八 「河原院」と〈六条御息所〉
九 褒子の落飾
第五章 「南院のいま君」(一〇八段)
―是忠親王王女について―
一 源宗于の女子
二 源宗于の素姓
三 源宗于女と〈閑院大君〉の関係
四 是忠親王の女婿
五 是忠親王の王女姣子女王
六 「南院式部卿の親王の女」
七 貞保親王と是忠親王
八 「南院内親王」敦子の存在
九 二つの南院第
第六章 「染殿の内侍」(一五九段)
―上毛野朝臣滋子―
一 従来の所伝
二 染殿第との関係
三 上毛野朝臣滋子の存在
四 上毛野朝臣氏と染殿第
五 源能有室の藤原滋子
六 「菅原の君」の没年
七 染殿第の伝領者
八 「染殿の内侍」の周辺伝説
終章 皇統転換期の縮図
一 両皇統の婚姻の二元性
二 初段の語るもの
承篇 『大和物語』の女性名称
序章 問題のありか
第一章 「若狭の御」(一五段)
一 陽成御在所としての「釣殿院」
二 「陽成院」第における御息所
三 〈武蔵の御〉との混同
四 武蔵守の候補者
五 遠景としての班子女王
第二章 「陽成院のすけの御」(一六段)
一 〈主殿助のむすめの御〉
二 小野絃風について
三 敦慶親王第としての「亭子院」
四 「すけの御」
第三章 「閑院の御」(四六段)
一 〈閑院第のむすめである御〉
二 幻の〈基経女陽成御息所〉
三 貞元親王室の基経女
四 平貞文との関係
五 閑院第を里第とする女官
第四章 「五条の御」(六〇段)
一 山蔭女一覧
二 在原業平女との契縁
三 清貫母と在原文子
四 在原滋春の事跡
五 「伊勢の守」の候補者
六 「五条の御」仮系図
七 五条尚侍満子
八 〈山蔭姪〉〈智泉女〉か
九 在衡の五条第
第五章 「伊予の御」(六五段)
一 伊予介連永の女子
二 是忠親王王子一覧
第六章 〈少輔の御〉(一一一段)
一 兼輔の対象の「少将の内侍」
二 〈橘公平〉という架空の人物
三 源公平の存在
四 大后穏子に侍仕する女官たち
第七章 「檜垣の御」(一二六段)と「弁の御息所」(一六五段)
一 「槍垣の御」
二 「弁の御息所」
三 「御」の意義
四 「君」「御」の視点と「家の女」「宮仕へ女房」の視点
終章 『大和物語』の「――の御」の定義
一 「御」と「御達」
二 「御達」と「御」たち
三 「――の御」の「御」
四 「御息所」の下位概念としての「御」
転篇 『大和物語』の史的環境―北家所領の第宅
序章 問題のありか
第一章 「東三条」と呼ばれる第宅
一 東京三条第の略形
二 良房と東三条第の史料
三 宇多上皇・班子女王の遷御した「東三条院」
四 元利親王第の「東三条家」
五 皇后昌子内親王の移御した「東三条」
第二章 堀河第と閑院第とについて
一 源兼忠の生母基経女
二 仲平女暁子と明子の居宅
三 致忠所領の閑院第
四 元平親王と閑院第
五 元良親王と閑院第の三姉妹
六 元平親王と「開院君」との婚姻の場
七 后妃の里第への遷幸
第三章 染殿第と南院第とについて
一 「せかゐの君」
二 「元利親王家」の「清和院」
三 「染殿尚侍」考
四 良房の白河第
五 基経の栗田山荘=北白河第
六 済時の「小白河第」と公任の「北白河第」
第四章 「東一条」と呼ばれる第宅
一 「外記日記」の記事
二 忠平第の「東家」
三 皇后安子の東院第
四 「東院公主」簡子の存在
五 「小一条伊尹朝臣宅東一条」
六 忠平の小一条第
七 良房の東一条第
八 〈小一条内大臣高藤〉
九 〈小一条〉の指呼する第宅
十 四坊三町・四町にわたる東院第
終章 史的環境の輪廓
一 良房第としての〈染殿第・東三条第〉
二 忠平第としての〈染殿第〉と元利親王第としての
〈東三条南院第〉
三 兼家第としての〈東三条第〉
結篇 『大和物語』の成立
第一章 研究の課題と方法
一 『大和物語』の文芸性
二 個別章段と全体構成
三 「事件年次」と「記述年次」
四 「事件年次」の史実性
五 本書の研究の方法
六 「二条の御息所」について
第二章 女官名称の原則
―「一条の君」の場合―
一 問題のありか
二 条坊名と后妃の称号
三 女蔵人「一条の君」と貞平親王王女「一条の君」
四 〈陽成院〉と「一条の君」
五 内裏の女官「女蔵人一条」
六 承香殿の「としこ」と「亭子院」との接点
七 褒子に侍仕する「一条の君」
八 伊勢と「一条の君」の交遊
九 「一条の君」の婚姻
十 「陽成院」に「一条の君」
第三章 『大和物語』と『後撰集』との乖離
―「監の命婦」考―
一 問題のありか
二 『大和物語』の「監の命婦」
三 『後撰集』の「藤原かつみの命婦」
四 〈左近将監恒興のむすめ〉
五 『後撰集』の「命婦清子」
六 〈平安直女〉と〈共政つま肥前〉
七 堤第の伝領―〈在原行平の鴨河辺第〉
八 堤第の伝領―〈朝忠の中河第〉
九 在原方子
十 『大和物語』と『後撰集』との間
第四章 『大和物語』の成立
一 問題のありか
二 『大和物語』の二部構成についての三説
三 『大和物語』の俯瞰図的考察―『古今集』歌章段
四 『大和物語』の俯瞰図的考察―『拾遺集』歌章段
五 第五十八段に登場する平兼盛
六 平兼盛の陸奥下向と源重之との関係
七 総論『大和物語』と三代集の関係―『拾遺集』
八 総論『大和物語』と三代集の関係―『後撰集』
九 総論『大和物語』と三代集の関係―『古今集』
十 事実の文芸
本書収載論文について
索引
(一)人名索引 (二)第宅索引 (三)章段索引 (四)論文索引 (五)和歌索引
附表
三代集所伝一覧表
清和―円融朝四省卿親王表
あとがき
起篇 『大和物語』の婚姻と第宅
序章 問題のありか
第一章 「亭子院のわか宮」(一一段)
―醍醐皇女について―
一 韶子内親王と源清蔭
二 「東の方」の居宅
三 本院第西の対屋に据えられた時平室
四 高経女「兵衛」
五 韶子内親王の斎院退下
六 醍醐皇女一覧
七 源清蔭と「亭子院」
第二章 「桂のみこ」(二〇段)
―光孝皇女について―
一 「桂のみこ」の婚姻
二 「桂ノ宮」第は〈西六条院〉
三 后腹の光孝皇女
四 「仲野親王六条亭」
五 敦慶親王の私第
六 元良親王と「かつらの宮」
第三章 「刑部の君」(四八段)
―宇多皇女について―
一 刑部卿のむすめ
二 宇多皇女一覧
三 第五女で第六(’’)内親王(’’’)の成子内親王
四 「女五のみこ」の所伝
五 敦固親王の私第
六 源湛の女子〈内蔵の更衣〉
七 「閑院の五のみこ」再考
第四章 「京極御息所」(六一段)
―法皇御所について―
一 時平のむすめ褒子
二 「河原院」への移御
三 宇多上皇の御所
四 「東院」と「東洞院」
五 「河原院」と「宇多院」
六 行明親王の小八条第
七 敦実親王と「宇多院」
八 「河原院」と〈六条御息所〉
九 褒子の落飾
第五章 「南院のいま君」(一〇八段)
―是忠親王王女について―
一 源宗于の女子
二 源宗于の素姓
三 源宗于女と〈閑院大君〉の関係
四 是忠親王の女婿
五 是忠親王の王女姣子女王
六 「南院式部卿の親王の女」
七 貞保親王と是忠親王
八 「南院内親王」敦子の存在
九 二つの南院第
第六章 「染殿の内侍」(一五九段)
―上毛野朝臣滋子―
一 従来の所伝
二 染殿第との関係
三 上毛野朝臣滋子の存在
四 上毛野朝臣氏と染殿第
五 源能有室の藤原滋子
六 「菅原の君」の没年
七 染殿第の伝領者
八 「染殿の内侍」の周辺伝説
終章 皇統転換期の縮図
一 両皇統の婚姻の二元性
二 初段の語るもの
承篇 『大和物語』の女性名称
序章 問題のありか
第一章 「若狭の御」(一五段)
一 陽成御在所としての「釣殿院」
二 「陽成院」第における御息所
三 〈武蔵の御〉との混同
四 武蔵守の候補者
五 遠景としての班子女王
第二章 「陽成院のすけの御」(一六段)
一 〈主殿助のむすめの御〉
二 小野絃風について
三 敦慶親王第としての「亭子院」
四 「すけの御」
第三章 「閑院の御」(四六段)
一 〈閑院第のむすめである御〉
二 幻の〈基経女陽成御息所〉
三 貞元親王室の基経女
四 平貞文との関係
五 閑院第を里第とする女官
第四章 「五条の御」(六〇段)
一 山蔭女一覧
二 在原業平女との契縁
三 清貫母と在原文子
四 在原滋春の事跡
五 「伊勢の守」の候補者
六 「五条の御」仮系図
七 五条尚侍満子
八 〈山蔭姪〉〈智泉女〉か
九 在衡の五条第
第五章 「伊予の御」(六五段)
一 伊予介連永の女子
二 是忠親王王子一覧
第六章 〈少輔の御〉(一一一段)
一 兼輔の対象の「少将の内侍」
二 〈橘公平〉という架空の人物
三 源公平の存在
四 大后穏子に侍仕する女官たち
第七章 「檜垣の御」(一二六段)と「弁の御息所」(一六五段)
一 「槍垣の御」
二 「弁の御息所」
三 「御」の意義
四 「君」「御」の視点と「家の女」「宮仕へ女房」の視点
終章 『大和物語』の「――の御」の定義
一 「御」と「御達」
二 「御達」と「御」たち
三 「――の御」の「御」
四 「御息所」の下位概念としての「御」
転篇 『大和物語』の史的環境―北家所領の第宅
序章 問題のありか
第一章 「東三条」と呼ばれる第宅
一 東京三条第の略形
二 良房と東三条第の史料
三 宇多上皇・班子女王の遷御した「東三条院」
四 元利親王第の「東三条家」
五 皇后昌子内親王の移御した「東三条」
第二章 堀河第と閑院第とについて
一 源兼忠の生母基経女
二 仲平女暁子と明子の居宅
三 致忠所領の閑院第
四 元平親王と閑院第
五 元良親王と閑院第の三姉妹
六 元平親王と「開院君」との婚姻の場
七 后妃の里第への遷幸
第三章 染殿第と南院第とについて
一 「せかゐの君」
二 「元利親王家」の「清和院」
三 「染殿尚侍」考
四 良房の白河第
五 基経の栗田山荘=北白河第
六 済時の「小白河第」と公任の「北白河第」
第四章 「東一条」と呼ばれる第宅
一 「外記日記」の記事
二 忠平第の「東家」
三 皇后安子の東院第
四 「東院公主」簡子の存在
五 「小一条伊尹朝臣宅東一条」
六 忠平の小一条第
七 良房の東一条第
八 〈小一条内大臣高藤〉
九 〈小一条〉の指呼する第宅
十 四坊三町・四町にわたる東院第
終章 史的環境の輪廓
一 良房第としての〈染殿第・東三条第〉
二 忠平第としての〈染殿第〉と元利親王第としての
〈東三条南院第〉
三 兼家第としての〈東三条第〉
結篇 『大和物語』の成立
第一章 研究の課題と方法
一 『大和物語』の文芸性
二 個別章段と全体構成
三 「事件年次」と「記述年次」
四 「事件年次」の史実性
五 本書の研究の方法
六 「二条の御息所」について
第二章 女官名称の原則
―「一条の君」の場合―
一 問題のありか
二 条坊名と后妃の称号
三 女蔵人「一条の君」と貞平親王王女「一条の君」
四 〈陽成院〉と「一条の君」
五 内裏の女官「女蔵人一条」
六 承香殿の「としこ」と「亭子院」との接点
七 褒子に侍仕する「一条の君」
八 伊勢と「一条の君」の交遊
九 「一条の君」の婚姻
十 「陽成院」に「一条の君」
第三章 『大和物語』と『後撰集』との乖離
―「監の命婦」考―
一 問題のありか
二 『大和物語』の「監の命婦」
三 『後撰集』の「藤原かつみの命婦」
四 〈左近将監恒興のむすめ〉
五 『後撰集』の「命婦清子」
六 〈平安直女〉と〈共政つま肥前〉
七 堤第の伝領―〈在原行平の鴨河辺第〉
八 堤第の伝領―〈朝忠の中河第〉
九 在原方子
十 『大和物語』と『後撰集』との間
第四章 『大和物語』の成立
一 問題のありか
二 『大和物語』の二部構成についての三説
三 『大和物語』の俯瞰図的考察―『古今集』歌章段
四 『大和物語』の俯瞰図的考察―『拾遺集』歌章段
五 第五十八段に登場する平兼盛
六 平兼盛の陸奥下向と源重之との関係
七 総論『大和物語』と三代集の関係―『拾遺集』
八 総論『大和物語』と三代集の関係―『後撰集』
九 総論『大和物語』と三代集の関係―『古今集』
十 事実の文芸
本書収載論文について
索引
(一)人名索引 (二)第宅索引 (三)章段索引 (四)論文索引 (五)和歌索引
附表
三代集所伝一覧表
清和―円融朝四省卿親王表
あとがき
