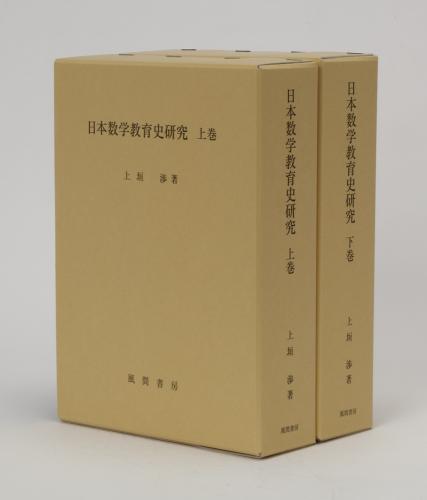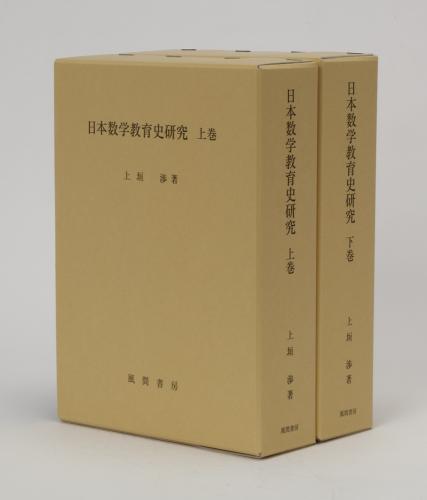
日本数学教育史研究 上巻
定価22,000円(本体 20,000円+税)
本書は、幕末・明治期から昭和30年代までの約90年間にわたる我が国の初等中等数学教育の歴史を総合的に論述した学術書の「上巻」。「第Ⅰ部 草創期の数学教育」、「第Ⅱ部 盛創期の数学教育」から成る。
【著者紹介】
上垣 渉(うえがき わたる)
1948年 兵庫県生まれ
1972年 東京学芸大学大学院修士課程修了
現在 三重大学名誉教授 全国珠算教育連盟学術顧問
(数学教育協議会副委員長、三重大学教育学部長、日本数学教育史
学会会長を歴任)
主な著書
『日本数学教育史』(編著、発行/亀書房、発売/日本評論社、2010年)
『数と図形の歴史70話』(共著、日本評論社、2010年)
『中学校 和算でつくるおもしろ数学授業』(編著、明治図書、2013年)
『『尋常小学算術』と多田北烏』(共著、風間書房、2014年)
『数学史の視点から分析する中学校数学重要教材研究事典』[数と式編、図形編](単著、明治図書、2014年)
『はじめて読む数学の歴史』(単著、角川ソフィア文庫、2016年)
目次を表示
序文
凡例
第Ⅰ部 草創期の数学教育
第1章 学制期の数学教育(1)
1.和算と洋算の語義に関する考察
和算と洋算の今日的語義/学制期における和算と洋算
2.学制の制定
3.学制及び学制草案における算術の規定
学制における規定/学制草案における規定/「洋法を用う」が付加された
時期
4.和算全廃・洋算専用の方針が採用された時期
小倉説の修正/洋算専用が決定された時期
5.明治7年文部省布達に関する新解釈 -日本算術と日本算をめぐって-
洋算専用の方針の変更/明治6年,7年文部省布達の再検討/日本算の解釈
について/用語「洋算」の新解釈/小学教則改定とのかかわり/小学教科
用図書からの視点
6.学制及び小学教則が公布されるまでの算術書の特徴
高久守静の『数学書』/『筆算訓蒙』と『洋算早学』/神田孝平の『数学
教授本』/『洋算独学』,『洋算例題』,『数学教授書』
7.文部省小学教則と師範学校小学教則
文部省小学教則の改定と師範学校小学教則の創定/2つの小学教則の比較
と各府県の状況
8.学制制定・洋算専用の時代背景
第2章 学制期の数学教育(2)
1.学制期における文部省の教科書政策
2.文部省編輯寮から師範学校編輯局へ
3.学制期における算術教科書とその意義
学制期の算術教科書/学制期における算術教科書の意義
4.『小学算術書』の種本に関する再考証
小倉による「コルバーン説」の修正/コルバーンの算術書が種本とされた
根拠/『小学算術書』の特徴/『小学算術書』と“Colburn’s Intellectual
Arithmetic”との比較/ロビンソンの算術書/デヴィスの算術書/『小学算
術書』の真の種本/『小学算術書』の優れた特徴
5.学制期における算術教授法
小学校の校舎と施設・設備/師範学校小学教則にもとづく算術教授法
6.学制期における幾何教育
第3章 教育令期の初等数学教育
1.教育令の公布とその改正
マレーの学監考案日本教育法と田中文部大輔の日本教育令/教育令制定か
ら改正,再改正へ
2.小学校教則綱領の布達とその意義
3.珠算教科書の増加
4.各府県の小学校教則
5.明治10年代の算術教科書の特徴
三千題流算術/開発主義教授法/明治10年代の筆算教科書
6.教育令期における幾何教育
7.教育令から学校令へ
第4章 西洋数学の輸入
1.中国経由による西洋数学の輸入
第1段階の輸入/第2段階の輸入
2.西洋人の直接的な教授等による輸入
長崎海軍伝習所の設立/第1期~第3期の伝習生/第1次の伝習所教育/
第2次の伝習所教育/伝習所のその後
3.開成所及び静岡学問所と沼津兵学校
開成所の柳河春三と神田孝平/開成所から静岡学問所・沼津兵学校へ/
沼津兵学校について/静岡学問所について
4.『数学啓蒙』,『筆算訓蒙』,『筆算題叢』及び西洋算術書の比較
『数学啓蒙』,『筆算訓蒙』,『筆算題叢』の関係/『筆算題叢』編纂に使用
された西洋算術書
5.和算家による西洋数学の普及
6.異色の数学者・伊藤慎蔵
第5章 明治前期における中学校の数学教育
1.中学教則略及び外国教師にて教授する中学教則の公布
2.各府県における数学教育(学制期)
3.中学校教則大綱の制定
4.大阪中学校の数学教育
算術教科書について/代数教科書について/幾何教科書について/三角法
教科書について
5.各府県における数学教育(教育令期)
各府県の教科課程/田中の算術教科書について/田中の代数教科書につい
て/田中の幾何教科書について/田中の三角法教科書について/柴田清亮
の『幾何学』/上野継光の『幾何精要』/赤木周行の『常用曲線』
6. 近藤真琴と攻玉塾
7. 幾何教育における形式陶冶的意義・目的の出現
第6章 幕末・明治初期における数学訳語・数学記号の様相
1.幕末・明治初期における蘭和及び英和辞書
幕末期における蘭和及び英和辞書/『英和対訳袖珍辞書』とその後裔
2.数学記号一覧表について
数学記号一覧表の原本/数学記号一覧表の比較検討
3.幕末から明治初期にかけての数学訳語
4.英和辞書等に係る年表
第7章 明治期における数学訳語統一の動き
1.東京数学会社の創立
2.数学訳語会の設立
3.数学訳語会における訳語例
4.“Algebra”,“Mathematics”,“Arithmetic”の訳語をめぐって
“Algebra”の訳語について/“Mathematics”の訳語について/“Arithmetic”
の訳語について
5.数学訳語会の3つの特徴
6.藤沢利喜太郎の数学辞書
7.駒野政和の数学辞書
8.宮本藤吉の数学辞書
9.海軍教育本部編纂の数学訳語集
10.長沢亀之助の数学辞書
第8章 明治検定期における初等数学教育
1.小学校令公布と小学校制度の確立
再改正教育令と小学校令の連続性/新定小学校令の公布
2.小学校の学科及其程度から小学校教則大綱へ
小学校の学科及其程度とその追加事項/小学校教則大綱の公布
3.小学校令改正と小学校令施行規則の公布
4.教科書検定制度の発足
教科用図書検定規則について/小学校図書審査委員会について/検定済教
科書の発行状況と明治検定期の時期区分
5.検定前期・小学校算術教科書の特徴
6.検定中期・小学校算術教科書の特徴
7.検定後期・小学校算術教科書の特徴
8.検定期における小学校幾何教育
9.明治中期における珠算復興運動
第9章 菊池大麓における教育と数学
1.菊池大麓の略歴
2.菊池における教育の目的
教育目的の道徳的側面/教育目的の知力的側面
3.『初等幾何学教科書』について
4.比例論について
5.数学書における左起横書き
6.言文一致文体への志向
7.数学に関する菊池の諸著作
第10章 明治中期における中等数学教育
1.中等諸学校に関する諸規程
中学校令の公布/高等女学校令の公布/師範学校令の公布
2.明治中期における中等諸学校の検定済教科書
中学校の算術教科書/中学校の代数教科書/中学校の幾何教科書/中学校
の三角法教科書/師範学校及び高等女学校の数学教科書/明治32年の中学
校・師範学校で使用された教科書に関する資料
3. 中学校における幾何初歩について
4. 高等女学校・師範学校における幾何初歩について
5.欧化主義の担い手 -菊池大麓と寺尾寿-
6.理論流儀算術の台頭
7.理論流儀算術の敗退
寺尾と藤沢の算術教科書の概要比較/算術教授の具体的内容について/理
論流儀算術敗退の5つの要因
第11章 藤沢利喜太郎の数学教育論
1.藤沢利喜太郎と日本の数学
2.『算術条目及教授法』と『数学教授法講義筆記』
3.算術教育の目的
4.直観主義算術への批判
5.三千題流算術への批判
6.数の多方的所分(四則併進主義)への批判
7.理論流儀算術への批判
8.数学教育からの量の放逐と名数の採用
量の放逐/名数の採用
9.数え主義による算術教授法
10.小数先行と3桁区切りの採用
小数先行の採用/3桁区切りの採用
11.単位換算と四則応用問題について
12.比と比例について
比の定義,比の値,割合/比例について
13.藤沢の幾何教育観
日本における幾何学の来歴/比例論について/算術と幾何について
14.代数学教科書の変遷
15.藤沢の『初等代数学教科書』
第Ⅱ部 盛創期の数学教育
第12章 黒表紙教科書の編纂・概要と特徴
1.黒表紙教科書の発足
2.『尋常小学算術書』及び『高等小学算術書』の編纂区分
3.『尋常小学算術書』の編纂要旨
4.数え主義について
5.暗算と筆算について
6.乗法九九について
逆九九の起こり/制限九九から総九九へ/新宮恒次郎の九九論
7.小数と分数について
8.四則応用問題について
9.比例及び歩合算について
第13章 文部省内の数学教科書担当官たち
1.文部省内における教科書担当部署の変遷
2.検定期における教科書担当官
3.黒表紙教科書の担当官
4.緑表紙及び水色表紙教科書の担当官
5.墨塗り及び暫定教科書の担当官
6.白表紙教科書の担当官
7.『小学生のさんすう第四学年用』について
8.小括
第14章 高等小学校の数学教育
1.高等小学校制度の変遷
2.第一期版~第五期版について
3.分数について
4.比例と歩合算との関係
5.歩合算について
6.比例について
7.求積について
8.四則応用問題について
9.負数と一次方程式について
10.二次方程式について
11.函数(凾数)について
12.級数について
13.幾何教材について
14.三角形の合同について
第15章 中等学校数学教育の定型化
1.中学校令施行規則の制定
尋常中学校の数学科教授内容の削減/尋常中学校教授細目から中学校令施
行規則へ
2.中学校令施行規則に関する菊池・沢柳の論争
3.中学校数学教授要目の制定
4.中学校数学教授要目の意義と限界
5.明治44年の中学校数学教授要目の改正
6.初期の高等女学校の数学教育
7.高等女学校の発展
8.実科高等女学校の新設
9.高等女学校の数学教育の定型化
10.高等女学校数学教授要目の改定
11.師範教育令の公布及び臨時教員養成所の設置
12.師範学校規程の制定と師範学校体制の確立
13.師範学校数学教授要目の制定
第16章 数学教科調査報告について
1.数学教科調査委員会と調査報告書一覧
概括的英文報告の序文より/15種類の数学教科調査報告について
2.小学校数学教科調査報告について
義務教育年限の延長,男女同級教授の問題/数理思想への言及/四則併進
と四則分進について/暗算,筆算,珠算/事実問題への言及
3.中学校数学教科調査報告について
中学校入学者および卒業者の状況/数学科の目的/東京高等師範学校附属
中学校数学教授要目及び編纂要旨/算術及び代数について/幾何について
4.高等女学校数学教科調査報告について
5.師範学校数学教科調査報告について
師範学校(男子)数学教科調査報告/女子師範学校数学教科調査報告
6.中等学校数学科教員養成に関する調査報告について
中等学校数学科教員の養成/高等師範学校の調査報告/第三臨時教員養成
所の調査報告/女子高等師範学校の調査報告
第17章 明治後期における中等学校数学教科書の様相
1.中等学校数学教科書に関する使用教科図書表
2.中学校及び師範学校数学教科書の様相
算術教科書について/代数教科書について/平面幾何教科書について/立
体幾何教科書について/平面三角法教科書について
3.高等女学校及び女子師範学校数学教科書の様相
算術教科書について/代数教科書について/幾何教科書について
4.高木貞治の数学教育論
高木貞治と林鶴一/数学の実用性について/数学の本質,目的について/
数学用語の問題/数学に対する興味の問題/『新式算術講義』について
第18章 数学教育改造運動の勃興
1.数学教育改造運動に関する解説書
2.ペリーの数学教育改造論
ペリー講演以前のイギリスの状況/ペリーの講演
3.ムーアの数学教育改造論
ムーア講演以前のアメリカの状況/ムーアの講演
4.クラインの数学教育改造論
クライン論文・講演以前のドイツの状況/クラインの論文及び講演/メラ
ンの要目について
5.数学教育改造運動の主張の要点
6.メランの要目
第19章 日本における数学教育改造運動の受容
1.井口在屋によるペリー運動の敷衍
2.日本における改造運動受容の時期区分
3.第1期改造運動受容の特徴
4.黒田稔の幾何教育論
黒田稔の略歴/黒田の幾何学教科書
5.数学科教員協議会の開催
開催に至るまで/協議題に関する討議/文部省諮問題に対する答申/講演
について
6.日本中等教育数学会の設立
7.大正13年教授要目改定の中止 -改造運動受容の最初の挫折-
第20章 算術改造運動の源流
1.谷本富の新教育学と欧州の新学校運動
2.谷本教育学の時期区分と主要著作
3.谷本富の自学輔導
4.谷本新教授法の影響を受けた実践家たち
岡千賀衛の自学輔導新教授法/及川平治の分団式動的教育法/樋口長市の
自学教育論/木下竹次,清水甚吾と谷本富,岡千賀衛の係わり/手塚岸衛,
香取良範と谷本富
5.大正前期における算術改造運動の2つの源流
6.我が国における新学校の設立
明治末期の新学校:済美,成蹊,帝国/大正期の新学校:成城小学校など
7.小括
第21章 算術改造運動の高揚
1.算術改造運動の時期区分
2.黎明期における算術改造運動の特徴
算術教授の目的と児童の生活との係わり/算術教授における実験的・実測
的取扱い
3.佐藤武の算術教育論
算術教授の目的について/数概念の教授法について/教授法その他の研究
課題について/発生的算術教育法/算術教育の集大成
4.高揚期における算術改造運動の特徴
算術の生活化をめぐって/実験・実測の定着/数理への着眼
5.函数及びグラフについて
6.大正末期~昭和初期における算術教育の様相
『教育研究』誌,『学校教育』誌より/『東京市学校調査(第二輯)』より
/算術教育の様相
第22章 小倉金之助の数学教育論
1.小倉金之助の伝記的著作
2.科学的精神の養成
3.形式陶冶の問題
4.数学の大衆化
5.数学教育史の研究
6.在野の数学教育評論家
7.自然主義文学からの影響
8.小倉による数学教育改造運動に対する評価
第23章 日本における数学教育改造運動の終焉
1.佐藤良一郎の『初等数学教育の根本的考察』
2.第2期改造運動受容の特徴
3.小倉金之助編輯の数学教育名著叢書
4.国元東九郎の直観幾何教授
女子学習院の教科課程表/トロイトラインの『幾何学的直観教授』/国元
東九郎の直観幾何教授/トロイトラインと国元の比較
5.昭和6年中学校教授要目の改定前夜
6.昭和6年の中学校数学教授要目改定
7.我が国における数学教育改造運動の挫折
数学教育史関係論文等一覧
書名索引(和書)
書名索引(洋書)
人名索引
あとがき
凡例
第Ⅰ部 草創期の数学教育
第1章 学制期の数学教育(1)
1.和算と洋算の語義に関する考察
和算と洋算の今日的語義/学制期における和算と洋算
2.学制の制定
3.学制及び学制草案における算術の規定
学制における規定/学制草案における規定/「洋法を用う」が付加された
時期
4.和算全廃・洋算専用の方針が採用された時期
小倉説の修正/洋算専用が決定された時期
5.明治7年文部省布達に関する新解釈 -日本算術と日本算をめぐって-
洋算専用の方針の変更/明治6年,7年文部省布達の再検討/日本算の解釈
について/用語「洋算」の新解釈/小学教則改定とのかかわり/小学教科
用図書からの視点
6.学制及び小学教則が公布されるまでの算術書の特徴
高久守静の『数学書』/『筆算訓蒙』と『洋算早学』/神田孝平の『数学
教授本』/『洋算独学』,『洋算例題』,『数学教授書』
7.文部省小学教則と師範学校小学教則
文部省小学教則の改定と師範学校小学教則の創定/2つの小学教則の比較
と各府県の状況
8.学制制定・洋算専用の時代背景
第2章 学制期の数学教育(2)
1.学制期における文部省の教科書政策
2.文部省編輯寮から師範学校編輯局へ
3.学制期における算術教科書とその意義
学制期の算術教科書/学制期における算術教科書の意義
4.『小学算術書』の種本に関する再考証
小倉による「コルバーン説」の修正/コルバーンの算術書が種本とされた
根拠/『小学算術書』の特徴/『小学算術書』と“Colburn’s Intellectual
Arithmetic”との比較/ロビンソンの算術書/デヴィスの算術書/『小学算
術書』の真の種本/『小学算術書』の優れた特徴
5.学制期における算術教授法
小学校の校舎と施設・設備/師範学校小学教則にもとづく算術教授法
6.学制期における幾何教育
第3章 教育令期の初等数学教育
1.教育令の公布とその改正
マレーの学監考案日本教育法と田中文部大輔の日本教育令/教育令制定か
ら改正,再改正へ
2.小学校教則綱領の布達とその意義
3.珠算教科書の増加
4.各府県の小学校教則
5.明治10年代の算術教科書の特徴
三千題流算術/開発主義教授法/明治10年代の筆算教科書
6.教育令期における幾何教育
7.教育令から学校令へ
第4章 西洋数学の輸入
1.中国経由による西洋数学の輸入
第1段階の輸入/第2段階の輸入
2.西洋人の直接的な教授等による輸入
長崎海軍伝習所の設立/第1期~第3期の伝習生/第1次の伝習所教育/
第2次の伝習所教育/伝習所のその後
3.開成所及び静岡学問所と沼津兵学校
開成所の柳河春三と神田孝平/開成所から静岡学問所・沼津兵学校へ/
沼津兵学校について/静岡学問所について
4.『数学啓蒙』,『筆算訓蒙』,『筆算題叢』及び西洋算術書の比較
『数学啓蒙』,『筆算訓蒙』,『筆算題叢』の関係/『筆算題叢』編纂に使用
された西洋算術書
5.和算家による西洋数学の普及
6.異色の数学者・伊藤慎蔵
第5章 明治前期における中学校の数学教育
1.中学教則略及び外国教師にて教授する中学教則の公布
2.各府県における数学教育(学制期)
3.中学校教則大綱の制定
4.大阪中学校の数学教育
算術教科書について/代数教科書について/幾何教科書について/三角法
教科書について
5.各府県における数学教育(教育令期)
各府県の教科課程/田中の算術教科書について/田中の代数教科書につい
て/田中の幾何教科書について/田中の三角法教科書について/柴田清亮
の『幾何学』/上野継光の『幾何精要』/赤木周行の『常用曲線』
6. 近藤真琴と攻玉塾
7. 幾何教育における形式陶冶的意義・目的の出現
第6章 幕末・明治初期における数学訳語・数学記号の様相
1.幕末・明治初期における蘭和及び英和辞書
幕末期における蘭和及び英和辞書/『英和対訳袖珍辞書』とその後裔
2.数学記号一覧表について
数学記号一覧表の原本/数学記号一覧表の比較検討
3.幕末から明治初期にかけての数学訳語
4.英和辞書等に係る年表
第7章 明治期における数学訳語統一の動き
1.東京数学会社の創立
2.数学訳語会の設立
3.数学訳語会における訳語例
4.“Algebra”,“Mathematics”,“Arithmetic”の訳語をめぐって
“Algebra”の訳語について/“Mathematics”の訳語について/“Arithmetic”
の訳語について
5.数学訳語会の3つの特徴
6.藤沢利喜太郎の数学辞書
7.駒野政和の数学辞書
8.宮本藤吉の数学辞書
9.海軍教育本部編纂の数学訳語集
10.長沢亀之助の数学辞書
第8章 明治検定期における初等数学教育
1.小学校令公布と小学校制度の確立
再改正教育令と小学校令の連続性/新定小学校令の公布
2.小学校の学科及其程度から小学校教則大綱へ
小学校の学科及其程度とその追加事項/小学校教則大綱の公布
3.小学校令改正と小学校令施行規則の公布
4.教科書検定制度の発足
教科用図書検定規則について/小学校図書審査委員会について/検定済教
科書の発行状況と明治検定期の時期区分
5.検定前期・小学校算術教科書の特徴
6.検定中期・小学校算術教科書の特徴
7.検定後期・小学校算術教科書の特徴
8.検定期における小学校幾何教育
9.明治中期における珠算復興運動
第9章 菊池大麓における教育と数学
1.菊池大麓の略歴
2.菊池における教育の目的
教育目的の道徳的側面/教育目的の知力的側面
3.『初等幾何学教科書』について
4.比例論について
5.数学書における左起横書き
6.言文一致文体への志向
7.数学に関する菊池の諸著作
第10章 明治中期における中等数学教育
1.中等諸学校に関する諸規程
中学校令の公布/高等女学校令の公布/師範学校令の公布
2.明治中期における中等諸学校の検定済教科書
中学校の算術教科書/中学校の代数教科書/中学校の幾何教科書/中学校
の三角法教科書/師範学校及び高等女学校の数学教科書/明治32年の中学
校・師範学校で使用された教科書に関する資料
3. 中学校における幾何初歩について
4. 高等女学校・師範学校における幾何初歩について
5.欧化主義の担い手 -菊池大麓と寺尾寿-
6.理論流儀算術の台頭
7.理論流儀算術の敗退
寺尾と藤沢の算術教科書の概要比較/算術教授の具体的内容について/理
論流儀算術敗退の5つの要因
第11章 藤沢利喜太郎の数学教育論
1.藤沢利喜太郎と日本の数学
2.『算術条目及教授法』と『数学教授法講義筆記』
3.算術教育の目的
4.直観主義算術への批判
5.三千題流算術への批判
6.数の多方的所分(四則併進主義)への批判
7.理論流儀算術への批判
8.数学教育からの量の放逐と名数の採用
量の放逐/名数の採用
9.数え主義による算術教授法
10.小数先行と3桁区切りの採用
小数先行の採用/3桁区切りの採用
11.単位換算と四則応用問題について
12.比と比例について
比の定義,比の値,割合/比例について
13.藤沢の幾何教育観
日本における幾何学の来歴/比例論について/算術と幾何について
14.代数学教科書の変遷
15.藤沢の『初等代数学教科書』
第Ⅱ部 盛創期の数学教育
第12章 黒表紙教科書の編纂・概要と特徴
1.黒表紙教科書の発足
2.『尋常小学算術書』及び『高等小学算術書』の編纂区分
3.『尋常小学算術書』の編纂要旨
4.数え主義について
5.暗算と筆算について
6.乗法九九について
逆九九の起こり/制限九九から総九九へ/新宮恒次郎の九九論
7.小数と分数について
8.四則応用問題について
9.比例及び歩合算について
第13章 文部省内の数学教科書担当官たち
1.文部省内における教科書担当部署の変遷
2.検定期における教科書担当官
3.黒表紙教科書の担当官
4.緑表紙及び水色表紙教科書の担当官
5.墨塗り及び暫定教科書の担当官
6.白表紙教科書の担当官
7.『小学生のさんすう第四学年用』について
8.小括
第14章 高等小学校の数学教育
1.高等小学校制度の変遷
2.第一期版~第五期版について
3.分数について
4.比例と歩合算との関係
5.歩合算について
6.比例について
7.求積について
8.四則応用問題について
9.負数と一次方程式について
10.二次方程式について
11.函数(凾数)について
12.級数について
13.幾何教材について
14.三角形の合同について
第15章 中等学校数学教育の定型化
1.中学校令施行規則の制定
尋常中学校の数学科教授内容の削減/尋常中学校教授細目から中学校令施
行規則へ
2.中学校令施行規則に関する菊池・沢柳の論争
3.中学校数学教授要目の制定
4.中学校数学教授要目の意義と限界
5.明治44年の中学校数学教授要目の改正
6.初期の高等女学校の数学教育
7.高等女学校の発展
8.実科高等女学校の新設
9.高等女学校の数学教育の定型化
10.高等女学校数学教授要目の改定
11.師範教育令の公布及び臨時教員養成所の設置
12.師範学校規程の制定と師範学校体制の確立
13.師範学校数学教授要目の制定
第16章 数学教科調査報告について
1.数学教科調査委員会と調査報告書一覧
概括的英文報告の序文より/15種類の数学教科調査報告について
2.小学校数学教科調査報告について
義務教育年限の延長,男女同級教授の問題/数理思想への言及/四則併進
と四則分進について/暗算,筆算,珠算/事実問題への言及
3.中学校数学教科調査報告について
中学校入学者および卒業者の状況/数学科の目的/東京高等師範学校附属
中学校数学教授要目及び編纂要旨/算術及び代数について/幾何について
4.高等女学校数学教科調査報告について
5.師範学校数学教科調査報告について
師範学校(男子)数学教科調査報告/女子師範学校数学教科調査報告
6.中等学校数学科教員養成に関する調査報告について
中等学校数学科教員の養成/高等師範学校の調査報告/第三臨時教員養成
所の調査報告/女子高等師範学校の調査報告
第17章 明治後期における中等学校数学教科書の様相
1.中等学校数学教科書に関する使用教科図書表
2.中学校及び師範学校数学教科書の様相
算術教科書について/代数教科書について/平面幾何教科書について/立
体幾何教科書について/平面三角法教科書について
3.高等女学校及び女子師範学校数学教科書の様相
算術教科書について/代数教科書について/幾何教科書について
4.高木貞治の数学教育論
高木貞治と林鶴一/数学の実用性について/数学の本質,目的について/
数学用語の問題/数学に対する興味の問題/『新式算術講義』について
第18章 数学教育改造運動の勃興
1.数学教育改造運動に関する解説書
2.ペリーの数学教育改造論
ペリー講演以前のイギリスの状況/ペリーの講演
3.ムーアの数学教育改造論
ムーア講演以前のアメリカの状況/ムーアの講演
4.クラインの数学教育改造論
クライン論文・講演以前のドイツの状況/クラインの論文及び講演/メラ
ンの要目について
5.数学教育改造運動の主張の要点
6.メランの要目
第19章 日本における数学教育改造運動の受容
1.井口在屋によるペリー運動の敷衍
2.日本における改造運動受容の時期区分
3.第1期改造運動受容の特徴
4.黒田稔の幾何教育論
黒田稔の略歴/黒田の幾何学教科書
5.数学科教員協議会の開催
開催に至るまで/協議題に関する討議/文部省諮問題に対する答申/講演
について
6.日本中等教育数学会の設立
7.大正13年教授要目改定の中止 -改造運動受容の最初の挫折-
第20章 算術改造運動の源流
1.谷本富の新教育学と欧州の新学校運動
2.谷本教育学の時期区分と主要著作
3.谷本富の自学輔導
4.谷本新教授法の影響を受けた実践家たち
岡千賀衛の自学輔導新教授法/及川平治の分団式動的教育法/樋口長市の
自学教育論/木下竹次,清水甚吾と谷本富,岡千賀衛の係わり/手塚岸衛,
香取良範と谷本富
5.大正前期における算術改造運動の2つの源流
6.我が国における新学校の設立
明治末期の新学校:済美,成蹊,帝国/大正期の新学校:成城小学校など
7.小括
第21章 算術改造運動の高揚
1.算術改造運動の時期区分
2.黎明期における算術改造運動の特徴
算術教授の目的と児童の生活との係わり/算術教授における実験的・実測
的取扱い
3.佐藤武の算術教育論
算術教授の目的について/数概念の教授法について/教授法その他の研究
課題について/発生的算術教育法/算術教育の集大成
4.高揚期における算術改造運動の特徴
算術の生活化をめぐって/実験・実測の定着/数理への着眼
5.函数及びグラフについて
6.大正末期~昭和初期における算術教育の様相
『教育研究』誌,『学校教育』誌より/『東京市学校調査(第二輯)』より
/算術教育の様相
第22章 小倉金之助の数学教育論
1.小倉金之助の伝記的著作
2.科学的精神の養成
3.形式陶冶の問題
4.数学の大衆化
5.数学教育史の研究
6.在野の数学教育評論家
7.自然主義文学からの影響
8.小倉による数学教育改造運動に対する評価
第23章 日本における数学教育改造運動の終焉
1.佐藤良一郎の『初等数学教育の根本的考察』
2.第2期改造運動受容の特徴
3.小倉金之助編輯の数学教育名著叢書
4.国元東九郎の直観幾何教授
女子学習院の教科課程表/トロイトラインの『幾何学的直観教授』/国元
東九郎の直観幾何教授/トロイトラインと国元の比較
5.昭和6年中学校教授要目の改定前夜
6.昭和6年の中学校数学教授要目改定
7.我が国における数学教育改造運動の挫折
数学教育史関係論文等一覧
書名索引(和書)
書名索引(洋書)
人名索引
あとがき