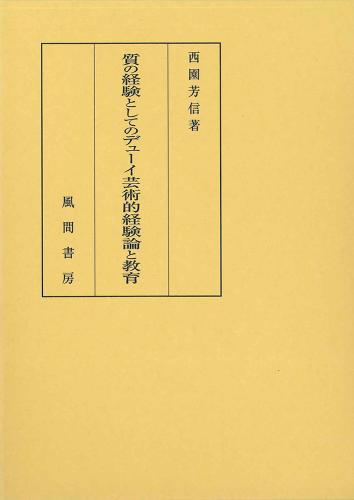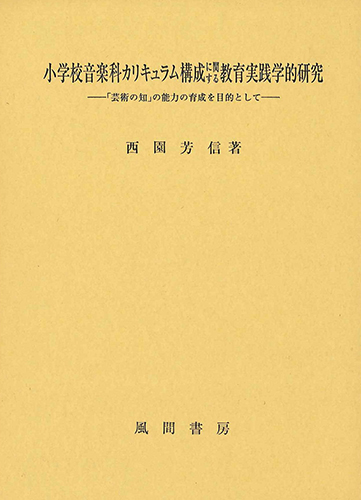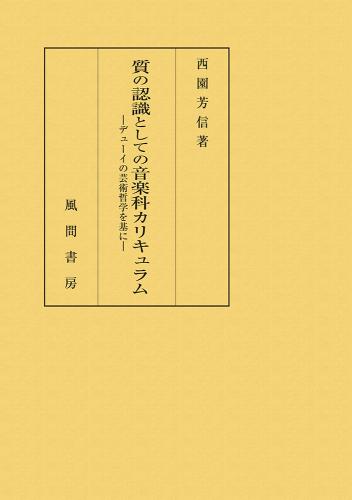
質の認識としての音楽科カリキュラム
デューイの芸術哲学を基に
定価5,500円(本体 5,000円+税)
デューイの芸術哲学を基に質の認識によって感性を育成する音楽科カリキュラムを開発。AI時代の音楽教育の在り方を論究する。
【著者略歴】
西園芳信(にしぞの よしのぶ)1948年生まれ
経暦 1973年武蔵野音楽大学大学院音楽研究科修士課程修了。1976年島根大学教育学部助手、同大学講師、1981年東京学芸大学講師、同大学助教授を経て、1995年鳴門教育大学教授。1996年兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科(博士課程)教授(併任)。2002年博士(学校教育学)(兵庫教育大学)。2010年鳴門教育大学理事・副学長(教育研究担当)。2016年鳴門教育大学名誉教授。2016年聖徳大学兼任講師。
専門 音楽教育学、教科内容学、教育実践学
著書
『音楽科カリキュラムの研究―原理と展開―』(音楽之友社、1984)『音楽科の学習指導と評価』(日本書籍、1987)『小学校音楽科カリキュラム構成に関する教育実践学的研究―「芸術の知」の能力の育成を目的として―』(風間書房、2005)『質の経験としてのデューイ芸術的経験論と教育』(風間書房、2015)
共著・編著
『総合的な学習と音楽表現』(黎明書房、2000)『教育実践学を中核とする教員養成コア・カリキュラム―鳴門プラン―』(暁教育図書、2006)『教育実践から捉える教員養成のための教科内容学研究』(風間書房、2009)『教科内容学に基づく教員養成のための教科内容構成の開発』(あいり出版、2021)『デューイの思想形成と経験の成長過程―デューイ没後70周年記念論集』(北樹出版、2022)
学会・社会活動
日本学校音楽教育実践学会、日本デューイ学会、日本教科内容学会、日本イギリス理想主義学会。中央教育審議会専門委員、第3期、第4期(芸術)など。
目次を表示
まえがき
序章 伝統的な音楽教育の理論とカリキュラム
一 日本の戦後の教育課程の特徴
二 伝統的な音楽教育の理論とカリキュラム
徳性の育成としての音楽教育
情操教育としての音楽教育
生活の成長としての音楽教育
美的教育としての音楽教育
三 質の認識としての音楽教育の理論とカリキュラムの要点
四 なぜデューイの芸術論を選択したのか
序章のまとめ
第一章 質の認識としての音楽教育の基礎哲学―デューイ芸術論の特徴―
一 芸術的経験の源―美的質―
二 日常経験と反省的経験
「経験」とは
知的問題解決と芸術的問題解決
三 日常経験から芸術的経験への発展
四 芸術的経験としての高みを作るのは何か
自然と精神の融合をつくるリズム
想像力(imagination)による経験の統合
素材を芸術的経験として凝集する感情の働き
物質と精神の融合による美的経験
五 デューイ芸術論は一元論哲学の反映
第一章のまとめ
第二章 質の認識としての音楽教育の理論
一 芸術表現の資源は自然の「感覚的質」
二 音楽は音を媒体に形式と内容によって生成
三 「生成の原理」
四 音楽科の教科内容
五 カリキュラム構成
六 「生成の原理」による音楽科の学習方法
七 音楽学習における感受の対象は「質」
第二章のまとめ
第三章 質の認識としての音楽科カリキュラム
一 音楽の教育的価値
二 音楽科教育の目標
表現や鑑賞の音楽経験
音楽の諸要素や質を知覚・感受し表現や批評文を生成する
質を認識し感性を育成する
三 質の認識としての音楽科カリキュラム
カリキュラム構成における指導内容の範囲
カリキュラム構成における指導内容の発展性
四 カリキュラムの展開
表現と鑑賞の活動が美的経験になるには
鑑賞活動における批評文指導の理論と実践
五 質の認識としての音楽科カリキュラムの事例
「生成を原理とする音楽カリキュラム」
平成二〇年「中学校学習指導要領音楽」の特徴
第三章のまとめ
第四章 学力育成に結びつく教員養成の音楽科の教育内容
一 教員養成における教科専門の問題
教科専門の教育内容と学校の教科内容との乖離
音楽科の教員養成の課題
二 教科内容学の観点からの教科専門音楽科の捉え直し
芸術(音楽)の認識論的定義
芸術(音楽)の教科内容構成の原理
音楽科の教科内容構成の柱
音楽科の教科内容構成の具体(概念・技能)
三 教員養成における音楽科の教育内容の計画
音楽科の教育内容の計画
小学校教員養成教科専門「音楽」の指導計画
四 小学校教員養成における教科専門「音楽」の展開
鑑賞の指導
器楽(ピアノ)の指導
第四章のまとめ
第五章 専門教育における音楽の指導内容―教科内容の四側面からの分析―
一 レナード・バーンスタインの『ヤングピープルズ・コンサート』における鑑賞教育の指導内容
各側面の指導内容
諸側面の関連性
二 アンドラーシュ・シフとミシェル・ベロフの『スーパーピアノレッスン』における音楽の指導内容
三 ヴァイオリニスト、ダニエル・ゲーデの『奇跡のレッスン』における音楽の指導内容
第五章のまとめ
第六章 AI時代において学校の音楽科教育に期待される能力
一 AI時代における感性育成の重要性
二 音楽による感性の育成
三 音楽的な見方・考え方の育成
四 教科横断型授業やSTEAM教育授業における感性能力の重要性と役割
第六章のまとめ
終章 本書で提案する内容の要旨
資料
参考文献
あとがき