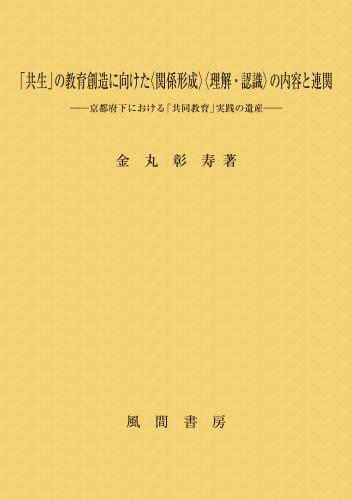
「共生」の教育創造に向けた〈関係形成〉〈理解・認識〉の内容と連関
京都府下における「共同教育」実践の遺産
定価8,800円(本体 8,000円+税)
インクルーシブ教育における〈関係形成〉〈理解・認識〉の意義と課題を踏まえて、1970-80年代の京都府下で行われた「共同教育」実践の創出と展開を整理・分析。「共生社会」づくりに貢献する教育の創造に向けて示唆を得る。
【著者略歴】
金丸 彰寿(かなまる あきとし)
1990年生まれ。
神戸大学大学院人間発達環境学研究科博士課程後期課程修了。博士(教育学)。
現在、神戸松蔭女子学院大学教育学部教育学科 准教授。
主要著書
『青年期発達障害者の自立を支えるセルフアドボカシーの理論と実践―『合理的配慮』時代をたくましく生きるために』金子書房、2016年(分担執筆)。
『人権としての特別支援教育』文理閣、2022年(分担執筆)。
主要論文
「青年の発達要求に基づく『共同教育』の創造と展開:1972―81年における京都府立与謝の海養護学校と京都府立加悦谷高等学校の実践に着目して」大学評価学会年報『現代社会と大学評価』第14号、2019年。
「京都府北部における『共同教育』の実践的・歴史的意義:〈関係形成〉〈理解・認識〉の分析枠組みを用いて」『神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要』第15巻第1号、2021年。
目次を表示
序章 課題・対象・方法
1. 問題の所在と本研究の視点
(1)問題意識:「共生」の教育を探究すること
(2)研究課題:「共同教育」の遺産の意義と限界
(3)本研究の視点:〈関係形成〉〈理解・認識〉という枠組み
2. 先行研究の検討
(1)「共同教育」における〈関係形成〉〈理解・認識〉
(2)「交流教育」「交流及び共同学習」における〈関係形成〉〈理解・認識〉
(3)インクルーシブ教育、「共生教育」における〈関係形成〉〈理解・認識〉
3. 本研究の目的、対象及び方法
(1)目的と対象:京都府下における「共同教育」実践の創出と展開(1971-88年)
(2)課題と方法:第1水準(総論レベル)及び第2水準(各論レベル「障害」・学校教育階梯)に則した〈関係形成〉〈理解・認識〉の内容と連関
(3)用語の整理
4. 本研究の構成
第1章 「交流教育」「交流及び共同学習」における〈関係形成〉〈理解・認識〉の内容と連関:学習指導要領上の位置付けとその変遷
1. 第Ⅰ期:特殊教育諸学校学習指導要領への「交流教育」の位置付け期(1971・72/79年)
(1)「交流」経験を通した〈関係形成〉
(2)「好ましい人間関係」による「理解」
2. 第Ⅱ期:通常学校学習指導要領への「交流教育」の位置付け期(1989/98・99年)
(1)「理解と認識を深める絶好の機会」としての「交流教育」
(2)〈関係形成〉と〈理解・認識〉の位置付け
3. 第Ⅲ期:「交流及び共同学習」への移行期(2008・09/2017・18年)
(1)「交流教育」から「交流及び共同学習」への用語変更にみる〈関係形成〉〈理解・認識〉
(2)インクルーシブ教育システム下の「交流及び共同教育」における〈関係形成〉〈理解・認識〉
4. 「交流教育」から「交流及び共同学習」への用語変更(2004-07年)
(1)特別支援教育特別委員会(2004-05年)における論議
(2)教育課程部会特別支援教育専門部会(2006-07年)における論議
5. 小括:単方向の矢印構造を有する〈関係形成〉〈理解・認識〉及び「共同教育」実践研究の要請
(1)〈関係形成〉〈理解・認識〉
(2)教育課程上の位置付け
(3)「共同教育」実践研究の要請
第2章 舞鶴地域の実践における〈関係形成〉〈理解・認識〉:盲ろう分校と高野小学校及び城北中学校の「共同教育」
1. 第Ⅰ期「誕生と創造期」(1971-75年):低学年・中学年・高学年の実践的区分
(1)高学年(5-6年生)実践における「対等平等な立場」
(2)低学年(1-2年生)実践における「認識の変革」
(3)中学年(3-4年生)実践における〈関係形成〉〈理解・認識〉
2. 第Ⅱ期「『9歳の壁』の導入期」(1976-81年):「認識過程」の提示
(1)1976年「認識過程」における〈関係形成〉〈理解・認識〉
(2)1979年「認識過程」における〈関係形成〉〈理解・認識〉:「9歳の壁」の導入
(3)1981年「認識過程」における〈関係形成〉〈理解・認識〉
3. 第Ⅲ期「深化期」(1982-88年度):「9歳の壁」導入後の実践
(1)低学年実践における〈関係形成〉〈理解・認識〉
(2)中学年実践における〈関係形成〉〈理解・認識〉
(3)高学年実践における〈関係形成〉〈理解・認識〉
(4)「9歳の壁」を超えた思春期における〈関係形成〉〈理解・認識〉:盲ろう分校と城北中の事例
4. 小括:「障害者問題」への連帯を築く方向性のもとでの〈関係形成〉〈理解・認識〉
(1)〈関係形成〉〈理解・認識〉
(2)教育課程上の位置付け
第3章 与謝地域の実践における〈関係形成〉〈理解・認識〉:与謝の海養護学校と加悦谷高校の「共同教育」
1. 第Ⅰ期「誕生と創造期」(1972-76年):青年期の発達要求への着眼
(1)「高校生春季討論集会」における「新しい課題意識」
(2)「合同文化祭」における「共同教育」
(3)「合同文化祭」における「友情と連帯の輪」の位置付け
2. 第Ⅱ期「深化期」(1977-80年):青年期の発達要求の追求
(1)「友情と連帯の輪」と「障害者問題」
(2)「合同文化祭」と「合同学習会」における〈関係形成〉〈理解・認識〉
3. 第Ⅲ期「開花期」(1981-88年):青年期の発達要求の組織化
(1)1981年度文化祭における〈関係形成〉〈理解・認識〉
(2)1982年度以降の実践における〈関係形成〉〈理解・認識〉
4. 小括:「人権」の問題として広がりと深まりを遂げていく〈関係形成〉〈理解・認識〉
(1)〈関係形成〉〈理解・認識〉
(2)教育課程上の位置付け
第4章 乙訓地域の実践における〈関係形成〉〈理解・認識〉:通常学校内の「『発達・障害』学習」
1. 第0期:「『『発達・障害』学習』の前史」(1973-82年)
(1)乙訓地域の「共同教育」実践における〈関係形成〉〈理解・認識〉
(2)〈関係形成〉〈理解・認識〉からみた「共同教育」実践の課題
2. 第Ⅰ期:「『『発達・障害』学習』の教材作成過程」(1982-86年)
(1)〈理解・認識〉における「発達と障害」の位置付け
(2)スライド教材「発達と障害のはなし」における〈理解・認識〉
3. 第Ⅱ期:『通常学級のカリキュラム案作成過程』(1986-87年)
(1)教材とカリキュラム案における〈理解・認識〉の位置付け
(2)小学校6ヵ年に応じたカリキュラム案における〈関係形成〉〈理解・認識〉
4. 第Ⅲ期:「『『発達・障害』学習』における学年別実践事例」(1986-90年)
(1)4年生の事例
(2)5-6年生の事例
5. 小括:「発達」的な「共感」の世界と「発達・障害」との往還を通した〈関係形成〉〈理解・認識〉
(1)〈関係形成〉〈理解・認識〉
(2)教育課程上の位置付け
終章 「共生」の教育の創造に向けた〈関係形成〉〈理解・認識〉の内容と連関:京都府下における「共同教育」実践の遺産
1. 京都府北部における「共同教育」を通した〈関係形成〉〈理解・認識〉の発展的な螺旋構造
(1)総括:舞鶴・与謝地域の実践における発展的な螺旋構造
(2)発展的な螺旋構造の意義:「交流教育」から「交流及び共同学習」への転換
2. 京都府南部における「『発達・障害』学習」の総括と限界
(1)総括:乙訓地域の実践における発展的な螺旋構造
(2)限界:「発達・障害」の歴史的・実践的な課題
3. 「共生」の教育の創造に向けて①:〈関係形成〉〈理解・認識〉の意義と課題
(1)「障害」以外を対象にする「共生」の教育への有効性:スウェーデンにおける「共生」のカリキュラムを対象に
(2)不可分な連関構造を有する〈関係形成〉〈理解・認識〉:福祉教育を対象に
4. 「共生」の教育の創造に向けて②:教育課程の内容と配列
(1)「同じ」と「違う」を行き交う相互関係からの揺さぶり
(2)「9歳の節」及び思春期・青年期の発達的な見通し
5. 本研究の示唆
(1)実践上の示唆
(2)研究上の示唆
(3)政策上の示唆
6. 残された課題
(1)「共生」の教育の具体化に向けた実践的研究
(2)京都府下における「共同教育」実践からみる子どもの発達的変容の検討
(3)京都府下における「共同教育」実践運動の隆盛と衰退の要因解明
(4)〈関係形成〉〈理解・認識〉からみる「協働」の概念検討
(5)〈関係形成〉〈理解・認識〉にもとづく教育的統合・包摂に係る教育史研究
(6)〈関係形成〉〈理解・認識〉の概念的検討
(7)世界のインクルーシブ教育及び「共生」の教育との架橋
補論 与謝地域の障害者福祉における〈関係形成〉〈理解・認識〉:よさのうみ福祉会の実践
1. よさのうみ福祉会の歴史と理念
(1)よさのうみ福祉会の歴史①:与謝の海の学校づくり運動
(2)よさのうみ福祉会の歴史②:共同作業所づくり運動
(3)よさのうみ福祉会の理念と運営
2. よさのうみ福祉会の特徴①:作業所・施設を事例に
(1)仕事を通した自分づくり:みねやま作業所の実践
(2)地域における連帯:障害者福祉センター夢織りの郷の実践
3. よさのうみ福祉会の特徴②:地域づくり
(1)リフレかやの里の経営実践
(2)やすらの里における「共生」実践
4. 結びにかえて:「発達要求の地域的組織化」を目指す〈関係形成〉〈理解・認識〉
文献
初出一覧
あとがき
索引
