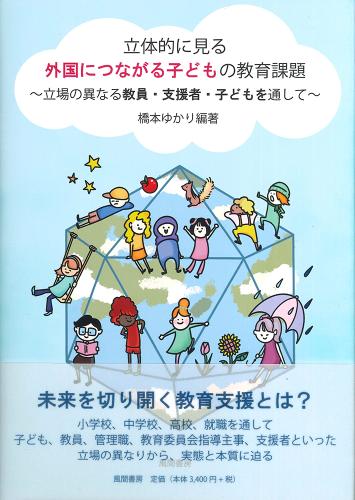
立体的に見る外国につながる子どもの教育課題
立場の異なる教員・支援者・子どもを通して
定価3,740円(本体 3,400円+税)
外国につながる子どもが学校現場で増加している現状で、日本語教育、国際教育の運営、保護者との連携など、立場の異なる教員・支援者が遭遇している課題を記述し、将来に向けた取り組みを提案する。
【執筆者紹介】
橋本ゆかり(はしもと ゆかり)
横浜国立大学教育学部・同大学院教育学研究科、教授。東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(横浜国立大学配置)博士後期課程主指導教員。お茶の水女子大学大学院博士後期課程修了、博士(人文科学)。
吉田ミシェリ恵子(よしだ みしぇり けいこ)
横浜市教育委員会日本語支援拠点施設鶴見ひまわりにて日本語講師。小学校の時ブラジルから来日。横浜国立大学大学院教育学研究科修士課程修了。修士課程在学中、在日ブラジル人向けのバイリンガル学習支援事業(オンライン)を立ち上げ、全国の散在地域に住む小学生・中学生に向け教科学習講師を務め、現在に至る。
窪津 宏美(くぼつ ひろみ)
韓国国立釜山大学日語日文学科客員教授。東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士後期課程(横浜国立大学配置)修了、博士(教育学)。横浜市立小学校にて教諭、主幹教諭として20年勤務し、学級担任の他、国際教室を担当。名古屋大学言語教育センター非常勤講師を経て、現職。
山近 佐知子(やまちか さちこ)
神奈川県教育委員会教育指導員・横浜国立大学教育学部非常勤講師。横浜国立大学大学院教育学研究科修士課程在学中。横浜国立大学教育学部卒業後、公立小学校教諭、神奈川県教育委員会指導主事、神奈川県立総合教育センター研修指導主事、公立小学校教頭、校長を経て、2020年定年退職後、現職。
宮澤 千澄(みやざわ ちずみ)
横浜市日本語支援拠点施設都筑ひまわり校長。横浜国立大学大学院教育学研究科修士課程在学中。横浜市立鶴見中学校国際教室担当教員の後、横浜市教育委員会指導主事、横浜市立飯田北いちょう小学校校長。定年退職後、東京学芸大学教職大学院で特命教授を経て、現職。
重山 陽子(しげやま ようこ)
高等学校英語・日本語・中国語講師。横浜国立大学大学院教育学研究科修士課程在学中。慶應義塾大学文学部卒業。大学卒業後、精密機械メーカー勤務。退職後、教員免許取得。高校の英語講師となるが、外国につながる生徒との出会いを契機に日本語教育を学び、現職。
今村 桜子(いまむら えいこ)
帝京大学日本語教育センター非常勤講師。東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士後期課程(横浜国立大学配置)在学中。1994年から地域日本語教室支援員。技能実習生向け企業内日本語研修業務、日本語学校勤務を経て、現職。
上法 顕子(じょうほう あきこ)
民間企業にて日本語学習e-learningや企業向け日本語研修の企画・運営業務を担当。上智大学文学部卒業後、JICA日系青年海外協力隊としてブラジル・サンパウロの日系コミュニティで継承日本語教育に従事。帰国後、横浜国立大学大学院教育学研究科修士課程進学。在学中、横浜市の小学校の国際教室や地域日本語教室で学習支援ボランティアとして活動。修了後、現職。
目次を表示
はじめに
【教員養成の立場から】
第1章 外国につながる子どもの問題を本質から支える教育
~理論からの探求~(橋本 ゆかり)
はじめに~マイノリティを支える教育を目指して~
1.外国につながる子どもの背景~歴史的背景~
2.外国につながる子どもの抱える問題~理論的解釈~
3.教育的アプローチ~言語と認知の発達~
4.学校文化と学校教育の構造の問い直し
おわりに~先にあるものを見据えて~
【外国につながる子どもの立場から】
第2章 外国につながりのある児童生徒だった私の経験
~当事者の考える日本語指導~(吉田ミシェリ恵子)
はじめに~日本語指導を必要とする経験~
1.直面した困難 その1~家族に対する帰属意識~
2.直面した困難 その2~孤独、いじめ、不登校、受験の壁~
3.日本人でもブラジル人でもない~複文化で育った経験と自己形成過程~
4.今できること~ブラジル人保護者への情報発信~
おわりに~支援者や教員に求められるもの~
【小学校国際教室担当主任、在籍学級担任教員の立場から】
第3章 エンパワーメントによる「多文化共生」への挑戦
~就学初期から始める協働の実践から~(窪津 宏美)
はじめに~多文化背景の子どもたちとの出会い~
1.多様化する児童の背景
2.日本語教育を学ぶことで見えてきたこと
3.学校教員と支援者のチーム力
4.「多文化共生」を持続可能にするエンパワーメント
おわりに~教育の可能性の模索~
【小学校管理職の立場から】
第4章 「グローバル社会に対応できる力」を育む学校作り
~「国際教室の立ち上げ」と「多文化共生の意識作り」の取組を通して~(山近 佐知子)
はじめに~校長として取り組んできたこと~
1.神奈川県の地域性
2.「国際教室」のない学校への校長としての着任
3.国際教室の立ち上げ
4.多文化共生の意識作り~管理職としての工夫~
5.二つの取組から分かったこと~長期的な展望を持って臨む~
おわりに~「持続可能な社会の創り手の育成」に向けて~
【中学校教員、小学校管理職、教育委員会指導主事の立場から】
第5章 多文化共生の学校作りのために
~国際教室の子どもたちと出会って~(宮沢 千澄)
はじめに~3つの立場から貫いた多文化共生への想い~
1.横浜市の地域性
2.中学校における、国際教室の運営
3.教育委員会での取組
4.小学校管理職としての多文化共生の学校作り
5.異なる立場からの課題~中学校、教育委員会、小学校管理職~
おわりに~共生社会が当たり前となる社会へ~
【高等学校の日本語講師の立場から】
第6章 日本語講師の視点から見る高等学校での課題
~学業継続・進学・就職の難しさ~(重山 陽子)
はじめに~生徒支援のきっかけ~
1.高校における「日本語指導が必要な生徒」
2.神奈川県内の外国につながる生徒
3.進路についての3つの課題
~生徒一人ひとりの実態から考える要因~
4.今後の希望~他分野での支援策・既存の教材の利用~
おわりに~将来を切り拓いていくために~
【保護者支援者の立場から】
第7章 外国につながる子どもの保護者が抱える問題と保護者支援
~地域日本語教室における支援の実践から見えること~(今村 桜子)
はじめに~外国人保護者との出会い~
1.外国人保護者の抱える問題
2.保護者支援
おわりに~教師や支援者による保護者支援を~
【海外日本語学校教員、国内小学校支援者の立場から】
第8章 日本と母国を行き来する外国につながる子どもの進路選択における課題
~帰国後や将来を見据えた支援の必要性~(上法 顕子)
はじめに~帰国した青年とのブラジルでの出会い~
1.将来を見据えた支援の重要性
2.日本と母国の間で揺れ動く進路選択
~それぞれに異なる事情~
3.日本と母国の垣根を越えた進路選択の支援
おわりに~日本でも母国でも生きていけるように~
執筆者紹介
用語索引
