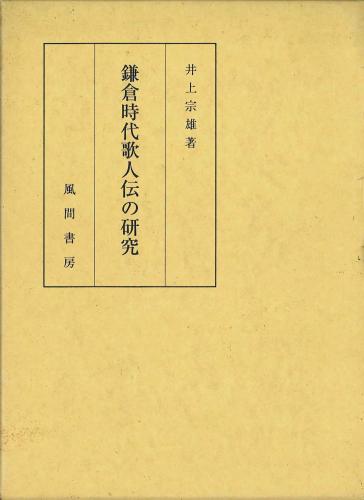
鎌倉時代歌人伝の研究
定価19,800円(本体 18,000円+税)
鎌倉時代の和歌の重要な家としての六条家、御子左家の動向を考察。また藤原信実、阿仏尼ほか主要歌人の生涯に詳細な検討を加え、鎌倉時代の歌壇の流れを大観する。
【著者略歴】
井上宗雄(いのうえ むねお)
1926(大正15)年 東京に生まれる
1951(昭和26)年 早稲田大学第一文学部(国文学専修)卒業
1953(昭和28)年 早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了
1966(昭和41)年 文学博士(立教大学)
早稲田大学高等学院教諭、立教大学教授を経て、
早稲田大学教授、立教大学名誉教授
※略歴は刊行当時のものです※
【主な著書】
『中世歌壇史の研究 室町前期』('61 風間書房、'84 改訂新版)
目次を表示
第一章 鎌倉前期における六条藤家の人々
一 新古今時代における六条家
二 経家・家衡・保季
1 経 家
経家略年譜(建久以後) 経家の和歌 まとめ
2 家 衡
3 保 季
4 六条家(九条家)略年表
承久三年~仁治三年
三 藤原行家の生涯―年譜風に―
第二章 藤原信実とその子孫たち―法性寺家の人々―
一 藤原信実年譜考証
二 信実補説
―右金吾(養子之禅尼)・春花門院弁(連歌禅尼)らをめぐって―
三 藤原(法性寺)為継と為信と
付 為理以下の末孫たち
第三章 御子左家の周辺
一 藤原(京極)為数年譜考
二 伝為兼資料二つ
―いわゆる「為兼★三十三首」と「詠源氏物語巻名和歌」
(解説と翻刻)と―
三 安裏門院とその女房たち
―阿仏尼序説―
四 阿仏尼伝の一考察
1 出自と生年
2 出仕、女房名
3 『うたたね』とその後
4 子どもたち
5 多くの譲状
6 建治・弘安期―その晩年―
7 歌歴について
8 略年譜
五 一条実経について
六 一条実経年譜
第四章 実材★母をめぐって
序説
一 権中納言実材★母集
付 平親清について
二 藤原政範集を紹介し実材★母集等との関係に及ぶ
三 平親清の娘たち、そして越前々司時広
四 平親清四女・五女とその家集
五 平親清五女集
―翻刻と考察―
付 実材★母一族略年譜
終りに
第五章 文永二年―白河殿七百首を中心に―
一 白河殿七百首の基礎的考察
―伝本と成立とを中心に―
二 歌壇・文永二年
―白河殿七百首の作者を中心に―
付 後嵯峨院の時代と後深草院二条
付章
一 『明題部類抄』をめぐって
―中世成立の歌題集成書の考察―
二 歌壇の概観
索引
初出について
あとがき
一 新古今時代における六条家
二 経家・家衡・保季
1 経 家
経家略年譜(建久以後) 経家の和歌 まとめ
2 家 衡
3 保 季
4 六条家(九条家)略年表
承久三年~仁治三年
三 藤原行家の生涯―年譜風に―
第二章 藤原信実とその子孫たち―法性寺家の人々―
一 藤原信実年譜考証
二 信実補説
―右金吾(養子之禅尼)・春花門院弁(連歌禅尼)らをめぐって―
三 藤原(法性寺)為継と為信と
付 為理以下の末孫たち
第三章 御子左家の周辺
一 藤原(京極)為数年譜考
二 伝為兼資料二つ
―いわゆる「為兼★三十三首」と「詠源氏物語巻名和歌」
(解説と翻刻)と―
三 安裏門院とその女房たち
―阿仏尼序説―
四 阿仏尼伝の一考察
1 出自と生年
2 出仕、女房名
3 『うたたね』とその後
4 子どもたち
5 多くの譲状
6 建治・弘安期―その晩年―
7 歌歴について
8 略年譜
五 一条実経について
六 一条実経年譜
第四章 実材★母をめぐって
序説
一 権中納言実材★母集
付 平親清について
二 藤原政範集を紹介し実材★母集等との関係に及ぶ
三 平親清の娘たち、そして越前々司時広
四 平親清四女・五女とその家集
五 平親清五女集
―翻刻と考察―
付 実材★母一族略年譜
終りに
第五章 文永二年―白河殿七百首を中心に―
一 白河殿七百首の基礎的考察
―伝本と成立とを中心に―
二 歌壇・文永二年
―白河殿七百首の作者を中心に―
付 後嵯峨院の時代と後深草院二条
付章
一 『明題部類抄』をめぐって
―中世成立の歌題集成書の考察―
二 歌壇の概観
索引
初出について
あとがき
