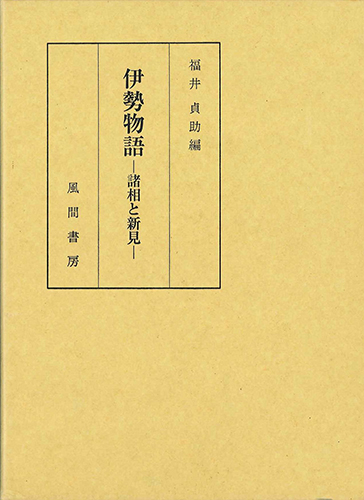
伊勢物語 諸相と新見
定価18,700円(本体 17,000円+税)
今日の伊勢物語研究の担い手である諸学者が、各自得意とし、問題と考え、あるいは未来を切り開く新見解を開陳執筆。編者の古希を記念した画期的論文集である。
【編者略歴】
福井貞助(ふくい ていすけ)
大正14年新潟県生まれ。
昭和23年東京大学文学部国文学科卒業。
弘前大学人文学部教授、静岡大学人文学部助教授、東京家政学院大学人文学部教授を歴任した。
現在静岡大学名誉教授。
【編者略歴】
福井貞助(ふくい ていすけ)
大正14年新潟県生まれ。
昭和23年東京大学文学部国文学科卒業。
弘前大学人文学部教授、静岡大学人文学部助教授、東京家政学院大学人文学部教授を歴任した。
現在静岡大学名誉教授。
目次を表示
『源氏物語』から『伊勢物語』へ 秋山 虔
『伊勢物語』初段考 仁平 道明
―物語のはじまりと唐代伝奇―
初段「女はらから」について 石田 穣二
伊勢物語的なるもの 野口 元大
『伊勢物語』の冒頭表現 片桐 洋一
伊勢物語の構成と名称 森本 茂
伊勢物語の日付記載章段と和歌 藤岡 忠実
勢語散文と勢語和歌 神尾 暢子
「まめ男」の背景 今西祐一郎
―『伊勢物語』試論―
『伊勢物語』の十六段について 河地 修
―紀有常と和歌―
河内の国高安と大和の国葛城 雨海 博洋
―伊勢物語と大和物語―
伊勢物語六三段と漢文学 今井 源衛
『伊勢物語』第六五段と第六九段をめぐって 菊地 靖彦
顕昭『古今集注』六四六番歌・注釈の意味するもの 市原 愿
伊勢物語の相補的解釈 田口 尚幸
―その序説としての試論―
伊勢物語と題詠 山本 登朗
―惟喬親王章段の世界―
伊勢物語と『古今和歌集』 松田 喜好
―八十七段を中心として―
定家本伊勢物語の表現形成 室伏 信助
―住書行幸の章段をめぐって―
『伊勢物語』と『万葉集』 柳田 忠則
―物語形成の一面―
『伊勢物語』の原形と『古今集』業平歌の詞書 山田 清市
現存本伊勢物語生成序説 渡辺 泰宏
―その基幹部分の生成と作者の性格に関する試論―
狩使本伊勢物語の構成と増益をめぐって 林 美朗
冷泉為和本伊勢物語について 中田 武司
鎌倉時代初期の作品における『伊勢物語』の享受 伊藤 颯夫
伊勢物語の特質と終焉段 福井 貞助
編者後記
『伊勢物語』初段考 仁平 道明
―物語のはじまりと唐代伝奇―
初段「女はらから」について 石田 穣二
伊勢物語的なるもの 野口 元大
『伊勢物語』の冒頭表現 片桐 洋一
伊勢物語の構成と名称 森本 茂
伊勢物語の日付記載章段と和歌 藤岡 忠実
勢語散文と勢語和歌 神尾 暢子
「まめ男」の背景 今西祐一郎
―『伊勢物語』試論―
『伊勢物語』の十六段について 河地 修
―紀有常と和歌―
河内の国高安と大和の国葛城 雨海 博洋
―伊勢物語と大和物語―
伊勢物語六三段と漢文学 今井 源衛
『伊勢物語』第六五段と第六九段をめぐって 菊地 靖彦
顕昭『古今集注』六四六番歌・注釈の意味するもの 市原 愿
伊勢物語の相補的解釈 田口 尚幸
―その序説としての試論―
伊勢物語と題詠 山本 登朗
―惟喬親王章段の世界―
伊勢物語と『古今和歌集』 松田 喜好
―八十七段を中心として―
定家本伊勢物語の表現形成 室伏 信助
―住書行幸の章段をめぐって―
『伊勢物語』と『万葉集』 柳田 忠則
―物語形成の一面―
『伊勢物語』の原形と『古今集』業平歌の詞書 山田 清市
現存本伊勢物語生成序説 渡辺 泰宏
―その基幹部分の生成と作者の性格に関する試論―
狩使本伊勢物語の構成と増益をめぐって 林 美朗
冷泉為和本伊勢物語について 中田 武司
鎌倉時代初期の作品における『伊勢物語』の享受 伊藤 颯夫
伊勢物語の特質と終焉段 福井 貞助
編者後記
