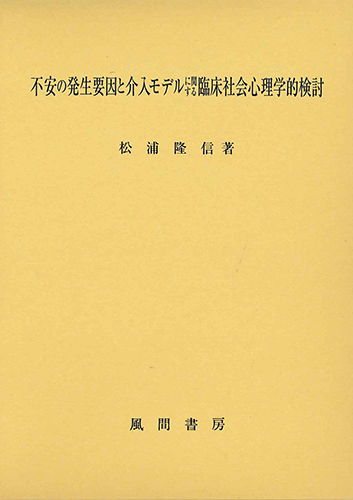
不安の発生要因と介入モデルに関する臨床社会心理学的検討
定価5,500円(本体 5,000円+税)
不安の発生要因および介入時の要点について、統計研究と事例研究の両者に基づき記述。臨床実践の内実に説明言語を与えるための心理学研究のあり方を提案する書。
☆第二回 日本森田療法学会奨励賞☆
【著者略歴】
松浦隆信(まつうら たかのぶ)
神奈川県横浜市出身
現職:鹿児島大学大学院臨床心理学研究科講師
専門領域:臨床心理学 臨床社会心理学 森田療法
職歴・教育歴:心療内科クリニックでの常勤臨床心理士としての臨床実践を中心に,不登校・ひきこもり当事者および家族への電話相談,ハローワークにおける就労支援などに従事する。2009年4月,上記クリニック在職中に日本大学大学院文学研究科心理学専攻博士後期課程に進学し,臨床実践と併行して研究活動を行う。2012年3月,同大学院修了,博士(心理学)。東京成徳大学応用心理学部および大妻女子大学人間関係学部非常勤講師,立正大学心理学部特任講師を経て現職。臨床心理士養成の専門職大学院教員として教育および研究活動の他,大学付属心理相談室でのケース担当や病院職員に対するメンタルヘルス相談などの臨床実践に取り組む。
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示
序
本研究の構成
第一章 不安の発生・維持メカニズム:総論
第1節 不安に関する諸問題
Ⅰ 不安の多様性
Ⅱ 不安の併存(Comorbidity)と連続性
Ⅲ 研究と治療の遅れ
Ⅳ まとめ
第2節 様々な不安と関連する認知行動的変数
Ⅰ 自己没入
Ⅱ 自己効力感
Ⅲ 回避
第3節 制御理論に基づく不安の発生・維持メカニズム
第二章 先行研究の問題点と本研究の目的
第1節 先行研究の問題点
Ⅰ 不安と抑うつの識別―特に自己没入との関連において―
Ⅱ 不安自体が各認知行動的変数に影響を与える可能性の検証
Ⅲ 社会的要因を加味したモデルの検討―特に親子関係のあり方について―
Ⅳ 介入方法および数量的効果検討
第2節 本研究の目的
第三章 自己没入と不安との関連―抑うつとの識別を考慮に入れて―
研究1 不安と抑うつの識別性が異なる複数尺度を用いた検討
研究2 不安障害疾患群における検討―うつ病群との比較―
第四章 不安および親子関係と自己没入・自己効力感・BISとの関連
研究3 不安が各認知行動的変数に影響を及ぼす可能性についての検討
研究4 両親の養育態度と各認知行動的変数との関連―疾患群での検討―
研究5 不安の親子間伝播メカニズムの検証―行動抑制系(BIS)の役割に焦点を当てて―
第五章 制御理論に基づく介入モデルの検証
研究6 自己没入の軽減をねらいとしたパニック障害への介入
研究7 親子関係のあり方に配慮した社交不安障害への介入
研究8 「対人不安軽減プログラム」に基づく介入モデルの効果検討
第六章 本研究の総括
第1節 総合考察
Ⅰ 不安の発生・維持メカニズムについて
Ⅱ 不安に対する介入モデルについて
第2節 本研究の限界と今後の課題
引用文献
謝辞
付録 使用質問紙
本研究の構成
第一章 不安の発生・維持メカニズム:総論
第1節 不安に関する諸問題
Ⅰ 不安の多様性
Ⅱ 不安の併存(Comorbidity)と連続性
Ⅲ 研究と治療の遅れ
Ⅳ まとめ
第2節 様々な不安と関連する認知行動的変数
Ⅰ 自己没入
Ⅱ 自己効力感
Ⅲ 回避
第3節 制御理論に基づく不安の発生・維持メカニズム
第二章 先行研究の問題点と本研究の目的
第1節 先行研究の問題点
Ⅰ 不安と抑うつの識別―特に自己没入との関連において―
Ⅱ 不安自体が各認知行動的変数に影響を与える可能性の検証
Ⅲ 社会的要因を加味したモデルの検討―特に親子関係のあり方について―
Ⅳ 介入方法および数量的効果検討
第2節 本研究の目的
第三章 自己没入と不安との関連―抑うつとの識別を考慮に入れて―
研究1 不安と抑うつの識別性が異なる複数尺度を用いた検討
研究2 不安障害疾患群における検討―うつ病群との比較―
第四章 不安および親子関係と自己没入・自己効力感・BISとの関連
研究3 不安が各認知行動的変数に影響を及ぼす可能性についての検討
研究4 両親の養育態度と各認知行動的変数との関連―疾患群での検討―
研究5 不安の親子間伝播メカニズムの検証―行動抑制系(BIS)の役割に焦点を当てて―
第五章 制御理論に基づく介入モデルの検証
研究6 自己没入の軽減をねらいとしたパニック障害への介入
研究7 親子関係のあり方に配慮した社交不安障害への介入
研究8 「対人不安軽減プログラム」に基づく介入モデルの効果検討
第六章 本研究の総括
第1節 総合考察
Ⅰ 不安の発生・維持メカニズムについて
Ⅱ 不安に対する介入モデルについて
第2節 本研究の限界と今後の課題
引用文献
謝辞
付録 使用質問紙
