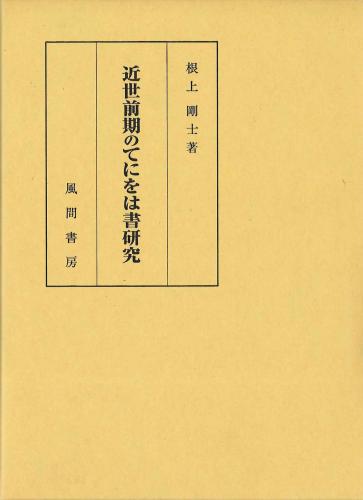
近世前期のてにをは書研究
定価19,800円(本体 18,000円+税)
「手爾葉大概抄」「姉小路式」について諸本の系統・成立事情を考究、てにをは書を通して日本人の言語意識を探る。さらに、古辞書・仮名遣い書にも論及する労作。
【著者略歴】
根上剛士(ねがみ つよし)
静岡県沼津市出身
昭和9年9月10日生
東京教育大学大学院文学研究科
日本文学専攻修士課程修了
東京都立高等学校教諭
埼玉大学教授(名誉教授)
東洋大学教授
※略歴は刊行当時のものです※
目次を表示
はじめに ―てには秘伝と連歌論
第一部 てにをは秘伝書研究
第一章 手爾葉大概抄の成立時期
第二章 手爾葉大概抄の研究 一
第三章 手爾葉大概抄の研究 二
第四章 手爾葉大概抄の研究 三
第五章 手爾葉大概抄の研究 四
第六章 連歌てにをは書と手爾葉大概抄
―星加宗一氏論文『連歌諸体秘伝抄』を中心として―
第七章 姉小路式の研究 一
―『歌道秘事口伝之事』との関係―
第八章 姉小路式の研究 二
―水府明徳会彰考館文庫蔵『手耳葉口伝』について―
第九章 姉小路式の研究 三
―姉小路式の伝本について―
第十章 姉小路式の研究 四
―『歌道秘蔵録』を中心として―
第十一章 『八代集手爾葉』と『和歌手爾葉伝授』
第十二章 『八代集てには』の疑いの「か」「や」「ぞ」の説について
第二部 てにをは書研究
第一章 『古今集和歌助辞分類』と『百人一首歌のこころ』
第二章 『古今集和歌助辞分類』と『和訓栞』
―『和訓栞』所引の資料として―
第三章 『古今集和歌助辞分類』と漢語文典
―中国漢字字書の助辞研究への影響―
第四章 村上織部と『天仁葉伝授』
第五章 村上織部撰『★藻編』について
第六章 『助辞和名考』について
第七章 『あゆひ抄』の「言霊」について
第八章 『あゆひ抄』の「だに家」の説について
第九章 『あゆひ抄』の「しるしの『て』」について
第三部 古辞書・仮名遣い書の研究
第一章 易林本節用集の「イ」「ヰ」、「ヲ」「オ」、「エ」「ヱ」部成立と「仮名文字遣」
第二章 文明本節用集年時注記考証
第三章 和漢通用集の所収語
第四章 西来寺蔵『名目抄』について
第五章 名目抄声点本考
第六章 国立国会図書館蔵『定家仮名づかひ』について
―四つ仮名の発音注記―
あとがき
索引
第一部 てにをは秘伝書研究
第一章 手爾葉大概抄の成立時期
第二章 手爾葉大概抄の研究 一
第三章 手爾葉大概抄の研究 二
第四章 手爾葉大概抄の研究 三
第五章 手爾葉大概抄の研究 四
第六章 連歌てにをは書と手爾葉大概抄
―星加宗一氏論文『連歌諸体秘伝抄』を中心として―
第七章 姉小路式の研究 一
―『歌道秘事口伝之事』との関係―
第八章 姉小路式の研究 二
―水府明徳会彰考館文庫蔵『手耳葉口伝』について―
第九章 姉小路式の研究 三
―姉小路式の伝本について―
第十章 姉小路式の研究 四
―『歌道秘蔵録』を中心として―
第十一章 『八代集手爾葉』と『和歌手爾葉伝授』
第十二章 『八代集てには』の疑いの「か」「や」「ぞ」の説について
第二部 てにをは書研究
第一章 『古今集和歌助辞分類』と『百人一首歌のこころ』
第二章 『古今集和歌助辞分類』と『和訓栞』
―『和訓栞』所引の資料として―
第三章 『古今集和歌助辞分類』と漢語文典
―中国漢字字書の助辞研究への影響―
第四章 村上織部と『天仁葉伝授』
第五章 村上織部撰『★藻編』について
第六章 『助辞和名考』について
第七章 『あゆひ抄』の「言霊」について
第八章 『あゆひ抄』の「だに家」の説について
第九章 『あゆひ抄』の「しるしの『て』」について
第三部 古辞書・仮名遣い書の研究
第一章 易林本節用集の「イ」「ヰ」、「ヲ」「オ」、「エ」「ヱ」部成立と「仮名文字遣」
第二章 文明本節用集年時注記考証
第三章 和漢通用集の所収語
第四章 西来寺蔵『名目抄』について
第五章 名目抄声点本考
第六章 国立国会図書館蔵『定家仮名づかひ』について
―四つ仮名の発音注記―
あとがき
索引
