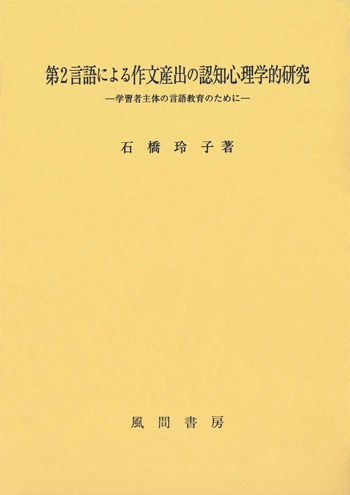
第2言語による作文産出の認知心理学的研究
学習者主体の言語教育のために
定価8,250円(本体 7,500円+税)
国内外の日本語学習者の作文産出に関する研究結果をまとめ、その知見から学習者の認知過程、認知要因、情意要因に配慮した第2言語の作文教育への示唆を提示する。
【著者略歴】
石橋玲子(いしばし れいこ)
昭和女子大学大学院文学研究科 特任教授
1965年 お茶の水女子大学文教育学部教育学科卒業
1991年 ジョージタウン大学言語学部大学院TESOL課程単位取得
1997年 お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修了
修士(人文科学)
2000年 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了
博士(人文科学)
茨城大学留学生センター教授などを経て現職。
【著者略歴】
石橋玲子(いしばし れいこ)
昭和女子大学大学院文学研究科 特任教授
1965年 お茶の水女子大学文教育学部教育学科卒業
1991年 ジョージタウン大学言語学部大学院TESOL課程単位取得
1997年 お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修了
修士(人文科学)
2000年 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了
博士(人文科学)
茨城大学留学生センター教授などを経て現職。
目次を表示
まえがき
第1部 第2言語の作文産出における第1言語の認知的関与
第1章 第2言語習得における第1言語の関与
1-1 はじめに
1-1-1 問題の所在
1-1-2 基本用語の定義
1-2 第2言語習得研究における本書の研究の位置づけ
1-3 第2言語習得における第1言語の役割の捉え方
1-3-1 言語転移
1-3-2 共有基底言語能力モデル(言語相互依存仮説)
1-4 第2言語の作文研究の概観
1-4-1 産出作文研究から産出過程研究へ
1-4-2 第1言語の関与に関する先行研究
1-4-3 先行研究の問題点
第2章 第2言語の作文産出過程における第1言語の関与
2-1 研究の背景
2-1-1 作文産出過程のモデル
2-1-2 日本語学習者対象の先行研究
2-1-3 発話思考法
2-2 研究目的
2-3 研究方法
2-4 結果と考察
2-4-1 作文産出過程の行動カテゴリー頻度
2-4-2 作文産出過程プロトコル中の第1言語使用
2-4-3 「リハーサル」における第1言語使用
2-5 まとめ
第3章 第2言語の作文産出に及ぼす第1言語介入の影響(Ⅰ)
3-1 研究目的と研究方法
3-1-1 研究目的
3-1-2 研究方法
3-2 作文の質に及ぼす影響
3-2-1 研究課題
3-2-2 質的分析の方法
3-2-2-1 分析の枠組みと評価基準
3-2-2-2 評定法
3-2-3 結果
3-2-3-1 質の主要構成要素の平均得点
3-2-3-2 日本語能力と作文プロセスの影響
3-2-4 結果の考察
3-3 作文の産出量に及ぼす影響―流暢性と構文の複雑さ
3-3-1 研究課題
3-3-2 分析方法
3-3-2-1 流暢性の認定尺度
3-3-2-2 構文的複雑さの尺度
3-3-3 結果
3-3-3-1 文の流暢性
3-3-3-2 文の構文的複雑性
3-3-4 結果の考察
3-4 作文の誤用に及ぼす影響
3-4-1 誤用判定の問題
3-4-2 研究課題
3-4-3 誤用分析の方法
3-4-3-1 全体的誤用の判定と分析データ
3-4-3-2 全体的誤用の分類
3-4-4 結果
3-4-4-1 全体的誤用から見た誤用率
3-4-4-2 全体的誤用の種類別結果
3-4-5 結果の考察
3-5 学習者の第1言語使用についての意識
3-5-1 研究の背景
3-5-2 研究目的
3-5-3 研究方法
3-5-4 結果と考察
3-5-4-1 作文の自己評価の比較
3-5-4-2 作文の書きやすさについての意識
3-5-4-3 第1言語使用についての意識
3-5-4-4 第1言語と第2言語の作文時の留意点の違い
3-5-5 まとめ
3-6 第1言語の「逆U字型効果」
第4章 第2言語の作文産出に及ぼす第1言語介入の影響(Ⅱ)
4-1 文章構成に及ぼす第1言語使用の影響
4-1-1 文章構成の定義
4-1-2 先行研究
4-1-3 研究目的
4-1-4 研究方法
4-1-5 結果と考察
4-1-5-1 文章構成パターン
4-1-5-2 作文の質の得点平均間の相関
4-1-6 まとめと今後の課題
4-2 作文のトピックの認知負担の観点から
4-2-1 問題の背景
4-2-2 先行研究
4-2-3 研究目的
4-2-4 研究方法
4-2-5 結果と考察
4-2-5-1 直接作文にトピックの抽象度が及ぼす影響
4-2-5-2 翻訳作文にトピックの抽象度が及ぼす影響
4-2-6 まとめ
4-3 第1言語の作文力との関連
4-3-1 問題の所在と研究目的
4-3-2 先行研究
4-3-3 研究方法
4-3-4 結果と考察
4-3-4-1 第1言語の作文力と第2言語の作文力の相関
4-3-4-2 作文の質の主要佼成要素毎の比較
4-3-5 まとめと今後の課題
第2部 産出作文の逸脱への認識
第5章 逸脱への学習者の気づき
5-1 学習者の自己訂正から見るモニター能力
5-1-1 はじめに
5-1-1-1 問題の所在と研究意義
5-1-1-2 先行研究
5-1-2 研究目的
5-1-3 研究方法
5-1-4 結果と考察
5-1-4-1 自己訂正の量的分析
5-1-4-2 自己訂正の質的分析
5-1-5 まとめと今後の課題
5-2 作文推敲課程から見る自己訂正、教師訂正の効果
5-2-1 はじめに
5-2-1-1 研究の意義
5-2-1-2 研究目的
5-2-2 先行研究
5-2-2-1 教師の添削の効果
5-2-2-2 自己訂正の効果
5-2-2-3 気づき
5-2-3 研究方法
5-2-4 結果と考察
5-2-4-1 対象作文のプロフィール
5-2-4-2 自己訂正過程における学習者の気づき
5-2-4-3 教師の誤用訂正に対する学習者の気づきと対応
5-2-4-4 教師の非修正箇所に対する学習者の気づきと対応
5-2-5 まとめと今後の課題
5-3 学習者の作文の誤用への気づきと修正
5-3-1 はじめに
5-3-2 先行研究
5-3-2-1 言語習得における気づき
5-3-2-2 気づきとフィードバック
5-3-3 研究目的
5-3-4 研究方法
5-3-5 結果と考察
5-3-5-1 自己訂正およびピア修正の気づきと修正
5-3-5-2 教師の非明示的フィードバックに対する気づきと修正
5-3-6 作文教育への提案
5-3-7 まとめと今後の課題
第6章 産出作文に対する教師のフィードバック
6-1 教師のフィードバックに対する学習者の認識と対応
6-1-1 問題の所在と先行研究
6-1-2 研究目的
6-1-3 研究方法
6-1-4 結果と考察
6-1-4-1 教師のフィードバックに対する学習者の留意
6-1-4-2 教師のフィードバックに対する学習者の対処
6-1-5 まとめと今後の課題
6-2 教師の記述的フィードバック過程―修正および非修正
6-2-1 問題の所在
6-2-2 先行研究
6-2-3 研究目的
6-2-4 研究方法
6-2-5 結果と考察
6-2-5-1 教師のフィードバック過程
6-2-5-2 教師のフィードバック結果における修正
6-2-6 まとめと今後の課題
第3部 作文産出に関わる学習者の認知的・情意的要因
第7章 学習者の作文産出に関わる認知的要因
7-1 作文産出に関わる学習者のビリーフ
7-1-1 研究の意義
7-1-2 研究目的
7-1-3 先行研究
7-1-4 研究方法
7-1-5 結果と考察
7-1-5-1 文章産出に関するビリーフ
7-1-5-2 日本語習熟度と作文産出に関するビリーフとの関連
7-1-5-3 日本語学習者の文章産出ビリーフを規定している要因
7-1-6 まとめと今後の課題
7-2 作文産出に関わるビリーフとストラテジー
7-2-1 研究の背景と意義
7-2-2 先行研究
7-2-3 研究目的
7-2-4 研究方法
7-2-5 結果と考察
7-2-5-1 作文産出の因子分析結果
7-2-5-2 因子の解釈と考察
7-2-5-3 因子と日本語の習熟度、作文成績との関連
7-2-6 まとめと今後の課題
第8章 作文産出に関連する学習者の情意的要因
8-1 作文産出に関連する不安要因
8-1-1 研究の背景と意義
8-1-2 先行研究
8-1-2-1 第2言語不安
8-1-2-2 第2言語の作文不安
8-1-3 研究目的
8-1-4 研究方法
8-1-5 結果と考察
8-1-5-1 作文に関わる不安要因の因子分析結果
8-1-5-2 作文に関わる不安要因と成績との関係
8-1-5-3 作文に関わる不安要因と日本語の習熟度との関係
8-1-5-4 作文不安群別による因子との関連
8-1-6 まとめと今後の課題
第9章 第2言語の作文教育への示唆
引用文献
資料
本書の章、節における論文の初出発表
第1部 第2言語の作文産出における第1言語の認知的関与
第1章 第2言語習得における第1言語の関与
1-1 はじめに
1-1-1 問題の所在
1-1-2 基本用語の定義
1-2 第2言語習得研究における本書の研究の位置づけ
1-3 第2言語習得における第1言語の役割の捉え方
1-3-1 言語転移
1-3-2 共有基底言語能力モデル(言語相互依存仮説)
1-4 第2言語の作文研究の概観
1-4-1 産出作文研究から産出過程研究へ
1-4-2 第1言語の関与に関する先行研究
1-4-3 先行研究の問題点
第2章 第2言語の作文産出過程における第1言語の関与
2-1 研究の背景
2-1-1 作文産出過程のモデル
2-1-2 日本語学習者対象の先行研究
2-1-3 発話思考法
2-2 研究目的
2-3 研究方法
2-4 結果と考察
2-4-1 作文産出過程の行動カテゴリー頻度
2-4-2 作文産出過程プロトコル中の第1言語使用
2-4-3 「リハーサル」における第1言語使用
2-5 まとめ
第3章 第2言語の作文産出に及ぼす第1言語介入の影響(Ⅰ)
3-1 研究目的と研究方法
3-1-1 研究目的
3-1-2 研究方法
3-2 作文の質に及ぼす影響
3-2-1 研究課題
3-2-2 質的分析の方法
3-2-2-1 分析の枠組みと評価基準
3-2-2-2 評定法
3-2-3 結果
3-2-3-1 質の主要構成要素の平均得点
3-2-3-2 日本語能力と作文プロセスの影響
3-2-4 結果の考察
3-3 作文の産出量に及ぼす影響―流暢性と構文の複雑さ
3-3-1 研究課題
3-3-2 分析方法
3-3-2-1 流暢性の認定尺度
3-3-2-2 構文的複雑さの尺度
3-3-3 結果
3-3-3-1 文の流暢性
3-3-3-2 文の構文的複雑性
3-3-4 結果の考察
3-4 作文の誤用に及ぼす影響
3-4-1 誤用判定の問題
3-4-2 研究課題
3-4-3 誤用分析の方法
3-4-3-1 全体的誤用の判定と分析データ
3-4-3-2 全体的誤用の分類
3-4-4 結果
3-4-4-1 全体的誤用から見た誤用率
3-4-4-2 全体的誤用の種類別結果
3-4-5 結果の考察
3-5 学習者の第1言語使用についての意識
3-5-1 研究の背景
3-5-2 研究目的
3-5-3 研究方法
3-5-4 結果と考察
3-5-4-1 作文の自己評価の比較
3-5-4-2 作文の書きやすさについての意識
3-5-4-3 第1言語使用についての意識
3-5-4-4 第1言語と第2言語の作文時の留意点の違い
3-5-5 まとめ
3-6 第1言語の「逆U字型効果」
第4章 第2言語の作文産出に及ぼす第1言語介入の影響(Ⅱ)
4-1 文章構成に及ぼす第1言語使用の影響
4-1-1 文章構成の定義
4-1-2 先行研究
4-1-3 研究目的
4-1-4 研究方法
4-1-5 結果と考察
4-1-5-1 文章構成パターン
4-1-5-2 作文の質の得点平均間の相関
4-1-6 まとめと今後の課題
4-2 作文のトピックの認知負担の観点から
4-2-1 問題の背景
4-2-2 先行研究
4-2-3 研究目的
4-2-4 研究方法
4-2-5 結果と考察
4-2-5-1 直接作文にトピックの抽象度が及ぼす影響
4-2-5-2 翻訳作文にトピックの抽象度が及ぼす影響
4-2-6 まとめ
4-3 第1言語の作文力との関連
4-3-1 問題の所在と研究目的
4-3-2 先行研究
4-3-3 研究方法
4-3-4 結果と考察
4-3-4-1 第1言語の作文力と第2言語の作文力の相関
4-3-4-2 作文の質の主要佼成要素毎の比較
4-3-5 まとめと今後の課題
第2部 産出作文の逸脱への認識
第5章 逸脱への学習者の気づき
5-1 学習者の自己訂正から見るモニター能力
5-1-1 はじめに
5-1-1-1 問題の所在と研究意義
5-1-1-2 先行研究
5-1-2 研究目的
5-1-3 研究方法
5-1-4 結果と考察
5-1-4-1 自己訂正の量的分析
5-1-4-2 自己訂正の質的分析
5-1-5 まとめと今後の課題
5-2 作文推敲課程から見る自己訂正、教師訂正の効果
5-2-1 はじめに
5-2-1-1 研究の意義
5-2-1-2 研究目的
5-2-2 先行研究
5-2-2-1 教師の添削の効果
5-2-2-2 自己訂正の効果
5-2-2-3 気づき
5-2-3 研究方法
5-2-4 結果と考察
5-2-4-1 対象作文のプロフィール
5-2-4-2 自己訂正過程における学習者の気づき
5-2-4-3 教師の誤用訂正に対する学習者の気づきと対応
5-2-4-4 教師の非修正箇所に対する学習者の気づきと対応
5-2-5 まとめと今後の課題
5-3 学習者の作文の誤用への気づきと修正
5-3-1 はじめに
5-3-2 先行研究
5-3-2-1 言語習得における気づき
5-3-2-2 気づきとフィードバック
5-3-3 研究目的
5-3-4 研究方法
5-3-5 結果と考察
5-3-5-1 自己訂正およびピア修正の気づきと修正
5-3-5-2 教師の非明示的フィードバックに対する気づきと修正
5-3-6 作文教育への提案
5-3-7 まとめと今後の課題
第6章 産出作文に対する教師のフィードバック
6-1 教師のフィードバックに対する学習者の認識と対応
6-1-1 問題の所在と先行研究
6-1-2 研究目的
6-1-3 研究方法
6-1-4 結果と考察
6-1-4-1 教師のフィードバックに対する学習者の留意
6-1-4-2 教師のフィードバックに対する学習者の対処
6-1-5 まとめと今後の課題
6-2 教師の記述的フィードバック過程―修正および非修正
6-2-1 問題の所在
6-2-2 先行研究
6-2-3 研究目的
6-2-4 研究方法
6-2-5 結果と考察
6-2-5-1 教師のフィードバック過程
6-2-5-2 教師のフィードバック結果における修正
6-2-6 まとめと今後の課題
第3部 作文産出に関わる学習者の認知的・情意的要因
第7章 学習者の作文産出に関わる認知的要因
7-1 作文産出に関わる学習者のビリーフ
7-1-1 研究の意義
7-1-2 研究目的
7-1-3 先行研究
7-1-4 研究方法
7-1-5 結果と考察
7-1-5-1 文章産出に関するビリーフ
7-1-5-2 日本語習熟度と作文産出に関するビリーフとの関連
7-1-5-3 日本語学習者の文章産出ビリーフを規定している要因
7-1-6 まとめと今後の課題
7-2 作文産出に関わるビリーフとストラテジー
7-2-1 研究の背景と意義
7-2-2 先行研究
7-2-3 研究目的
7-2-4 研究方法
7-2-5 結果と考察
7-2-5-1 作文産出の因子分析結果
7-2-5-2 因子の解釈と考察
7-2-5-3 因子と日本語の習熟度、作文成績との関連
7-2-6 まとめと今後の課題
第8章 作文産出に関連する学習者の情意的要因
8-1 作文産出に関連する不安要因
8-1-1 研究の背景と意義
8-1-2 先行研究
8-1-2-1 第2言語不安
8-1-2-2 第2言語の作文不安
8-1-3 研究目的
8-1-4 研究方法
8-1-5 結果と考察
8-1-5-1 作文に関わる不安要因の因子分析結果
8-1-5-2 作文に関わる不安要因と成績との関係
8-1-5-3 作文に関わる不安要因と日本語の習熟度との関係
8-1-5-4 作文不安群別による因子との関連
8-1-6 まとめと今後の課題
第9章 第2言語の作文教育への示唆
引用文献
資料
本書の章、節における論文の初出発表
