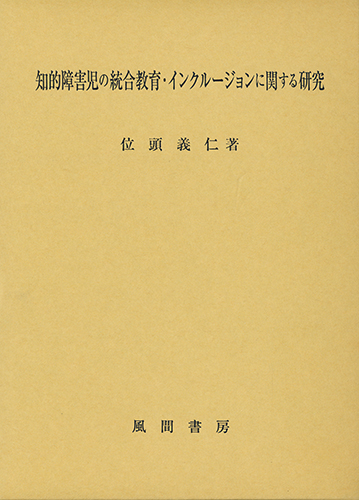
知的障害児の統合教育・インクルージョンに関する研究
定価8,800円(本体 8,000円+税)
著者40年に及ぶ日米の統合教育の実情を比較・研究した上で、現在進行中の特別支援教育の重要課題を指摘し、これを成功させる有益な方法を具体的に提示した労作。
【著者略歴】
位頭義仁(いとう よしひと)
1961年 徳島大学附属小学校教諭
1966年 徳島大学附属養護学校教諭
1972年 国立特殊教育総合研究所研究員
1978年 国立特殊教育研究所研究室長
1985年 鳴門教育大学助教授
1987年 鳴門教育大学教授
1990年 鳴門教育大学附属養護学校校長(併任)
1998年 鳴門教育大学評議員・学校教育研究センター長(併任)
2001年 徳島文理大学教授
徳島大学 横浜国立大学 四国大学 鳴門教育大学 愛媛大学の非常勤講師を歴任
現 在 鳴門教育大学名誉教授
徳島文理大学教授
博士(教育学)
【著者略歴】
位頭義仁(いとう よしひと)
1961年 徳島大学附属小学校教諭
1966年 徳島大学附属養護学校教諭
1972年 国立特殊教育総合研究所研究員
1978年 国立特殊教育研究所研究室長
1985年 鳴門教育大学助教授
1987年 鳴門教育大学教授
1990年 鳴門教育大学附属養護学校校長(併任)
1998年 鳴門教育大学評議員・学校教育研究センター長(併任)
2001年 徳島文理大学教授
徳島大学 横浜国立大学 四国大学 鳴門教育大学 愛媛大学の非常勤講師を歴任
現 在 鳴門教育大学名誉教授
徳島文理大学教授
博士(教育学)
目次を表示
序章 研究目的,研究課題および方法
第1節 研究目的
第2節 研究課題
第3節 研究方法
第1章 知的障害のある子どもの統合教育・インクルージョンの理論的研究
第1節 日本の知的障害のある子ども等の統合教育・インクルージョンの動向
1.法令,通達・通知,協力者会議報告等
2.山梨県におけるリソースルームの先行的実践
3.神奈川県における統合教育・インクルージョンの先行的実践
文 献
第2節 知的障害特殊学級と通常学級の交流教育に関する先行研究の検討
1.教科交流の教科と時間
2.交流教育に対する保護者と障害のある子どもの意識
3.教科交流の問題点
4.交流教育による障害のある子どもの変容
5.教員の態度
6.交流による一般の子どもの障害のある子どもに対する意識
7.障害(者)理解教育
文 献
第3節 通常学級に在籍する障害のある子どもの実態とその支援に関する先行研究の検討
1.通常学級に在籍する知的障害のある子どもの実態
2.教員が指導上困難と感じていること
3.通常学級に在籍する知的障害のある子どもの教育的支援の実態
4.通常学級に在籍する障害のある子どもの教育的支援の在り方
文 献
第2章 アメリカ合衆国の統合教育とインクルージョンの実情
第1節 アメリカ合衆国における統合教育の教育実践とその成果
―文献による考察―
1.問題と目的
2.統合教育による通常学級の教員の変化
3.統合教育の教育効果をめぐる検討
4.REIの主張と障害のある子どもの教育についての検討
文 献
第2節 アメリカ合衆国におけるインクルージョンの教育実践とその成果
―文献による考察―
1.問題と目的
2.インクルージョンの教育環境
3.インクルージョンの教育効果と評価
4.考 察
文 献
第3章 知的障害のある子どもの統合教育の実証的研究
第1節 通常学級における知的障害のある子どもに対する教育的支援と学習の実態
1.問題と目的
2.方 法
3.結果と考察
文 献
第2節 教科交流における教員,知的障害のある子ども,および一般の子どもの行動
1.問題と目的
2.方 法
3.結 果
4.考 察
文 献
資 料
第4章 特別支援教育の現状と課題
第1節 特別支援教育をめぐる論点の検討
1.特別な教育の対象となる障害の種別
2.通常学級に在籍する知的障害のある子ども等への教育的対応
3.特殊学級の縮小と「特別支援教室」
4.特別支援教育を支える教職員の問題
5.特別支援学校の地域の教育センターとしての役割
6.特別支援教育コーディネーター
文 献
資 料
第2節 小学校教員の統合教育・インクルージョンに関する意識
―徳島県と神奈川県における調査結果から―
1.研究目的
2.方 法
3.結 果
4.考 察
文 献
第3節 小学校における特別支援教育に向けての体制づくりに関する調査
1.研究目的
2.方 法
3.結 果
4.考 察
第5章 結 論
第1節 知的障害のある子どもの統合教育・インクルージョンの在り方
1.日本の知的障害のある子どもの統合教育・インクルージョンの課題
2.知的障害のある子どもの教育の場としての通常学級と特殊学級
3.知的障害のある子どもの特別な教育的ニーズと通常学級
文 献
第2節 アメリカ合衆国の統合教育・インクルージョンから日本は何を学ぶべきか
1.合衆国の統合教育・インクルージョンの制度
2.インクルージョンと日米の特性
文 献
あとがき
第1節 研究目的
第2節 研究課題
第3節 研究方法
第1章 知的障害のある子どもの統合教育・インクルージョンの理論的研究
第1節 日本の知的障害のある子ども等の統合教育・インクルージョンの動向
1.法令,通達・通知,協力者会議報告等
2.山梨県におけるリソースルームの先行的実践
3.神奈川県における統合教育・インクルージョンの先行的実践
文 献
第2節 知的障害特殊学級と通常学級の交流教育に関する先行研究の検討
1.教科交流の教科と時間
2.交流教育に対する保護者と障害のある子どもの意識
3.教科交流の問題点
4.交流教育による障害のある子どもの変容
5.教員の態度
6.交流による一般の子どもの障害のある子どもに対する意識
7.障害(者)理解教育
文 献
第3節 通常学級に在籍する障害のある子どもの実態とその支援に関する先行研究の検討
1.通常学級に在籍する知的障害のある子どもの実態
2.教員が指導上困難と感じていること
3.通常学級に在籍する知的障害のある子どもの教育的支援の実態
4.通常学級に在籍する障害のある子どもの教育的支援の在り方
文 献
第2章 アメリカ合衆国の統合教育とインクルージョンの実情
第1節 アメリカ合衆国における統合教育の教育実践とその成果
―文献による考察―
1.問題と目的
2.統合教育による通常学級の教員の変化
3.統合教育の教育効果をめぐる検討
4.REIの主張と障害のある子どもの教育についての検討
文 献
第2節 アメリカ合衆国におけるインクルージョンの教育実践とその成果
―文献による考察―
1.問題と目的
2.インクルージョンの教育環境
3.インクルージョンの教育効果と評価
4.考 察
文 献
第3章 知的障害のある子どもの統合教育の実証的研究
第1節 通常学級における知的障害のある子どもに対する教育的支援と学習の実態
1.問題と目的
2.方 法
3.結果と考察
文 献
第2節 教科交流における教員,知的障害のある子ども,および一般の子どもの行動
1.問題と目的
2.方 法
3.結 果
4.考 察
文 献
資 料
第4章 特別支援教育の現状と課題
第1節 特別支援教育をめぐる論点の検討
1.特別な教育の対象となる障害の種別
2.通常学級に在籍する知的障害のある子ども等への教育的対応
3.特殊学級の縮小と「特別支援教室」
4.特別支援教育を支える教職員の問題
5.特別支援学校の地域の教育センターとしての役割
6.特別支援教育コーディネーター
文 献
資 料
第2節 小学校教員の統合教育・インクルージョンに関する意識
―徳島県と神奈川県における調査結果から―
1.研究目的
2.方 法
3.結 果
4.考 察
文 献
第3節 小学校における特別支援教育に向けての体制づくりに関する調査
1.研究目的
2.方 法
3.結 果
4.考 察
第5章 結 論
第1節 知的障害のある子どもの統合教育・インクルージョンの在り方
1.日本の知的障害のある子どもの統合教育・インクルージョンの課題
2.知的障害のある子どもの教育の場としての通常学級と特殊学級
3.知的障害のある子どもの特別な教育的ニーズと通常学級
文 献
第2節 アメリカ合衆国の統合教育・インクルージョンから日本は何を学ぶべきか
1.合衆国の統合教育・インクルージョンの制度
2.インクルージョンと日米の特性
文 献
あとがき
