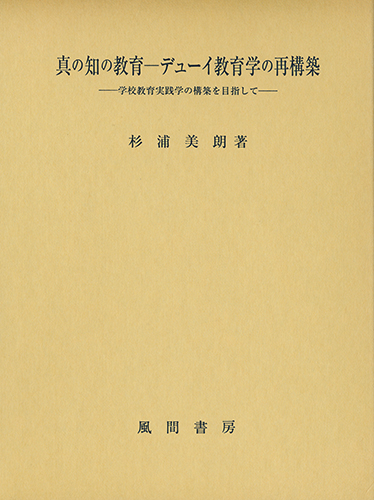
真の知の教育―デューイ教育学の再構築
学校教育実践学の構築を目指して
定価20,900円(本体 19,000円+税)
教員養成と学校カリキュラムの在り方が問われ、幾多の論議が展開されている現在、デューイ教育学と教育実践に学ぶことによって、学校教育実践学の在り方を探る。
【著者略歴】
杉浦美朗(すぎうら よしろう)
1933年 静岡県に生まれる
1960年 京都大学大学院教育学研究科博士課程満期退学
現在 兵庫教育大学名誉教授、甲南女子大学名誉教授、教育学博士
主著(デューイ教育学に関する単著に限定する)
『デューイにおける探究の研究』(風間書房、1976年)
『デューイにおける活動的な諸仕事の研究』(風間書房、1981年)
『デューイにおける教材の研究』(風間書房、1982年)
『デューイにおける探究としての学習』(風間書房、1984年)
『デューイにおける総合学習の研究』(風間書房、1985年)など
【著者略歴】
杉浦美朗(すぎうら よしろう)
1933年 静岡県に生まれる
1960年 京都大学大学院教育学研究科博士課程満期退学
現在 兵庫教育大学名誉教授、甲南女子大学名誉教授、教育学博士
主著(デューイ教育学に関する単著に限定する)
『デューイにおける探究の研究』(風間書房、1976年)
『デューイにおける活動的な諸仕事の研究』(風間書房、1981年)
『デューイにおける教材の研究』(風間書房、1982年)
『デューイにおける探究としての学習』(風間書房、1984年)
『デューイにおける総合学習の研究』(風間書房、1985年)など
目次を表示
はしがき
第1章 知性の誕生と本性
第1節 知性の自然性
1 自然の三層の連続性
進化論的自然主義
人間と自然の連続性
自然の三層の統合体としての人間
精神の偶発─心身二元論の克服─
還元論の克服─歴史的過程の連続性の回復─
生命の本質としての成長と進化
生命の本質としての成長と進化
─両価性の世界の中に生きる生活体の在り方─
要求→努力→満足→要求……の循環過程としての生命
自己保存の働きとしての生命
3 生命機制の具体
絶えざる生命衝動→個別衝動の展開としての生命
絶えざる好奇心→興味の展開としての生命
絶えざる感性→識別の展開としての生命
絶えざる感情→記号の展開としての生命
絶えざる通常形態の知性の働き
→最高形態の知性の働きの展開としての生命
4 実験─未知への進入─としての経験
生活体と環境の相互作用としての経験
実験としての経験
未知への進入としての経験
5 予見する働き→探究する働きとしての知性
具体的示唆としての知性
意味に対する反応=意図的活動としての知性
意味を積み込まれた活動─意図的活動─としての経験
活動を意図的にする働きとしての意味
意味の所有によって統制された意図的目的的活動としての知性
第2節 探究の実践性─状況の変容としての探究─
1 Inquiryとしての探究
2 探究の定義─状況の変容としての探究─
探究の定義─状況の変容としての探究─
1つの脈絡的全体としての状況
3 状況の現実存在的変容としての探究
4 自我の感情の内における変化ではない状況の現実存在的変容としての探究
5 実験による状況の現実存在的変容としての探究
実験による状況の現実存在的変容
状況の現実存在的変容の具体
第3節 探究の共同性─言語を通しての探究の成立─
1 言語の本質─活動の共同性─
人間同士の相互作用
信号反射─言語の基礎素材─
意味を持った存在=記号としての言語
言語の本質─活動の共同性の成立─
言語─意味─共同活動
2 道具の道具としての言語
言語の協約性
道具の道具としての言語〈1〉
道具の道具としての言語〈2〉
3 言語⇔意味⇔活動の共同体
4 シンボルとサイン
シンボルとサイン〈1〉
探究におけるシンボルとサイン
探究における専門シンボルの機能
5 探究の母胎としての言語─意味
第2章 探究の展開過程と論理構造
第1節 探究の展開過程
1 探究の展開過程の定式
デューイ自身の定式
われわれの定式
2 探究の展開過程の具体
探究の先行条件:不確定的状況
第1の探究の様相:不確定的状況における困難の感得
第2の探究の様相:問題の設定─観察を通しての知性的整理─
第3の探究の様相:推断による可能的解決策=仮説の策定
第4の探究の様相:推論による可能的解決策=仮説の理論的検証
=確定
第5の探究の様相:実験による可能的解決策=仮説の事実的検証
探究の最終結果:状況の変容と知識の産出=確定的状況と真理
われわれの最終の定式
3 探究の展開過程の柔軟性
柔軟な探究の展開過程
案内役としての探究の展開過程の定式
柔軟な案内役による探究の主体の誕生
第2節 探究の論理構造
1 与件と観念の共同としての探究
与件と観念の共同としての探究
与件と観念の共同の誕生
与件と観念の相互検証
2 命題の共同としての探究
現存命題
普遍命題
命題の共同としての探究
3 観察と推理の共同としての探究
操作の共同の形態
観察と推断の共同
推断と推論の共同
推論と観察の共同
回憶と推断の共同
推論と感得の共同
4 探究の論理構造の図式
第1図式
第2図式
第3図式
第4図式
範型図式─第4図式─
5 探究の論理構造の本性
案内役としての探究の論理構造
探究の論理構造の仮説性
第3節 探究における想像の役割
1 想像の本性
可能性を把握する働きとしての想像
想像を通しての理想の企投─発見と想像─
想像を通しての全体の把握
2 推断における想像の働き
現実性から可能性への飛躍としての推断
想像を通しての推断の展開
3 推論における想像の働き
可能性から可能性への飛躍としての推論
想像を通しての推論の展開
4 直接の観察における想像の働き
観念に導かれた事実の確定としての直接の観察
想像を通しての直接の観察の展開
5 間接の観察─回憶─における想像の働き
普遍命題によって陳述されている既有の知識や経験に基づく回憶
間接の観察─回憶─における想像の働き
第3章 探究の展開を通しての経験の改造─成長─としての教育─真の知の教育─
第1節 絶えざる探究の展開を通しての経験の改造─成長─としての教育
1 知性に導かれての経験の改造
教育としての成長の条件
第1条件:意味の増加
第2条件:後続の経験を方向づける能力の増大
成長の条件としての知性─知性に導かれての経験の改造としての教育─ 317
2 絶えざる探究の展開を通しての経験の改造─成長─としての教育
探究としての知性の働き
絶えざる探究の展開を通しての経験の改造─成長─としての教育
第2節 本来の自己教育─真の知の教育の具体─
1 成長する能力としての未熟性
成長する能力としての未熟性
社会的能力としての依存性
経験から学ぶ能力としての可塑性
子供の自己教育としての教育
2 すでに激しく活動的な存在としての子供
すでに激しく活動的な存在としての子供─太陽としての子供─
生まれつきの活動傾向の自発性
子供が為す何ごとかとしての成長
3 共同活動を通しての自己教育
教育の社会性─社会による子供の形成─
共同活動を通しての人間─子供─の形成
共同活動を通しての自己教育
第3節 真の知の教育の具体
1 真の知の教育の学習内容
学習者の経験における教材の成長
熟知としての知識
情報としての知識─コミュニケートされた知識─
科学としての知識
科学の方法─探究の方法─
2 真の知の教育のための学習媒体
記号としての学習媒体の種類
記号としての学習媒体の事例
3 真の知の教育のための学習場面
組織し直された社会生活としての学校
1つの共同体生活の形式としての学校
子供が生活する場所としての学校
外に開かれた学習場面としての学校
活動的な仕事の学校への導入
4 真の知の教育のための学習形態
一斉学習
集団学習
個別学習
5 真の知の教育における教授活動
教師の指導─広義の教授活動─の必要性
教師の指導の具体?=状況設定機能
教師の指導の具体?=探究指導機能
第4節 総合学習を通しての真の知の教育
1 活動的な仕事の内実
2 活動的な仕事からの形式的な教科の展開
活動的な仕事からの形式的な教科の展開
─教科学習 vs 総合学習の克服─
活動的な仕事からの形式的な教科の展開の具体
3 総合学習を通しての真の知の教育の教育課程
教育課程の構成原理─成長の原理─
成長段階の特徴
教材選択の具体
第5節 真の知の教育のための教育評価
1 教育評価の本質
教育評価の対象
教育評価の原理
2 学習活動の目標─学習目標─の具体
一般目標1
一般目標2
教育評価に基づく授業設計素描
あとがき
第1章 知性の誕生と本性
第1節 知性の自然性
1 自然の三層の連続性
進化論的自然主義
人間と自然の連続性
自然の三層の統合体としての人間
精神の偶発─心身二元論の克服─
還元論の克服─歴史的過程の連続性の回復─
生命の本質としての成長と進化
生命の本質としての成長と進化
─両価性の世界の中に生きる生活体の在り方─
要求→努力→満足→要求……の循環過程としての生命
自己保存の働きとしての生命
3 生命機制の具体
絶えざる生命衝動→個別衝動の展開としての生命
絶えざる好奇心→興味の展開としての生命
絶えざる感性→識別の展開としての生命
絶えざる感情→記号の展開としての生命
絶えざる通常形態の知性の働き
→最高形態の知性の働きの展開としての生命
4 実験─未知への進入─としての経験
生活体と環境の相互作用としての経験
実験としての経験
未知への進入としての経験
5 予見する働き→探究する働きとしての知性
具体的示唆としての知性
意味に対する反応=意図的活動としての知性
意味を積み込まれた活動─意図的活動─としての経験
活動を意図的にする働きとしての意味
意味の所有によって統制された意図的目的的活動としての知性
第2節 探究の実践性─状況の変容としての探究─
1 Inquiryとしての探究
2 探究の定義─状況の変容としての探究─
探究の定義─状況の変容としての探究─
1つの脈絡的全体としての状況
3 状況の現実存在的変容としての探究
4 自我の感情の内における変化ではない状況の現実存在的変容としての探究
5 実験による状況の現実存在的変容としての探究
実験による状況の現実存在的変容
状況の現実存在的変容の具体
第3節 探究の共同性─言語を通しての探究の成立─
1 言語の本質─活動の共同性─
人間同士の相互作用
信号反射─言語の基礎素材─
意味を持った存在=記号としての言語
言語の本質─活動の共同性の成立─
言語─意味─共同活動
2 道具の道具としての言語
言語の協約性
道具の道具としての言語〈1〉
道具の道具としての言語〈2〉
3 言語⇔意味⇔活動の共同体
4 シンボルとサイン
シンボルとサイン〈1〉
探究におけるシンボルとサイン
探究における専門シンボルの機能
5 探究の母胎としての言語─意味
第2章 探究の展開過程と論理構造
第1節 探究の展開過程
1 探究の展開過程の定式
デューイ自身の定式
われわれの定式
2 探究の展開過程の具体
探究の先行条件:不確定的状況
第1の探究の様相:不確定的状況における困難の感得
第2の探究の様相:問題の設定─観察を通しての知性的整理─
第3の探究の様相:推断による可能的解決策=仮説の策定
第4の探究の様相:推論による可能的解決策=仮説の理論的検証
=確定
第5の探究の様相:実験による可能的解決策=仮説の事実的検証
探究の最終結果:状況の変容と知識の産出=確定的状況と真理
われわれの最終の定式
3 探究の展開過程の柔軟性
柔軟な探究の展開過程
案内役としての探究の展開過程の定式
柔軟な案内役による探究の主体の誕生
第2節 探究の論理構造
1 与件と観念の共同としての探究
与件と観念の共同としての探究
与件と観念の共同の誕生
与件と観念の相互検証
2 命題の共同としての探究
現存命題
普遍命題
命題の共同としての探究
3 観察と推理の共同としての探究
操作の共同の形態
観察と推断の共同
推断と推論の共同
推論と観察の共同
回憶と推断の共同
推論と感得の共同
4 探究の論理構造の図式
第1図式
第2図式
第3図式
第4図式
範型図式─第4図式─
5 探究の論理構造の本性
案内役としての探究の論理構造
探究の論理構造の仮説性
第3節 探究における想像の役割
1 想像の本性
可能性を把握する働きとしての想像
想像を通しての理想の企投─発見と想像─
想像を通しての全体の把握
2 推断における想像の働き
現実性から可能性への飛躍としての推断
想像を通しての推断の展開
3 推論における想像の働き
可能性から可能性への飛躍としての推論
想像を通しての推論の展開
4 直接の観察における想像の働き
観念に導かれた事実の確定としての直接の観察
想像を通しての直接の観察の展開
5 間接の観察─回憶─における想像の働き
普遍命題によって陳述されている既有の知識や経験に基づく回憶
間接の観察─回憶─における想像の働き
第3章 探究の展開を通しての経験の改造─成長─としての教育─真の知の教育─
第1節 絶えざる探究の展開を通しての経験の改造─成長─としての教育
1 知性に導かれての経験の改造
教育としての成長の条件
第1条件:意味の増加
第2条件:後続の経験を方向づける能力の増大
成長の条件としての知性─知性に導かれての経験の改造としての教育─ 317
2 絶えざる探究の展開を通しての経験の改造─成長─としての教育
探究としての知性の働き
絶えざる探究の展開を通しての経験の改造─成長─としての教育
第2節 本来の自己教育─真の知の教育の具体─
1 成長する能力としての未熟性
成長する能力としての未熟性
社会的能力としての依存性
経験から学ぶ能力としての可塑性
子供の自己教育としての教育
2 すでに激しく活動的な存在としての子供
すでに激しく活動的な存在としての子供─太陽としての子供─
生まれつきの活動傾向の自発性
子供が為す何ごとかとしての成長
3 共同活動を通しての自己教育
教育の社会性─社会による子供の形成─
共同活動を通しての人間─子供─の形成
共同活動を通しての自己教育
第3節 真の知の教育の具体
1 真の知の教育の学習内容
学習者の経験における教材の成長
熟知としての知識
情報としての知識─コミュニケートされた知識─
科学としての知識
科学の方法─探究の方法─
2 真の知の教育のための学習媒体
記号としての学習媒体の種類
記号としての学習媒体の事例
3 真の知の教育のための学習場面
組織し直された社会生活としての学校
1つの共同体生活の形式としての学校
子供が生活する場所としての学校
外に開かれた学習場面としての学校
活動的な仕事の学校への導入
4 真の知の教育のための学習形態
一斉学習
集団学習
個別学習
5 真の知の教育における教授活動
教師の指導─広義の教授活動─の必要性
教師の指導の具体?=状況設定機能
教師の指導の具体?=探究指導機能
第4節 総合学習を通しての真の知の教育
1 活動的な仕事の内実
2 活動的な仕事からの形式的な教科の展開
活動的な仕事からの形式的な教科の展開
─教科学習 vs 総合学習の克服─
活動的な仕事からの形式的な教科の展開の具体
3 総合学習を通しての真の知の教育の教育課程
教育課程の構成原理─成長の原理─
成長段階の特徴
教材選択の具体
第5節 真の知の教育のための教育評価
1 教育評価の本質
教育評価の対象
教育評価の原理
2 学習活動の目標─学習目標─の具体
一般目標1
一般目標2
教育評価に基づく授業設計素描
あとがき
