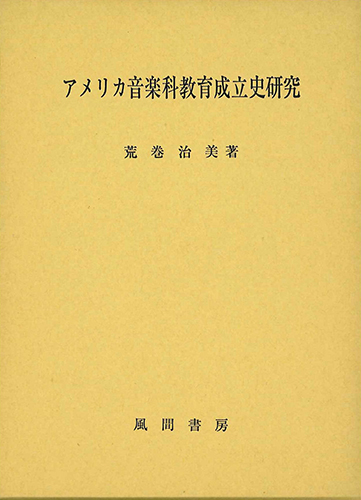
アメリカ音楽科教育成立史研究
定価12,100円(本体 11,000円+税)
世紀転換期のアメリカ音楽教育の歴史的展開を、唱歌科から音楽科への転換と捉え、成立期音楽科が芸術至上主義を本質としていたことを明らかにした意欲作。
【著者略歴】
荒巻治美(あらまき はるみ)
1968年12月 広島県に生まれる
1992年3月 広島大学教育学部教科教育学科音楽教育学専修卒業
1994年3月 広島大学大学院教育学研究科博士課程前期修了
1997年3月 広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了
学位取得 博士(教育学)
1999年4月 佐賀大学文化教育学部講師
【著者略歴】
荒巻治美(あらまき はるみ)
1968年12月 広島県に生まれる
1992年3月 広島大学教育学部教科教育学科音楽教育学専修卒業
1994年3月 広島大学大学院教育学研究科博士課程前期修了
1997年3月 広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了
学位取得 博士(教育学)
1999年4月 佐賀大学文化教育学部講師
目次を表示
序章 本研究の意義と方法
第一節 研究主題
第二節 本研究の特質と意義
第一章 音楽科教育運動の課題
第一節 世紀転換期の唱歌科教育
一 唱歌科の確立
二 唱歌科の性格
第二節 世紀転換期中等学校における音楽教育
一 中等教育改革運動と音楽科
二 中等学校音楽教育の一般的状況
第三節 音楽科教育運動の展開
第二章 C.H.ファーンズワースの音楽科教育論
―音楽的観念の形成―
第一節 C.H.ファーンズワースの課題と活動
第二節 音楽科教育の原理
一 芸術音楽の人間形成上の価値
二 音楽科教育の目的―鑑賞力の育成―
三 音楽科教育の目標―音楽的観念の形成―
四 音楽科教育の方法原理
第三節 初等音楽科教育の方法
一 音楽科教育構想上の課題
二 音楽科教育の内容系統
三 学年段階と学習領域
四 学習指導法
第四節 音楽科学習指導論
一 歌唱指導の原理と方法
二 記譜法指導の原理と方法
三 鑑賞指導の原理と方法
四 器楽演奏の指導
第五節 スネデン・ファーンズワース論争
一 論争の過程
二 音楽の価値
三 音楽科教育の目的と位置
四 音楽科教育の原理
五 論争の性格と意義
第六節 歴史的意義
第三章 A.M.フライベルガーの鑑賞教育論
―音楽批評能力の育成―
第一節 フライベルガーの課題と活動
第二節 音楽科教育の根幹―鑑賞教育―
一 音楽科の地位の向上
二 音楽科の意義
第三節 鑑賞教育の目的―音楽批評能力の育成―
一 鑑賞教育―聴取レッスン―
二 聴取レッスンの目標
第四節 学習指導の原理
一 学習指導の課題
二 聴くことによる学習―集中と識別―
三 言語による学習
四 音楽批評の基盤
第五節 聴取学習内容の編成
一 全体計画
二 第1-3学年―感覚期―
三 第4-6学年―観念連合期―
四 第7-10学年―青年期―
五 課程編成の特徴
第六節 聴取学習指導の方法
一 音楽学習指導方法の特徴
二 各学年の鑑賞指導―鑑賞能力育成の系統―
第七節 歴史的意義
第四章 F.E.クラークの低学年鑑賞教育論―聴取力育成―
第一節 クラークの課題と活動
第二節 音楽教育改革論―芸術音楽鑑賞―
第三節 鑑賞教育の原理
一 低学年音楽科における鑑賞の教育的意義
二 学校音楽と鑑賞教育
三 音楽科における鑑賞指導の目的・目標
第四節 低学年の鑑賞指導の内容と方法
一 学習活動領域
二 教材曲の選択
三 第1-3学年の鑑賞指導内容
四 学習指導の方法
第五節 歴史的意義
第五章 音楽科教育実践(1)―生活主義―
第一節 実験学校と音楽科教育運動
第二節 デューイ・スクールにおける音楽学習
一 カリキュラムの全体計画と音楽学習の位置
二 音楽的活動の内容
三 M.R.ケーンの音楽学習指導論
四 ケーンの理論とデューイ・スクールの音楽学習
五 評価
第三節 シカゴ大学教育学部附属実験学校の実践
一 音楽学習の目的
二 音楽科カリキュラム
三 性格と問題点
第四節 ミズーリ大学附属初等学校における音楽学習
一 学校教育の組織
二 音楽学習活動の位置と内容
三 特質と問題点
第五節 歴史的意義
第六章 音楽科教育実践(2)―芸術主義―
第一節 音楽科教育運動とホーレス・マン・スクール,スパイヤ・
スクール
第二節 スパイヤ・スクール・カリキュラム(1903年版)における音楽科
課程
一 学校教育における音楽科の位置
二 初等音楽科課程
第三節 ホーレス・マン・スクール(1906-7年版)における音楽科課程
一 学校教育における音楽科の位置
二 音楽科課程
三 教授過程
第四節 スパイヤ・スクール・カリキュユラム(1913年版)における音楽
科課程
一 学校教育における音楽科の位置
二 音楽科課程
第五節 歴史的意義
第七章 音楽科教科書―『進歩主義音楽双書』の性格と意義―
第一節 音楽科教育運動と『進歩主義音楽双書』
第二節 音楽科教育の原理
一 音楽科教育の目標―識別的鑑賞力の育成―
ニ 識別的鑑賞力
三 鑑賞力育成の論理
四 音楽の学習領域
第三節 音楽科教育の内容編成
一 教科書の内容編成
二 全体計画
第四節 音楽科の学習指導
一 学習指導内容の編成
ニ 学習指導法
第五節 歴史的意義
第八章 中等学校音楽科の成立と性格―NEA中等教育改造審議会音楽科委員会
報告―
第一節 中等学校音楽科教育運動
一 MTNA・NEA合同委員会報告
二 MSNCハイスクール委員会報告
三 中等教育改造審議会の課題
第二節 中等教育改造審議会音楽科委員会
第三節 中等学校における音楽科の位置と目的
一 『中等教育の根本原理』―生活主義―
二 音楽科委員会報告―芸術主義―
第四節 音楽科教育の目標
第五節 音楽科課程
一 予備的報告書における教科課程
二 本報告における音楽科課程
三 初等学校音楽科の内容
第六節 歴史的意義―中等学校音楽科の性格と意義―
第九章 初等学校音楽科の成立と性格―MSNC教育委員会報告―
第一節 MSNC教育委員会の課題と活動
第二節 委員会の基本方針
一 音楽科教育の価値
二 音楽科教育の目標
第三節 初等学校音楽科課程
第四節 歴史的意義
終章 音楽科教育の成立と性格―生活音楽表現者から芸術音楽鑑賞者へ―
史料及び引用・参考文献
謝辞
第一節 研究主題
第二節 本研究の特質と意義
第一章 音楽科教育運動の課題
第一節 世紀転換期の唱歌科教育
一 唱歌科の確立
二 唱歌科の性格
第二節 世紀転換期中等学校における音楽教育
一 中等教育改革運動と音楽科
二 中等学校音楽教育の一般的状況
第三節 音楽科教育運動の展開
第二章 C.H.ファーンズワースの音楽科教育論
―音楽的観念の形成―
第一節 C.H.ファーンズワースの課題と活動
第二節 音楽科教育の原理
一 芸術音楽の人間形成上の価値
二 音楽科教育の目的―鑑賞力の育成―
三 音楽科教育の目標―音楽的観念の形成―
四 音楽科教育の方法原理
第三節 初等音楽科教育の方法
一 音楽科教育構想上の課題
二 音楽科教育の内容系統
三 学年段階と学習領域
四 学習指導法
第四節 音楽科学習指導論
一 歌唱指導の原理と方法
二 記譜法指導の原理と方法
三 鑑賞指導の原理と方法
四 器楽演奏の指導
第五節 スネデン・ファーンズワース論争
一 論争の過程
二 音楽の価値
三 音楽科教育の目的と位置
四 音楽科教育の原理
五 論争の性格と意義
第六節 歴史的意義
第三章 A.M.フライベルガーの鑑賞教育論
―音楽批評能力の育成―
第一節 フライベルガーの課題と活動
第二節 音楽科教育の根幹―鑑賞教育―
一 音楽科の地位の向上
二 音楽科の意義
第三節 鑑賞教育の目的―音楽批評能力の育成―
一 鑑賞教育―聴取レッスン―
二 聴取レッスンの目標
第四節 学習指導の原理
一 学習指導の課題
二 聴くことによる学習―集中と識別―
三 言語による学習
四 音楽批評の基盤
第五節 聴取学習内容の編成
一 全体計画
二 第1-3学年―感覚期―
三 第4-6学年―観念連合期―
四 第7-10学年―青年期―
五 課程編成の特徴
第六節 聴取学習指導の方法
一 音楽学習指導方法の特徴
二 各学年の鑑賞指導―鑑賞能力育成の系統―
第七節 歴史的意義
第四章 F.E.クラークの低学年鑑賞教育論―聴取力育成―
第一節 クラークの課題と活動
第二節 音楽教育改革論―芸術音楽鑑賞―
第三節 鑑賞教育の原理
一 低学年音楽科における鑑賞の教育的意義
二 学校音楽と鑑賞教育
三 音楽科における鑑賞指導の目的・目標
第四節 低学年の鑑賞指導の内容と方法
一 学習活動領域
二 教材曲の選択
三 第1-3学年の鑑賞指導内容
四 学習指導の方法
第五節 歴史的意義
第五章 音楽科教育実践(1)―生活主義―
第一節 実験学校と音楽科教育運動
第二節 デューイ・スクールにおける音楽学習
一 カリキュラムの全体計画と音楽学習の位置
二 音楽的活動の内容
三 M.R.ケーンの音楽学習指導論
四 ケーンの理論とデューイ・スクールの音楽学習
五 評価
第三節 シカゴ大学教育学部附属実験学校の実践
一 音楽学習の目的
二 音楽科カリキュラム
三 性格と問題点
第四節 ミズーリ大学附属初等学校における音楽学習
一 学校教育の組織
二 音楽学習活動の位置と内容
三 特質と問題点
第五節 歴史的意義
第六章 音楽科教育実践(2)―芸術主義―
第一節 音楽科教育運動とホーレス・マン・スクール,スパイヤ・
スクール
第二節 スパイヤ・スクール・カリキュラム(1903年版)における音楽科
課程
一 学校教育における音楽科の位置
二 初等音楽科課程
第三節 ホーレス・マン・スクール(1906-7年版)における音楽科課程
一 学校教育における音楽科の位置
二 音楽科課程
三 教授過程
第四節 スパイヤ・スクール・カリキュユラム(1913年版)における音楽
科課程
一 学校教育における音楽科の位置
二 音楽科課程
第五節 歴史的意義
第七章 音楽科教科書―『進歩主義音楽双書』の性格と意義―
第一節 音楽科教育運動と『進歩主義音楽双書』
第二節 音楽科教育の原理
一 音楽科教育の目標―識別的鑑賞力の育成―
ニ 識別的鑑賞力
三 鑑賞力育成の論理
四 音楽の学習領域
第三節 音楽科教育の内容編成
一 教科書の内容編成
二 全体計画
第四節 音楽科の学習指導
一 学習指導内容の編成
ニ 学習指導法
第五節 歴史的意義
第八章 中等学校音楽科の成立と性格―NEA中等教育改造審議会音楽科委員会
報告―
第一節 中等学校音楽科教育運動
一 MTNA・NEA合同委員会報告
二 MSNCハイスクール委員会報告
三 中等教育改造審議会の課題
第二節 中等教育改造審議会音楽科委員会
第三節 中等学校における音楽科の位置と目的
一 『中等教育の根本原理』―生活主義―
二 音楽科委員会報告―芸術主義―
第四節 音楽科教育の目標
第五節 音楽科課程
一 予備的報告書における教科課程
二 本報告における音楽科課程
三 初等学校音楽科の内容
第六節 歴史的意義―中等学校音楽科の性格と意義―
第九章 初等学校音楽科の成立と性格―MSNC教育委員会報告―
第一節 MSNC教育委員会の課題と活動
第二節 委員会の基本方針
一 音楽科教育の価値
二 音楽科教育の目標
第三節 初等学校音楽科課程
第四節 歴史的意義
終章 音楽科教育の成立と性格―生活音楽表現者から芸術音楽鑑賞者へ―
史料及び引用・参考文献
謝辞
