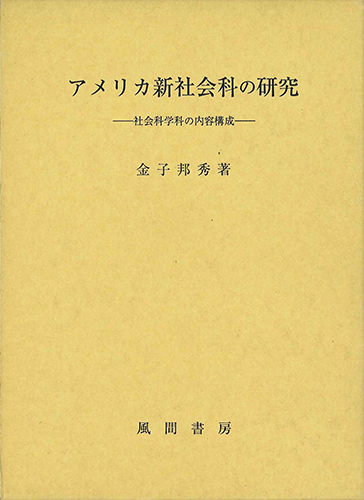
アメリカ新社会科の研究
社会科学科の内容構成
定価15,400円(本体 14,000円+税)
1960~70年代、多くの社会科学者が創造に努力を傾注したアメリカ新社会科、特に社会科学科の内容構成原理の解明を通して「社会科とは何か」を考究した好著。
【著者略歴】
金子邦秀(かねこ くにひで)
1950年 神奈川県横浜市に生まれる
1973年 早稲田大学第一文学部日本史学専攻卒業
1975年 広島大学大学院教育学研究科修士課程修了
1977年 同上博士課程中途退学
1977年 同志社大学文学部助手、のち専任講師、助教授
1989年 同志社大学文学部教授
1994年 博士(教育学)
【著者略歴】
金子邦秀(かねこ くにひで)
1950年 神奈川県横浜市に生まれる
1973年 早稲田大学第一文学部日本史学専攻卒業
1975年 広島大学大学院教育学研究科修士課程修了
1977年 同上博士課程中途退学
1977年 同志社大学文学部助手、のち専任講師、助教授
1989年 同志社大学文学部教授
1994年 博士(教育学)
目次を表示
序章 本研究の意義と方法
第一節 研究主題
第二節 本研究の特質と意義
第三節 研究方法と本論文の構成
第一章 アメリカ新社会科と社会科学教育
第一節 アメリカ新社会科の性格
一 アメリカ新社会科の成立・発展・衰退と再評価
二 アメリカ新社会科の性格
第二節 社会科学科教育内容構成の課題と類型
一 これまでの新社会科の類型論とその検討
二 社会科学科内容構成の課題と類型
第二章 単一社会科学型の内容構成
第一節 内容構成の課題と事例
第二節 全体構成―「ホルト社会科」
第三節 分析的社会科学に基づく科目・単元構成―『比較政治システム』
一 「ホルト社会科」の『比較政治システム』
二 内容構成の理論的基礎
(一)比較政治学の成立
(二)マクリディスの理論
(三)比較政治学と政治学習
三「ホルト社会科」第9学年1学期『比較政治システム』の内容構成
第四節 総合的社会科学に基づく科目・単元構成―『西洋社会の形成』
一 『西洋社会の形成』の全体構成
二 「歴史研究法」
三 分析的質問
四 「歴史研究法」それ自体を教授・学習する単元構成
―「歴史研究への導入」を事例として
五 総合的社会科学に基づく単元構成―『西洋社会の形成』
第3章「ルネサンス」を事例として
第五節 内容構成の論理と問題点
第三章 複合社会科学型の内容構成
第一節 内容構成の課題と事例
第二節 複合社会科学型に基づく教科・単元構成
―「ハーコート社会科学」
一 全体構成―「ハーコート社会科学」
(一)全体の内容構成
(二)スコープとシークエンス
(三)各学年の内容
1.幼稚園―アメリカ合衆国民の祖国―
2.第1学年―私と私たち―
3.第2学年―他の人々―
4.第3学年―コミュニティ―
5・第4学年―社会的行動と相互作用―
6.第5学年―人々の行動の文化的背景―
7.第6学年―人間と行動システム―
(四)「ハーコート社会科学」の全体的特徴
二 「ハーコート社会科学」の単元構成
(一)単元構成の類型
(二)社会科学的概念対応事実教授型の単元構成―幼稚園単元3
「ガーナ」を事例として
(三)社会科学的概念教授型の単元構成―第2学年単元7
「あなたの環境を使うこと」を事例として
(四)社会科学的概念・価値教授型の単元構成―第6学年単元3
「社会と相互作用している集団」を事例として
1.単元の目標―社会学の概念とそれに関連した価値の教授
2.単元の全体的特徴
3.小単元第4節「一つの社会の中で伝承された地位」(インド)の授業構成
4.社会科学的概念・価値教授型の単元構成の意義と特質
第三節 複合社会科学型に基づく科目・単元構成
―「フィールド中等社会科」の『合衆国史のさまざまな見方』
一 『合衆国史のさまざまな見方』の全体構成
二 『合衆国史のさまざまな見方』の単元構成
(一)総合的社会科学に基づく単元構成―単元1「再統合期を通じての
アメリカ」を事例として
(二)分析的社会科学に基づく単元・授業構成―単元4「アメリカの経済」第18章「戦時と繁栄」を事例として
三 教材の中での社会科学的見方の深化のさせ方
(一)「拡大されたテーマ」の方式
(二)「深い取り扱い」の方式
第四節 内容構成の論理と問題点
第四章 統合社会科学型の内容構成
第一節 内容構成の課題と事例
第二節 全体構成―「フィールド初等社会科」
一 「フィールド初等社会科」の全体的特色
二 「フィールド初等社会科」の各学年の内容
第三節 事象統合に基づく科目・単元構成
―「フィールド初等社会科」第7学年『人類の冒険』
一 『人類の冒険』の科目の全体構成
二 事象統合に基づく単元構成
(一)事象統合による概念構造とその指導法
(二)事象統合に基づく単元構成―単元9「技術と20世紀」の
24章「共産主義、民主主義、及び第三世界」を事例として
三 『人類の冒険』の探究プロセス
四 統合社会科学型の内容構成を支える教材―『人類の冒険』の教材の検討
第四節 内容構成の論理と問題点
第五章 総合社会科学型の内容構成
第一節 内容構成の課題と事例
第二節 総合社会科学型に基づく教科・単元構成―「シルバー社会科学」
一 全体構成―「シルバー社会科学」
(一)全体の内容構成
(二)スコープとシークエンス
二 各学年の内容と全体的特徴
(一)各学年の内容
1.第1学年『家族の中の生活』
―社会的集団の基礎である家族の学習―
2.第2学年『コミュニティの生活』―人間の生活の基本的な場
であるコミュニティの学習―
3.第3学年『人々と資源』―人々の生活を支える資源の学習―
4.第4学年『諸地域の人々』―世界の諸地域と人々の生活の学習―
5.第5学年『人々とアイデア』―人間とその環境、生活を変えてきた
発明やアイデアの学習―
6.第6学年『アメリカの人々』―南北両アメリカについての学習―
7.第7学年『人々と変化』―人々に変化をもたらす原因とこれらを
探究する仕方の学習―
8.第8学年『これがわれわれの世界だ』―地球・人間・社会と未来
についての学習―
(二)「シルバー社会科学」の全体的特徴
第三節 社会諸科学の共通の概念に基づく科目・単元構成―「シルバー
社会科学」
一 単元構成の類型
二 社会諸科学の共通概念対応事実教授型の単元構成―第2学年
『コミュニティの生活』の単元6「コミュニティはルールを作る」を 事例として
(一)単元の内容構成とその特色
(二)単元を支える社会諸科学の概念
三 社会諸科学の概念教授型単元―第6学年『アメリカの人々』
の単元1「文化を探る」の第5章「ヨーロッパの人々
アフリカの人々が新世界に来る」を事例として
第四節 内容構成の論理と問題点
第六章 総合社会・自然科学型の内容構成
第一節 内容構成の課題と事例
第二節 総合社会・自然科学型に基づく教科・単元構成―「ホウトン
社会科」
一 全体構成―「ホウトン社会科」
(一)全体の構成
(二)四つの学際的な概念に基づくスコープとシークエンス
1.四つの学際的な概念
2.スコープとシークエンス
二 各学年の内容と社会諸科学の概念
(一)各学年の内容
1.幼稚園『私』
2.第1学年『われわれがすること』
3.第2学年『われわれのまわりの世界』
4.第3学年『われわれはだれなのか』
5.第4学年『惑星地球』
6.第5学年『合衆国』
7.第6学年『人々の生活様式』
(二)「ホウトン社会科」のカリキュラムの意義と特質
1.「ホウトン社会科」の学年段階的特徴
2.各学年で教授・学習される社会諸科学の概念
第三節 集団・環掛こ基づく科目・単元構成
一 集団に基礎を置く単元構成―第3学年『われわれはだれなのか』の
単元3「集団とは何か」を事例として
二 環境に基礎をおく単元構成―第4学年『惑星地球』の単元4
「あなたの周りの水」を事例として
三 ミクロからマクロへの単元構成―第5学年『合衆国』の単元4
「グローバル・コミュニティにおける合衆国」を事例として
四 集団・環境に基づく単元構成―第6学年『人々の生活様式』
の単元3「どのように文化は多様化し変化するか」を事例として
第四節 内容構成の論理と問題点
第七章 社会科学科内容構成の論理と問題点
終章 アメリカ新社会科の特徴と問題点
資料及び参考文献
あとがき
第一節 研究主題
第二節 本研究の特質と意義
第三節 研究方法と本論文の構成
第一章 アメリカ新社会科と社会科学教育
第一節 アメリカ新社会科の性格
一 アメリカ新社会科の成立・発展・衰退と再評価
二 アメリカ新社会科の性格
第二節 社会科学科教育内容構成の課題と類型
一 これまでの新社会科の類型論とその検討
二 社会科学科内容構成の課題と類型
第二章 単一社会科学型の内容構成
第一節 内容構成の課題と事例
第二節 全体構成―「ホルト社会科」
第三節 分析的社会科学に基づく科目・単元構成―『比較政治システム』
一 「ホルト社会科」の『比較政治システム』
二 内容構成の理論的基礎
(一)比較政治学の成立
(二)マクリディスの理論
(三)比較政治学と政治学習
三「ホルト社会科」第9学年1学期『比較政治システム』の内容構成
第四節 総合的社会科学に基づく科目・単元構成―『西洋社会の形成』
一 『西洋社会の形成』の全体構成
二 「歴史研究法」
三 分析的質問
四 「歴史研究法」それ自体を教授・学習する単元構成
―「歴史研究への導入」を事例として
五 総合的社会科学に基づく単元構成―『西洋社会の形成』
第3章「ルネサンス」を事例として
第五節 内容構成の論理と問題点
第三章 複合社会科学型の内容構成
第一節 内容構成の課題と事例
第二節 複合社会科学型に基づく教科・単元構成
―「ハーコート社会科学」
一 全体構成―「ハーコート社会科学」
(一)全体の内容構成
(二)スコープとシークエンス
(三)各学年の内容
1.幼稚園―アメリカ合衆国民の祖国―
2.第1学年―私と私たち―
3.第2学年―他の人々―
4.第3学年―コミュニティ―
5・第4学年―社会的行動と相互作用―
6.第5学年―人々の行動の文化的背景―
7.第6学年―人間と行動システム―
(四)「ハーコート社会科学」の全体的特徴
二 「ハーコート社会科学」の単元構成
(一)単元構成の類型
(二)社会科学的概念対応事実教授型の単元構成―幼稚園単元3
「ガーナ」を事例として
(三)社会科学的概念教授型の単元構成―第2学年単元7
「あなたの環境を使うこと」を事例として
(四)社会科学的概念・価値教授型の単元構成―第6学年単元3
「社会と相互作用している集団」を事例として
1.単元の目標―社会学の概念とそれに関連した価値の教授
2.単元の全体的特徴
3.小単元第4節「一つの社会の中で伝承された地位」(インド)の授業構成
4.社会科学的概念・価値教授型の単元構成の意義と特質
第三節 複合社会科学型に基づく科目・単元構成
―「フィールド中等社会科」の『合衆国史のさまざまな見方』
一 『合衆国史のさまざまな見方』の全体構成
二 『合衆国史のさまざまな見方』の単元構成
(一)総合的社会科学に基づく単元構成―単元1「再統合期を通じての
アメリカ」を事例として
(二)分析的社会科学に基づく単元・授業構成―単元4「アメリカの経済」第18章「戦時と繁栄」を事例として
三 教材の中での社会科学的見方の深化のさせ方
(一)「拡大されたテーマ」の方式
(二)「深い取り扱い」の方式
第四節 内容構成の論理と問題点
第四章 統合社会科学型の内容構成
第一節 内容構成の課題と事例
第二節 全体構成―「フィールド初等社会科」
一 「フィールド初等社会科」の全体的特色
二 「フィールド初等社会科」の各学年の内容
第三節 事象統合に基づく科目・単元構成
―「フィールド初等社会科」第7学年『人類の冒険』
一 『人類の冒険』の科目の全体構成
二 事象統合に基づく単元構成
(一)事象統合による概念構造とその指導法
(二)事象統合に基づく単元構成―単元9「技術と20世紀」の
24章「共産主義、民主主義、及び第三世界」を事例として
三 『人類の冒険』の探究プロセス
四 統合社会科学型の内容構成を支える教材―『人類の冒険』の教材の検討
第四節 内容構成の論理と問題点
第五章 総合社会科学型の内容構成
第一節 内容構成の課題と事例
第二節 総合社会科学型に基づく教科・単元構成―「シルバー社会科学」
一 全体構成―「シルバー社会科学」
(一)全体の内容構成
(二)スコープとシークエンス
二 各学年の内容と全体的特徴
(一)各学年の内容
1.第1学年『家族の中の生活』
―社会的集団の基礎である家族の学習―
2.第2学年『コミュニティの生活』―人間の生活の基本的な場
であるコミュニティの学習―
3.第3学年『人々と資源』―人々の生活を支える資源の学習―
4.第4学年『諸地域の人々』―世界の諸地域と人々の生活の学習―
5.第5学年『人々とアイデア』―人間とその環境、生活を変えてきた
発明やアイデアの学習―
6.第6学年『アメリカの人々』―南北両アメリカについての学習―
7.第7学年『人々と変化』―人々に変化をもたらす原因とこれらを
探究する仕方の学習―
8.第8学年『これがわれわれの世界だ』―地球・人間・社会と未来
についての学習―
(二)「シルバー社会科学」の全体的特徴
第三節 社会諸科学の共通の概念に基づく科目・単元構成―「シルバー
社会科学」
一 単元構成の類型
二 社会諸科学の共通概念対応事実教授型の単元構成―第2学年
『コミュニティの生活』の単元6「コミュニティはルールを作る」を 事例として
(一)単元の内容構成とその特色
(二)単元を支える社会諸科学の概念
三 社会諸科学の概念教授型単元―第6学年『アメリカの人々』
の単元1「文化を探る」の第5章「ヨーロッパの人々
アフリカの人々が新世界に来る」を事例として
第四節 内容構成の論理と問題点
第六章 総合社会・自然科学型の内容構成
第一節 内容構成の課題と事例
第二節 総合社会・自然科学型に基づく教科・単元構成―「ホウトン
社会科」
一 全体構成―「ホウトン社会科」
(一)全体の構成
(二)四つの学際的な概念に基づくスコープとシークエンス
1.四つの学際的な概念
2.スコープとシークエンス
二 各学年の内容と社会諸科学の概念
(一)各学年の内容
1.幼稚園『私』
2.第1学年『われわれがすること』
3.第2学年『われわれのまわりの世界』
4.第3学年『われわれはだれなのか』
5.第4学年『惑星地球』
6.第5学年『合衆国』
7.第6学年『人々の生活様式』
(二)「ホウトン社会科」のカリキュラムの意義と特質
1.「ホウトン社会科」の学年段階的特徴
2.各学年で教授・学習される社会諸科学の概念
第三節 集団・環掛こ基づく科目・単元構成
一 集団に基礎を置く単元構成―第3学年『われわれはだれなのか』の
単元3「集団とは何か」を事例として
二 環境に基礎をおく単元構成―第4学年『惑星地球』の単元4
「あなたの周りの水」を事例として
三 ミクロからマクロへの単元構成―第5学年『合衆国』の単元4
「グローバル・コミュニティにおける合衆国」を事例として
四 集団・環境に基づく単元構成―第6学年『人々の生活様式』
の単元3「どのように文化は多様化し変化するか」を事例として
第四節 内容構成の論理と問題点
第七章 社会科学科内容構成の論理と問題点
終章 アメリカ新社会科の特徴と問題点
資料及び参考文献
あとがき
