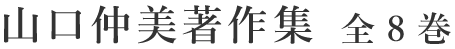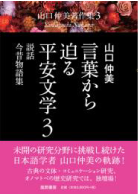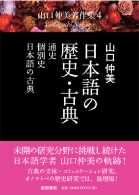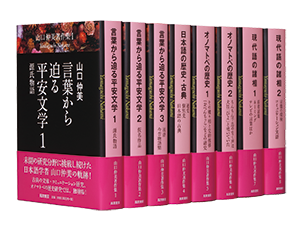
未開の研究分野に挑戦し続けた日本語学者 山口仲美の軌跡!
古典の文体・コミュニケーション研究、オノマトペの歴史研究では、独壇場!
A5判・上製カバー装 各巻平均 665頁 総頁 5316頁
各巻 定価 6,380円(税込) 揃定価 51,040円(税込)(分売可)パンフレットのダウンロード
[PDFダウンロード]
お知らせ
2022年10月25日 第10回(令和4年)「2022日本学賞」に山口仲美先生がご選出されました。対象となる業績は「日本語に関する独創的な研究」です。 おめでとうございます。
2021年11月3日 令和3年度の文化功労者に山口仲美先生がご選出されました。日本語学の分野では女性初のご選出です。 おめでとうございます。
講演会のお知らせ
ラジオ出演のお知らせ
2019年7月25日(木) 午前4時~5時
NHKラジオ第1放送「ラジオ深夜便」に山口仲美先生が出演されました。
・石澤典夫さんのコーナー「私のアート交遊録」『古典が教えてくれた生きるチカラ』
2019年3月30日(土)(無事終了いたしました)
朝日ブックアカデミー3月講座(主催 朝日新聞東京本社メディアビジネス局)にて、山口仲美先生が「言葉から迫る平安文学」をテーマに講演されました。
講演の内容につきましては、4月12日(金)の朝日新聞 朝刊(関東)に紙上採録が掲載されました。
また、4月14日に好書好日(https://book.asahi.com/article/12285398)のウェブサイトにて、当日の様子がアップされております。
どうぞご覧ください。
2019年6月8日(土)(無事終了いたしました)
語彙・辞書研究会 第55回研究発表会にて、山口仲美先生が「平安時代の男と女のコミュニケーション」 と題して講演をされました。
語彙・辞書研究会 ホームページ
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/affil/goijisho/
メディアで紹介されました
- 2022年5月4日
- 日本経済新聞(朝刊)大学面にてインタビュー記事が掲載されました。「日本の古典、世界に通ず」
- 2022年2月19日
- 静岡新聞(朝刊)コラム「大自在」にて山口仲美先生の記事が掲載されました。
- 2021年11月2日
- 読売新聞(朝刊)教育・投書面にてインタビュー記事が掲載されました。「学ぶ 育む 日本語 好きになる授業を 文化功労者に決まった山口仲美さん」
- 2021年9月14日
- 月刊「書写書道」2021年5月号から2021年7月号(日本武道館 発行)にかけて、「リレーエッセイ 若者へのメッセージ37」(全3回)が連載されました。
- 2021年9月10日
- 季刊「日本語学」第40巻第3号 秋号(明治書院 発行)より、エッセイ形式の新連載「日本語が消滅する時」(全8回)がスタートいたします。第1回目のテーマは、「おしよせる言語消滅の波」です。
- 2020年12月8日
- 「巨福」第112号(臨済宗建長寺派宗務本院 制作・発行)にて、インタビュー記事が掲載されました。「シリーズ・生きる ひと紀行58 わたしの二つの転機」
- 2020年12月1日
- 「ゆうゆう」第226号(一般財団法人 日本老人福祉財団 発行)にて、インタビュー記事が掲載されました。「ゆうゆうインタビュー206 山口仲美さん」
- 2020年9月25日
- 好書好日のウェブサイトにて、インタビュー記事が掲載されました。「古典文学、オノマトペの研究など、山口仲美さんの著作集 全8巻が完結!
記念インタビュー」
記事は、以下のURLよりご覧になれます。
https://book.asahi.com/article/13672414 - 2019年12月11日
- 日刊ゲンダイ〈日刊〉第12957号にて、山口仲美先生の記事が掲載されました。「愉快な“病人”たち 大腸がん・膵臓がん 手術を受けると意思決定できたのは予定日の2日前だった 日本語学者 山口仲美さん」
- 2019年11月30日
- 西日本新聞にて、『山口仲美著作集 5 オノマトペの歴史1』が紹介されました。「担当記者の激オシ本 ワクワクする トリビアの宝庫」
- 2019年10月12日
- 朝日新聞朝刊にサンヤツ広告を掲載いたしました。『山口仲美著作集 5 オノマトペの歴史1』
- 2019年9月18日
- 雑誌『ラジオ深夜便』2019年10月号(通巻231号)にて、山口仲美先生および山口仲美著作集が紹介されました。「アンカーエッセー 人生出会い旅 60 ~山口仲美さん」
- 2019年5月18日
- 朝日新聞(朝刊)にサンヤツ広告を掲載いたしました。『山口仲美著作集 4 日本語の歴史・古典』
- 2019年4月14日
- 好書好日のウェブサイトにて、朝日ブックアカデミー3月講座の当日の様子が掲載されました。「恋人と喧嘩別れしたら?
「平安文学」に学ぶ男と女のコミュニケーション術! 日本語学者・山口仲美さん講演|好書好日」
記事は、以下のURLよりご覧になれます。
https://book.asahi.com/article/12285398 - 2019年4月12日
- 朝日新聞(朝刊(関東))にて、朝日ブックアカデミー3月講座の紙上採録が掲載されました。「言葉から迫る平安文学」
- 2019年3月11日
- 出版ニュース 3中旬号、情報区にて、山口仲美著作集が紹介されました。
- 2019年3月9日
- 図書新聞(3390号)にて、『山口仲美著作集 1 言葉から迫る平安文学1 源氏物語』の書評が掲載されました。
「言語学的な方法に拠る分析の数々 山口仲美の長く充実した研究人生の、豊饒なその成果」 評者は浅川哲也先生(首都大学東京教授)です。 - 2019年3月2日
- 東京新聞(夕刊)文化面、土曜訪問にてインタビュー記事が掲載されました。「日本語 消滅する前に 古典研究の著作集を刊行中」
インタビュー記事はは以下のURLよりご覧になれます。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/culture/doyou/CK2019030202000280.html - 2019年1月18日
- 週刊読書人に『言葉から迫る平安文学 3 説話・今昔物語集』が紹介されました。
- 2018年12月26日
- 日本経済新聞(夕刊)にインタビュー記事が掲載されました。
「日本語学者・山口仲美の著作集刊行」 - 2018年11月16日
- 週刊読書人(特集 全集・講座・シリーズ)に先生が執筆されたエッセイが掲載されました。
「全集・著作集が役に立つ時 筆者が考える3つのメリット」 - 2018年11月11日
- 東京新聞に紹介されました。「出版情報」
- 2018年11月5日
- 秋田魁新報に紹介されました。「日本語論、硬軟織り交ぜ 山口仲美著作集発刊」

山口 仲美(やまぐち なかみ)
1943年静岡県生まれ。お茶の水女子大学卒業。
東京大学大学院修士課程修了。文学博士。
現在 埼玉大学名誉教授。
専門 日本語学( 日本語史・古典の文体・オノマトペの歴史)
著書
『平安文学の文体の研究』( 明治書院、第12回金田一京助博士記念賞)、『平安朝の言葉と文体』(風間書房)、 『日本語の歴史』(岩波書店、第55回日本エッセイスト・クラブ賞)、 『犬は「びよ」と鳴いていた』(光文社)、『日本語の古典』(岩波書店)など多数。 2008年紫綬褒章、2016年瑞宝中綬章受章。専門分野関係のテレビ・ラジオ番組にも多数出演。
好評の既刊
第1巻 言葉から迫る平安文学1源氏物語
第一巻は、言葉や文体、そしてコミュニケーションといった言語学的な立場から、『源氏物語』のさまざまな問題を追究。三部から成る。
Ⅰ部は、「『源氏物語』男と女のコミュニケーション」。源氏物語に登場する男と女は、どんなコミュニケーションをとっていたのか? その様相を具体的に解明している。
Ⅱ部は、「『源氏物語』の言葉と文体」。比喩や象徴詞(=オノマトペ)や形容語などに注目して、『源氏物語』独自の問題を解明する。
Ⅲ部は、「文章・文体研究の軌跡と展望」。『言葉から迫る平安文学』1巻・2巻・3巻に共通する著者の立場を明確にしている。 文章・文体研究の草創期の状態も明らかになる。
第2巻 言葉から迫る平安文学2仮名作品
第二巻は、平安時代の仮名で書かれた『源氏物語』以外の日記・随筆・物語を対象に、言語学的側面からさまざまな問題を追究。四部から成る。Ⅰ部は、導入部的な論。
Ⅱ部は、「物語と日記の言葉と文体」。平安文学作品全体の文体にかかわる問題と、竹取物語・和泉式部日記といった個別の作品の言葉と文体にかかわる問題を取り扱う。
Ⅲ部は、「『枕草子』新しい読み方」。『枕草子』をマナー集として読むという新しい読み方を提示し、『枕草子』の魅力を味わう。
Ⅳ部は、「研究余滴」。仮名文学作品を読んでいて、疑問に思ったこと、感動したこと、主張したくなったことなどを、エッセイ風にまとめたものを収録。
第3巻 言葉から迫る平安文学3説話・今昔物語集
第三巻は、説話文学全般およびその中で傑出している『今昔物語集』を対象に、言葉や文体あるいは表現方法を追究した巻。三部から成る。
Ⅰ部は、「説話文学の言葉と文体」。直喩法などの表現技法に的を絞って、従来とは違った出典文献との比較という方法で手堅く今昔物語集の文体に迫った論などを収録。
Ⅱ部は、「『今昔物語集』の表現方法」。『今昔物語集』の表現方法に着目し、読者を魅了してやまない表現方法の秘密を解明。
Ⅲ部は、「『今昔物語集』にみる生きる力」。読者に勇気を与え、生きる力を与えてくれる話をセレクトし、原文・現代語訳・解説を行ない、今昔物語集の持つエネルギーをあぶりだす。
第4巻 日本語の歴史・古典通史・個別史・日本語の古典
第四巻は、日本語の史的推移を追究した著書や論文を収録したもの。三部から成る。
Ⅰ部は、「日本語の歴史―通史―」。日本語はどんなふうに歩んで、現代にいたるのか? 日本語の将来を担うすべての人々にむけて、その史的推移をわかりやすく解説。
Ⅱ部は、「日本語の歴史―個別史―」。日本語を文体、語彙、命名、翻訳語という個別的な観点からクローズアップして、その史的推移を解明。日本人の感覚・感情のあり方、その時代の志向などを浮き彫りにする。
Ⅲ部は、「日本語の古典」。言葉や表現といった今までとは違った日本語学的な切り口から、古典作品を通史的に取り上げ、その魅力を解き明かす。
この巻は、遠い昔の日本人の熱い血と切なる思いをお伝えできることを願って執筆されている。
第5巻 オノマトペの歴史1その種々相と史的推移・「おべんちゃら」などの語史
著作集5・6『オノマトペの歴史』二巻は、オノマトペ(=擬音語・擬態語)のさまざまな性質や史的推移を明らかにした論文やエッセイを収録。第五巻はⅠⅡⅢの三部から成る。
Ⅰ部は、「オノマトペの種々相」。『源氏物語』や『今昔物語集』、狂言やコミックなど作品別・ジャンル別にとらえた時に顕著に現われるオノマトペの特色・機能を解明。研究のエキスをぎゅっと詰めこんだ二〇のコラムも、おすすめ。
Ⅱ部は、「オノマトペの史的推移」。語彙・語音構造・意味・語法などの面からオノマトペの史的推移を追究。男女の泣き方を表すオノマトペ、動物の声を写す擬音語、楽器の音を表す擬音語など、興味津々の史的推移が解き明かされる。
Ⅲ部は、「『おべんちゃら』などの語史」。「いちゃもん」「おべんちゃら」「どんぶり」「パチンコ」などオノマトペにルーツを持つと思われる言葉を対象に、その語史を追究。びっくりするような言葉のルーツが明らかに。
第6巻 オノマトペの歴史2ちんちん千鳥のなく声は・犬は「びよ」と鳴いていた
著作集6『オノマトペの歴史2』は、オノマトペ(=擬音語・擬態語)のうち、鳥の鳴き声や獣の声を写す言葉の推移の解明に特化した巻。ⅠⅡⅢの三部から成る。
Ⅰ部は、「ちんちん千鳥のなく声は」。カラスやウグイスなど一二種類の鳥の鳴き声を写す擬音語の歴史を辿る。現代人が予想もしなかったような鳴き声から、その時代の人々の暮らしや民話・民間信仰まで解明されてゆく。
Ⅱ部は、「犬は『びよ』と鳴いていた」。時代とともに推移する擬音語・擬態語の一般的な性格を明らかにし、犬や猫、牛などの獣の声の変化とその原因を追究。日本人独特の感性と文化が光る予想外で楽しい話がいっぱい。
Ⅲ部は、「オノマトペ研究余滴&エッセイ」。妖しげな言葉、「ちんちんかもかも」はどこから出て来た言葉? 「ひゅうどろどろ」は、なぜお化けの出る合図に? オノマトペがあるからこそ可能になる豊かな日本語の世界がここに。
第7巻 現代語の諸相1若者言葉・ネーミング・テレビの言葉ほか
著作集7『現代語の諸相1』は、若者言葉・あだ名・広告表現・テレビの言葉などの現代語をテーマにした著書・論文を中心としている。ⅠⅡⅢⅣの四部から成る。
Ⅰ部は、「若者言葉に耳をすませば」。若者言葉はどんな特質を持っているのか? 本音全開の座談会を中心に、若者言葉を創りだす方式・特色を実証的に追究していく。
Ⅱ部は、「ネーミングと広告」。命名行為の秘密を解くカギの詰まった「あだ名」。傑作な「あだ名」の条件とは? また、新聞・ラジオ・テレビにおける広告表現の推移も解明。
Ⅲ部は、「テレビの言葉」。刻々と変わりゆく言葉の先端を視聴者の立場とテレビを作る立場からとらえている。どうかあなたもテレビで出題された問題を解いていただきたい。
Ⅳ部は、「現代語の問題&エッセイ」。日本語教育や敬語表現などに関する論を収録。滅入っている人を元気にさせるのは「言葉の力」。そんなエッセイも最後に収めておいた。
第8巻 現代語の諸相2言葉の探検・コミュニケーション実話
著作集8『現代語の諸相2』は、ユニークな言葉、中国人や医者とのコミュニケーションをとりあげ、エッセイタッチで書いた単行本を収録している。ⅠⅡⅢⅣの四部から成る。
Ⅰ部は、「言葉の探検」。ドキッとするような七二の言葉や表現をとりあげ、その特性を解明。冒頭に付いている問題を解いてから本文に読み進むと、論旨が一層明快に。
Ⅱ部は、「言葉の先生、北京を行く」。中国人の大学教師・リーさんを中心に、彼らのコミュニケーション術やその能力の高さにたじたじとなる話を収録。
Ⅲ部は、「大学教授がガンになってわかったこと」。命に係わる選択を、どのようなコミュニケーションで解決したのか。納得のいく治療を受けるための患者の心得を伝授。
Ⅳ部は、「身辺エッセイ&経歴」。身の回りで起きた出来事、私の出会ったステキな先生、日々の思いなどを綴る。最後に、著者のこれまでの歩みを網羅した経歴を収めた。